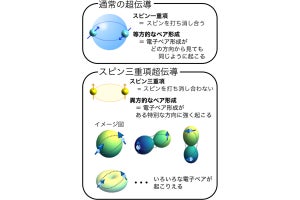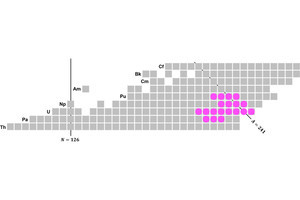日本原子力研究開発機構(原子力機構)は、その化学的特性から“電池の活物質として潜在的な可能性をもつ”とされるウランを用いた「ウラン蓄電池」を世界で初めて開発。充放電性能を確かめたと3月13日に発表した。
同成果は、原子力機構 原子力科学研究所 NXR開発センター 大容量蓄電池開発特別チームの大内和希研究副主幹、同・植野雄大研究員、同・渡邉雅之研究主席らの研究チームによるもの。今回の技術に関しては、2024年11月に特許出願が行われた。
ウランの同位体の235Uを原子力発電の燃料として利用するためには、工程として「濃縮」を経る必要がある。その結果生成されるのが、235Uの含有量が低い「劣化ウラン」だ。
原子力規制庁が2024年5月に発表した「我が国における令和5年(2023年)の保障措置活動の実施結果」によれば、日本国内に約1万6,000トン、世界全体では約160万トンの劣化ウランが存在する。しかし、現在の原子力発電の主力である軽水炉においては、劣化ウランは燃料として利用できない。そのため増加の一途をたどっており、放射性物質として厳重に保管する以外にないのが現状だ(高速増殖炉の技術が確立されれば、燃料として利用できるようになる可能性がある)。
ウランは核分裂物質であるため、一般的には負のイメージを持たれやすいが、その優れた化学的特性として、酸化数が3価から6価までと幅広いことが挙げられる。この酸化数の多様性は、酸化還元反応を利用した充放電を可能とする活物質としての応用ポテンシャルを示唆するものである。
2000年代初頭にウランを活物質とする蓄電池の概念が提唱されたものの、実用的な性能に関する報告はこれまでなされていなかった。このような背景を踏まえて研究チームは今回、利用価値が見出されていなかった劣化ウランに新たな資源としての価値を与えるべく、ウランを活物質とした蓄電池を開発してその性能を実証することにした。
2000年代初頭に唱えられた概念では、正負両極にウランを用いることが想定されていた。それに対して今回開発されたウラン蓄電池では、負極にはウランが用いられているが、正極には鉄が活物質として採用された点が特徴だ。
これは、鉄を用いることで正極の電解液を安定化できることに加え、電圧の向上が見込まれるためである。また電解液は、有機溶媒とイオン液体を混合したものが用いられている(この電解液中において、ウランと鉄はそれぞれ溶解し、陽イオンの状態で存在している)。
ウラン蓄電池の充放電には、ウランイオンと鉄イオンそれぞれの酸化数の変化が利用されている。充電時には、正極において鉄イオンの酸化数が2価から3価へと変化し、電子が放出される。この電子は回路を経由して負極へと到達し、ウランイオンの酸化数を4価から3価に変化させる。このように正極から負極へ電子の流れ(電流)を発生させ、ウランイオンと鉄イオンの化学状態を変えることで、電気エネルギーを化学エネルギーに転換して蓄えることが可能だ。
一方、ウラン蓄電池を放電させるときは、逆の反応を起こす。つまり、ウランイオンが3価から4価へ、鉄イオンが3価から2価へ変化することで回路に電流が発生し、化学エネルギーを電気エネルギーとして取り出せるのである。
実験では、充電前後の負極側のウランを含む電解液の変化が確認された。充電前は緑色で、ウランイオンが4価の状態で存在していることが示されている。充電が進行すると、電解液は徐々に濃い紫色に変わる様子が確認された。これは、ウランイオンが4価から3価へと変化したこと伴うものと考えられる。放電を始めると液色は徐々に緑色へと戻ることも観察された。
-

ウラン蓄電池での充電・放電での負極側の電解液の色の変化。ウランを用いた電解液を負極側に入れて充電すると(左)、液色は緑色から濃い紫色に変化し(右)、放電すると緑色に戻る
(出所:原子力機構Webサイト)
今回試作されたウラン蓄電池の起電力は1.3Vで、一般的なアルカリ乾電池(1.5V)に近い値だった。充電後の蓄電池をLEDにつなぐと問題なく点灯し、蓄電池として機能することが実証された。また今回の実験では、充放電が10回繰り返されたが、蓄電池の性能は顕著な変化を示さなかったという。
さらに、負極、正極共に電解液中に析出物が確認されなかったことから、ウラン蓄電池では安定して充放電を繰り返せる可能性が示唆されたとのこと。以上の実験結果から、ウランを活物質とする蓄電池の充放電性能が世界で初めて確認された。
研究チームは今後、電解液を循環させることでウラン蓄電池の容量(電気を蓄えられる量)の向上をめざす。加えて、循環させる電解液の量やウランと鉄の濃度を増やすことによる大容量化の可能性や、蓄電池を構成する電極や隔膜の最適な材料に関する検討を進めていく。
大容量化が達成され、国内に保管されている劣化ウランを蓄電池として実用化・社会実装できれば、メガソーラーの需給調整機能など、新たな役割が期待できるとしている。