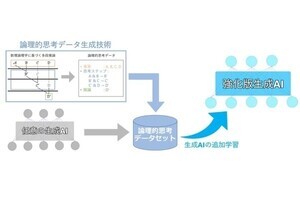日立製作所が2020年以来、5年ぶりにCESの会場に戻ってきた。日立のグループ企業による多彩なソリューションと、R&D段階の先進技術をブースに集めて、日立が推進するLumada(ルマーダ)事業のグローバル展開を多角的に見せた。
生成AIやデジタルツインに関連する話題が脚光を浴びたCES 2025。そこに出展した日立は、どんな収穫を得たのか。Hitachi Digital(日立デジタル)のプレジデント兼COOであるガジェン・カンディア氏に話を聞いた。
先進技術でインダストリアルワークを効率化
最初に筆者が取材した日立ブースの展示を振り返る。
「インダストリアルメタバース」はデジタル3D空間の中で、老朽化したインフラの点検保守作業を効率よく、かつ高い精度を確保しながら実現するソリューションだ。ブースでは下水道のパイプライン検査の事例を見せていた。
ベースになるのはAIモデルによる画像認識。下水管内部を撮影した動画データを元に3D空間のモデルを作成し、その上にAIによる検査結果のレポートを重ね合わせて、破損箇所を特定する。AIによる検査だけでは十分な精度が保てないため、さらに検査士が画像を目で確認しながら破損箇所のダブルチェックを行うという作業工程を想定している。
このとき、熟練ではない検査士が任務に就く場合は、熟練者と協調して同時に目視確認を行うことを推奨している。未熟練者の仕事を熟練者がダブルチェックすることで、保守点検作業のミスが防げるだけでなく、未熟練者のトレーニングにもなるからだ。
通常はAIから未熟練者、そして次に熟練者……という3段階のステップで確認を行うが、検査士2名はメタバース空間内で同時に作業できるため、効率アップにもつながる。
インダストリアルメタバースのデモンストレーションは、まだPoC(実証実験)の段階にあるという。検査結果のレポートを出力する段階では、一般的なLLM(今回はChatGPT)を使っているが、下水管の画像データを集めて破損箇所を特定するという特殊な使い方になるため、これを導き出すアルゴリズムは日立が独自にチューニングしたものを試作している。
生成AIやARの活用にも注力
続く事例は、AIとAR/VRヘッドセットを活用する遠隔検査のソリューションだ。
展示では空調機器のコンプレッサーを修理・点検する事例として、AR空間上に表示されるガイダンスに沿って、重点箇所を確認しながら作業を進めるデモンストレーションを見せていた。ヘッドセットに搭載したカメラでコンポーネントを撮影し、解析して補修が必要な箇所を特定し、ARナビゲーションを頼りに修理方法を検討できるというものだ。
または、現場まで赴く前に3Dモデルを見ながら作業の内容を確認後、実際の作業に移るという活用方法もある。
このソリューションは現在も日立が開発を進めている。展示スタッフによると「AIの認識、日立が作っている部分はPoCを通じて実績が積み上がってきた。それなりに使えるレベルに到達しつつある」という。
3件めの展示は、数百ページのボリュームにもなる産業用機器等のサービスマニュアルのデータを元に、生成AIでフォールトツリー型式のトラブルシューティングマニュアルをつくるサービスの事例だ。フォールトツリー(Fault Tree)とは、製品や設備に発生したトラブルの原因を解析する手法のこと(編注:「故障の木解析」とも呼ばれる)。こちらはまだR&D段階の技術としてCESに展示した。
エンジニアが取りためてきたノート、ヒストリカルログなどのデータも集積してマニュアルに織り込んだり、インターフェースはAIエージェントとの音声対話型に仕上げたりすることも可能だという。出力フォーマットもトラブルシューティングマニュアルだけでなく、専門用語辞書を生成するケースも検討されている。
CESで見せた、日立の「引き出しの多さ」
いま、社会の至るところでデジタルトランスフォーメーション(DX)が加速する中、日立はパワーグリッドやデータセンター、AIといった、DXの実現に欠かせないエッセンシャルな領域の知見と経験を幅広く保有している。世界最大のエレクトロニクスショーであるCESに出展することで、「顧客が必要とするDXの可能性を、日立が全方位からサポートできることを知ってもらうこと」が、日立が5年ぶりにCESに出展した背景にある狙いだと、ガジェン氏は説く。
近年のCESにはコンシューマーエレクトロニクスの範ちゅうを超えた、最先端のあらゆるデジタルテクノロジーが集まってくる。商談や視察の目的でCESに集まるトレードビジターの期待も幅広い。ゆえに、さまざまなDXのソリューションを見せた日立のブースも好評だったようだ。
「かつてはBtoC、BtoBの領域が明快に分かれていた。昨今のデジタルテクノロジーのトレンドはボーダレスになりつつある。ブースに足を運んだ顧客には、日立がモビリティからグリーンテックまで、さまざまな課題を解決できる会社であることが伝わったはずだ」(ガジェン氏)
拡大する協創提案
日立は過去10年間、ビジネスの方向転換を大胆に図ってきた。イタリアの鉄道信号保安会社であるアンサルドSTS(Ansaldo STS)や、フランスのタレス(Thales) グラウンドトランスポーテーションシステムズ部門、デジタルエンジニアリングのエキスパートである米国のグローバルロジック(GlobalLogic)、スイスABBのパワーグリッド部門(エネルギー)などを買収した後も、ていねいにビジネスの構造を改革した。
「日立が有するテクノロジーやソリューションを単体で見せるだけでなく、ひとつにつなぎ合わせたときに生まれる提案」を顧客に見せることにも注力している、とガジェン氏は語る。
たとえば、日立は電車の車両メーカーだが、列車を安全かつ効率よく走らせるためには、パワーグリッドや運行管理のデジタル技術と高度に統合する必要がある。グループが持つさまざまなテクノロジーのシナジーから、カスタマーニーズに寄り添う提案を「協創=コクリエーション」するという理念に基づき、近年の日立は成長を遂げてきた。
そのひとつの事例が、鉄道の保守点検システムだ。日立が持つデジタルエンジニアリングの技術を活かし、毎秒40,000件の画像データを記録、AIを使って自動解析しながら鉄道インフラとその周辺環境のメンテナンスを高度に実現するシステムを米NVIDIAと共同開発した。従来は人力で行ってきた鉄道網の保守点検の作業を効率化できる、日立ならではの新しい価値提案だ。
CESに出展してガジェン氏はことに、AI領域で日立に寄せられる期待が非常に大きいことを知ったという。AIテクノロジーによるDX推進について、日立にはITシステムなどバックオフィスの効率化と、インダストリアルワーカーをはじめとするフロントラインの業務に携わる、プロフェッショナルの生産性向上を図るノウハウがあるとガジェン氏は語る。
また、デジタルやAIといった技術を既存のシステムに統合して効率化を図ったり、あるいは顧客の求める新しい価値を協創したりすることにも、日立は力を入れている。この点は、前述のCES 2025の展示デモで具体を示した。
今後もDXが加速し、「AIテクノロジーの時代」に突入したときに、日立はますます強い存在感を放つ企業になるだろう。