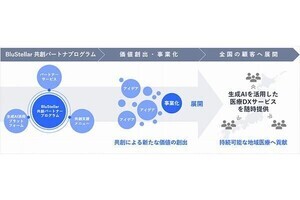近年、日本の全国各地で甚大な被害をもたらす自然災害が頻発している。その際、高齢者や障がい者などの災害要配慮はさまざまな理由によって逃げ遅れてしまうことがあるという。
また、要配慮者のうち、自ら避難することが困難で特に支援が必要な避難行動要支援者については、災害対策基本法の改正により、「誰と(支援者)」、「どうやって(避難手段)」、「どこに(避難先)」避難するか、あらかじめ決めておく「個別避難計画」の作成が区市町村の努力義務とされた。
このような背景を踏まえ、東京海上レジリエンス、NEC、アビームコンサルティング1月14日、東京都が運営する「東京データプラットフォーム」のケーススタディ事業に採択され、「要配慮者の個別避難トータルサポートプロジェクト」を2024年8月から実施していたと発表。
同プロジェクトでは、風水害における要配慮者の個別避難を支援するため、官民の防災関連データやデジタルツールである「NEC避難行動支援サービス」を活用した取り組みを多摩市・江戸川区で検証する。1月21日、多摩市でNEC避難行動支援サービスを活用した実証が行われたので、本稿ではその模様を紹介する。
「要配慮者の個別避難トータルサポートプロジェクト」の概要
東京データプラットフォームとは、東京都がデジタルの力で東京のポテンシャルを引き出す「スマート東京」の実現に向けて、官民のさまざまなデータの利活用を促進し、新たなサービスの創出を後押しするために運営しているプラットフォームのこと。
そして東京データプラットフォームでは、データ利活用促進の一環として、官民さまざまな分野のデータの掛け合わせや、新たなデータ利活用のユースケースを創出する先駆的なプロジェクトを選定し、支援するケーススタディに取り組んでいる。
3社が取り組んでいる要配慮者の個別避難トータルサポートプロジェクトでは、「個別避難計画作成の高度化」「安否確認の高度化」「災害時の支援者サポート」「要支援者移動の連携スキーム検証」「個別避難計画作成から避難支援事業の全体見直し」「災害時における要配慮者の新たな避難先検証」を行っている。
「個別避難計画作成の高度化」「安否確認の高度化」「災害時の支援者サポート」「要支援者移動の連携スキーム検証」「個別避難計画作成から避難支援事業の全体見直し」の5つに関しては多摩市、「災害時における要配慮者の新たな避難先検証」に関しては江戸川区を実証フィールドとして取り組んでおり、平時(計画策定時)と災害時(避難)の両輪でのアプローチが特徴となっている。
今回、多摩市では、NEC避難行動支援サービスを活用した「安否確認の高度化」と「災害時の支援者サポート」の実証が行われた。
ロールプレイで避難支援の実証
今回の実証に活用されているNEC避難行動支援サービスは、自治体と地域コミュニティ(町内会など)をつなぎ、平時は個別避難計画をオンラインで作成し、災害時は支援者に計画情報を共有して、要支援者の避難支援をしやすくするサービス。
同サービス内に実装されている共助避難支援機能は、専用アプリのインストール不要で、Webブラウザにて、要支援者の安否確認や情報共有が可能という特徴を備えている。
この災害時に要支援者の安否を登録、その登録結果を自動で集約できる共助避難支援機能を用いて、支援者や自治体職員の皆さまの安否確認業務の負荷低減、支援が行き届いていない支援者への迅速なフォローにつながるかどうかを検証するのが、今回の実証の目的だ。
実証には多摩市で働くケアマネージャー12人が参加。2人組を組んで支援者役と要支援者役に分かれ、「台風が近付いてきた」という設定で状況付与カードの内容に従って電話をかけ、その安否結果を名簿に記載していくというロールプレイの体験を行った。
参加者からは「普段は紙ベースの名簿を活用しているが、非常時に必ず取り出せるとは限らないのでデータだと安心できる」「災害時に通信状況が安定しているかという不安もあるが、それをクリアできれば今よりも便利に活用できそう」といった声が上がっていた。
今後、東京海上レジリエンス、NEC、アビームコンサルティングの3社は、多摩市・江戸川区の協力のもと、官民の防災関連データを活用した要配慮者の個別避難を支援するための実証を行うことで、「逃げ遅れゼロ」実現に寄与していきたい考え。