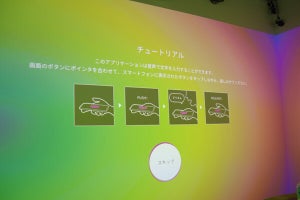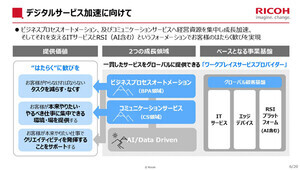リコーは2024年度(FY24)の新卒1年目社員を対象とするフォローアップ研修の一環として、「『"はたらく"に歓びを』Day Experience」と題したブランドワークショップを実施中(以下、FY24研修)だ。昨年から始まったこの試みでは、企業へのエンゲージメントの向上とリコーブランドの強化を狙う。
リコーの人事担当が主催する入社1年目社員を対象とした育成施策は、入社前に行われる「内定者学習会」、入社後の4月に行われる「新入社員研修」、1年目の冬頃に行われる「新入社員フォローアップ研修」に分けられる。本稿では、新入社員フォローアップ研修として実施された「『"はたらく"に歓びを』Day Experience」の様子を紹介したい。
リコーはなぜ社内向けにブランド研修を実施するのか?
リコーが目指す姿として掲げる「"はたらく"に歓びを」を体感するために、今回の研修には2024年4月に入社した147人の新入社員が参加した。
FY24研修の流れは以下の通り。まず、1年目社員は20人ほどの7グループに分かれ、グループごとに別日程で「創造力の発揮」をテーマとしたワークショップに取り組む。各グループの中でさらに4~5人のチームに分かれ、テーマに沿ったアイデア創出に挑戦。全日程が終了した時点で、各日程の中から選ばれた計7チームが全社公開のコンペに参加し、最終的に総合優勝チームを決める。優勝チームが考案したアイデアは、自部署や関連部署など限定的ではあるがPoCへと進む。場合によっては全社展開も検討されるという。
FY21まで、リコーブランドをテーマとした研修プログラムは存在しなかったそう。そのため、リコーブランドのコアとなる「"はたらく"に歓びを」を入社後に理解する機会を得ることが難しかった。こうした状況を解消すべく、コミュニケーション戦略センターブランド戦略室の稲田旬氏らが人事部門に働きかけ、翌年から研修の実施に至った。
ブランド研修で会社の使命や目指す姿を伝えることで、会社生活の早いうちからコアバリューを理解し、企業ブランドと日々の業務とのつながりを認識して働くモチベーションの向上を促す狙いがある。そのため、まずは会社組織への入口となる新入社員向けの研修から開始している。
FY22研修では75人の新入社員を対象にオンラインで座学タイプの講義を実施。翌年FY23に初めて、新入社員120人向けにブランドワークショップ「『"はたらく"に歓びを』Day Experience」が開催された。コロナ禍が落ち着いたタイミングと重なり、多くのメンバーが対面でワークショップに取り組んだ。連動施策として、社長と新入社員の対談や、社内報を用いた情報展開などが実施されたという。
稲田氏は「FY22の研修を見て、よくありがちで面白くない研修という印象を受けた。それよりも、参加者が楽しいと思えて、記憶に残り、長続きする研修を考え始めた」と振り返った。
2年目社員が企画した"改良版"ワークショップ
FY23研修のワークショップを体験した社員のうち、有志の3人がFY24のワークショップを企画する2年目社員という立場で参加した。稲田氏らブランド部門だけで企画を完結するのではなく、若手社員も巻き込んだ研修として企画がスタートした。
「企画する側がどれだけ面白いことを考えても、受け手側は聞きたいことだけを聞くし、頭に残したいものだけを残す。多くの企業が手を変え品を変えブランド研修に取り組んでいると思うが、企画者と参加者が分かれている限りギャップは埋められないと考え、FY23研修の参加者にも企画側になってもらった」(稲田氏)
FY24研修では、FY23と同じく「"はたらく"に歓びを」の理解を深め、自身の業務との関連を理解することを目的としながら、前年ワークショップを受けた2年目社員によるフィードバックを反映した。
FY23研修のテーマは「創造的にはたらくためのアイデアを考える」というもの。FY24は「チームの想像力の発揮を促進する社内向けの企画を考える」をテーマとし、より自分ごととして理解を深められるよう改良。
研修時間内にアイデアを考えて終わりだったFY23研修の内容に、FY24研修では会社への提案や実践を通じて「伝える」プロセスを追加。PoCを含めた社内実践、さらには新規事業化も見据え、社内制度をふんだんに使った社内巻き込み型のプロジェクトへと発展させた。
2年目社員が考案したFY24研修の目玉イベントが、全社向けに公開されるプレゼン大会「Yolo Pitch 2024(よろピッチ2024)」。これは各日程で選ばれた7チームが出場する、いわば決勝戦的な位置付けのイベントで、2025年3月中旬に開催が予定されている。選抜チームメンバーの上司らも当日は会場に駆けつけるという。
今回は企画側となった2年目社員の山内裕世氏は「イベントを全社に公開することで、先輩社員にも『"はたらく"に歓びを』をいま一度考える機会としてもらい、1年目社員に触発されてほしい」と、その狙いを語る。
ちなみに、「Yolo Pitch」の名前は、「"はたらく"に歓びを」、通称「はたよろ」の"よろ"の部分と、「You only live once(人生は一度きり)」の頭文字を取った略称に由来するという。
企画する山内氏ら有志の2年目社員も、FY24研修の実施に向けた検討は苦労したそうだ。構想の初期段階から全社を巻き込んだイベントとする方針は固まっていたのだが、具体的なスケジュールや予算、研修で活用できる社内制度など、多くの壁があったという。
山内氏は自身が参加したFY23のワークショップについて、「リコーが企業としてどのような思いで『"はたらく"に歓びを』を掲げ、どのように日々の業務を進めているのかを理解できた。自身の日々の業務の中でも、いかに『"はたらく"に歓びを』を実現できるのかを考えるきっかけになった」と振り返った。
2年目社員の思いは1年目社員に届いたのか?
稲田氏と山内氏の話を聞いた後、実際にFY24研修に参加した1年目社員の2人を取材した。回答してくれたのはデジタルサービス事業本部の出野雄大氏と安田優花氏。ワークショップ企画者の意図は1年目の社員にも届いたのだろうか。
ワークショップに参加した感想を教えてください
出野氏:まず率直に、面白い研修だと思いました。私が所属するのはシステムエンジニアの部署で、ものを作る立場です。上司からもよく「ものを作って売るだけでなく経験を売ろう」と言われます。ワークショップを通じて業務改善に取り組んだことで、「"はたらく"に歓びを」を軸とした視点から新規事業開発について考えることができました。
安田氏:私も、斬新な研修だなと思いました。参加する前は、座学研修で一方的に講義を聞くだけだと思っていたので、とても新しい雰囲気を感じました。就職活動や入社時の研修では「"はたらく"に歓びを」について考える機会がありましたが、入社から半年以上が経過し、日々の業務に追われて当社のバリューを忘れてしまいがちなタイミングで、改めて考える機会になりました。
今後もこのようなワークショップには参加したいですか
出野氏:全員が参加するワークショップは半日だけなのでとてもさみしいです。半年に一回などもっと継続的に、何か取り組む機会があれば嬉しいですね。
来年は企画する側になりたいですか。また、もし企画するならどんな内容にしますか
出野氏:もし企画する側になれたら、新入社員だけでなくさまざまな年次の人と合同で取り組む内容にしたいです。先輩社員も日々の業務の中で自身の作業に没頭する時間が増えていると思いますが、「『"はたらく"に歓びを』Day Experience」に参加して当社の目指す姿を振り返る機会にしてほしいです。
安田氏:今回のワークショップは、まずアイデアを出して発表するところまでで一区切りです。来年以降の企画を考えるとするならば、アイデアを出して終わりではなく、プロトタイプを作ってみるなど走り出すまでサポートしたいです。
また、7日程から1チームずつ、計7チームだけが「Yolo Pitch」に進むのではなく、例えば、全チームのアイデアをMicrosoft SharePointで社内に共有して投票してもらうなど、より全社を巻き込んだ企画にアップデートしたいです。
ワークショップで学んだことは自分の日々の業務に生かせそうですか
出野氏:上司からよく言われる「もの売りではなくこと売り」「経験を売ることを考える」という視点について、今回のワークショップの経験をそのまま生かせそうです。本題とはそれますが、今回の研修は配属先がばらばらな同期が久しぶりに集まる機会でもあったので、お互いに良い刺激になりました。
翌年以降も、研修を受けた新入社員が企画する側になるというこの取り組みは続くという。数年後にはリコー社内で研修企画者のコミュニティが拡大することとなる。年を経るごとに改良される同社の新卒研修に今後も注目したい。