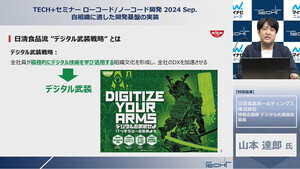UiPathはこのほど、AI×オートメーション活用の最前線を紹介するイベント「AIオートメーションフォーラム2024」を開催した。長らくRPAによる自動化を進めてきた同社だが、最近はRPAなどによるロボティックとAIによるエージェンティックによって実現される「エージェンティックオートメーション」を目指している。
「エージェンティックオートメーション」とはどのようなもので、どんなメリットをもたらすのか。同イベントの講演から、ひも解いてみたい。
ロボティックとエージェンティックの融合を目指す
UiPath カントリーマネージャーの南哲夫氏は、今回のイベントで展開したい内容として、「パートナーと加速」「エージェンティックオートメーション」「日本のユースケースを世界に」を挙げた。
「どのような形で、エージェンティックオートメーションを実現するかを説明する」と南氏。同社はこれまで多くの顧客にRPAを中心とした業務改革を支援してきたが、ロボットを中心としたオートメーションが主だったという。
同社は現在、ロボティックとエージェンティックによる自動化の未来を描いている。その中で、ロボティックを左脳、また、エージェンティックを右脳と見なしている。ロボティックは高い信頼性と効率を必要とする繰り返し作業に最適であり、一方、エージェンティックは高い適応性を必要とする臨機応変なタスクに適している。
南氏は「左脳をベースに右脳でロボットではできない意思決定を行う。左脳と右脳を融合することを目指す」と語った。
生成AIで広がるオートメーションの可能性
次に、アイ・ティ・アール プリンシパル・アナリスト 舘野真人氏が、「生成AIが拓くオートメーションの新たな可能性」というテーマの下、生成AIの進化によって導かれる自動化の未来像と、今後企業が注視すべき動向について解説した。
国内で進まない全社業務レベルの自動化
舘野氏は、同社が実施した「IT投資動向調査2020〜2025」を引き合いに出し、国内企業のオートメーションの取り組みの状況を紹介した。これによると、DX(デジタルトランスフォーメーション)のテーマのうち、「業務の自動化」に取り組んでいると回答した国内企業の割合は40%を超えるという。同氏は、「20%程度だった2020年から、コロナ禍を経て大きく伸びた」と説明した。
ただし、課題もあるという。従業員1,000人以上の企業に勤務し、RPAを導入済みのIT担当者を対象に実施した調査では、「全社業務レベル」での自動化にたどり着いている企業はわずか13%だったとのことだ。
「単一のタスクレベルの自動化が中心になっている。自動化の導入は簡単だが、拡大は難しい。今の課題は、最終的に顧客に価値を届けるところまで、どうやって拡大するか」(館野氏)
館野氏は、自動化の拡大展開を妨げる要因として、以下の4点を挙げた。
- 経営層・業務部門の理解不足
- 自動化すべきタスクを発見する仕組みの未整備
- ボット(ワークフロー)を開発・運用できる人材の不足
- 多数のボット(ワークフロー)の統制に対する不安
生成AIで変わるオートメーション
そして、館野氏は生成AIの登場により、自動化テクノロジーは「nice to have」から「must have」の存在へと変わりつつあると指摘した。さらに、「生成AIは自動化しないことによるリスクも生む」と同氏は述べた。
同社の調査では、業務自動化で「成果が出ている」とした企業では、生成AIの業務適用も進んでいることが明らかになっている。「業務の自動化と生成AIは親和性が高く、切っても切れない関係になると見ている」と、館野氏は説明した。
館野氏は生成AIの次なる活用ステップとして、自律的にタスクを実行する「AI(LLM)エージェント」への注目が高まっていることを紹介した。
現在は、プロンプトから生成AIに質問を投げかけると、LLMが事前学習データに基づく回答を生成するといった形での利用が多い。次のステップが、RAG(検索拡張生成)を活用して、外部の知識ソースを組み合わせてより適正な回答を生成するといったものだ。その次のステップで、AIエージェントが目標達成のために自律的にLLMを活用して回答を得つつ行動する。
館野氏は、ITRが考えるAIエージェントの意義として、以下を紹介した。
- LLMの推論能力を活用して複雑な問題を分解し、解決するための計画を作成できる
- 外部ツールを使用してさまざまなアクション(Web検索、API呼び出しコード実行など)を実行する
- 過去のやり取りや動作を記憶し、その内容を将来のアクションに役立てる
AIエージェント市場での覇権を握るべく、さまざまなベンダーがAIエージェントについて戦略を発表している。館野氏は、「来年以降、AIエージェントが大きなテーマになるが、エージェントについて情報が錯綜するのでは。AIのベンダーだけでなく、オラクル、Salesforce、ServiceNowなどのアプリベンダーも参入している。どうやって実装するかが議論になる」との見方を示した。
また、館野氏は「Agentic Process Automation」という考え方を示し、「エージェンティックAIはエキスパートのスキルを代替できる可能性がある」と述べた。とはいえ、エージェントベースの自動化を実業務に適用するうえでは、克服すべき課題も少なくないという。
リーダーに求められる生成AI時代のスキルとマインドセット
最後に、館野氏は生成AIに関して、リーダーが備えるべきスキルとマインドセットについて説明した。「一番変わるべきはリーダー。リーダーしか発揮できないスキルがある」(同氏)
まず、スキルとしては「技術の有望性を見極める」「最適なユースケースを見いだす」「プロジェクトの投資妥当性を判断する」の3点が求められる。
一方、マインドセットとしては、「“初心者”の心構えをもつ」「組織文化を当事者間で共有する」「オープンで協力的な風土を育む」の3点が求められる。
館野氏は、「オートメーションはどうやって拡大し、効果を上げるかに目を向ける必要がある。エージェントは今後トレンドになると考えられるため、オートメーション全体を考えた戦略が必要。リーダーには新しいスキルとマインドセットを手にしてもらいたい」と語り、講演を締めくくった。
エージェンティックオートメーションを実現する製品を提供
続いて、UiPath プロダクトマーケティング部部長 夏目健氏が、エージェンティックオートメーションを実現する同社の製品について説明を行った。
夏目氏は、「2023年にはゼロだったAIエージェントへの世界的な支出が、2024年には4億ドル近くに急増した。2028年までに組織内の意思決定の15%をエージェントが自律的に行う時代が訪れる」として、AIエージェントの時代が始まることを紹介した。
このトレンドに向けて、2025年に、以下の3点に取り組む必要があるという。夏目氏は「エージェントを活用しやすい環境を作ることも大事。エージェントが社内のデータを解釈しやすくしたり、エージェントを作るだけでなく、周辺環境も変えていったりする必要がある」と述べた。
- AIエージェントとエージェンティックオートメーションについて学ぶ
- エージェンティックオートメーションを活用したプロセスを少なくとも1つ開始する
- その一環として、先行企業の動向を注視するまたは自らその一員になる
AIエージェントが活躍する世界における、同社の製品戦略がエージェンティックオートメーションとなる。エージェンティックオートメーションへの第一歩となる製品としては、会話型エージェント「Autopilot for Everyone」、エージェント開発ツール「Agent Builder」、自動化ワークフローの自己修復エージェント「Healing Agent」が発表されている。
夏目氏は、「多くの業種でRPA×エージェントのユースケースが広がると考えている。UiPathはエージェンティックオートメーションに大きく踏み出している」と語っていた。