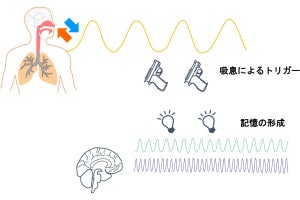北海道教育大学(北教大)、神戸大学、中京大学の3者は12月6日、中強度の20分の運動後に記憶学習をした後の記憶保持に対する影響を調査した結果、24時間後では運動条件と安静条件間に差が見られず、4週間後でも統計学的な差は認められなかったものの、6週間後と8週間後では、運動条件の正答数が安静条件よりも多いことがわかり、しかし11か月後には条件間での差は消失していることが確認されたと共同で発表した。
同成果は、北教大 岩見沢校 スポーツ教育課程の森田憲輝教授、神戸大 人間発達環境学研究科の石原暢准教授、中京大 教養教育研究院の紙上敬太准教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、豪州スポーツ医学協会が刊行するスポーツにおける科学と医学に関する全般を扱う学術誌「Journal of Science and Medicine in Sport」に掲載された。
学習内容や体験したことなどを記憶時点から数分から数十分、さらには数年以上の期間保持する脳機能のことを「長期記憶(エピソード記憶)」という。しかし長期記憶といえども時間と共に忘れていくため、1か月後にはおよそ20%しか残らないとされる。それに対し、運動後に学習すると長期記憶が向上することが知られており、これまでの研究では1回の運動で最長1週間ほど長期記憶の向上が確認されていた。ただし、その効果がどれほど持続するのかについては不明だったとする。そこで研究チームは今回、運動後の長期記憶向上に持続的な効果が示されれば、学校での学習や職場、そして日常生活において運動の効果的な利用を推奨できるのではないかと考え、どれほど持続するのかを調査したとする。
今回の研究には健康な大学生44名が参加し、実験には「クロスオーバー法を用いた被験者内比較対照実験」という研究デザインが用いられた。クロスオーバー法とは、実験条件の順番で生じうる影響を相殺するため、同じ被験者が複数の条件をランダムな順番で体験する方法のこと。一方の被験者内比較対照実験とは、同じ被験者に対して複数の条件を異なるタイミングで与え、条件間の違いによる変化を比較する実験方法だ。この両者を組み合わせることで、実験条件の順番による影響と個人差による影響をどちらも最小限に抑えることができるとしている。
同実験では、参加者によりランダムな順序で運動条件と座位安静条件が実施された。運動条件では、20分間の中強度サイクリング運動(最大予備心拍数の50%強度)が実施され、座位安静条件では実験室で20分間の座位安静(スマートフォンの操作や読書なども禁止)とされた。その後、15個の単語を声に出して読み上げ、その後覚えた単語を1分間でできるだけ多く書き出すテスト(単語思い出しテスト)を5セット実施。そして、24時間後、4週間後、6週間後、8週間後さらに11か月後に、2つの条件で学習した単語の思い出しテストが実施され、両条件で記憶した単語の正答数が比較された。
そして実験の結果、記憶学習の直後に思い出した単語の最大正答数は、条件間で差が無く(学習直後での最大正答数:運動条件12.9±1.9個、座位安静条件12.7±2.3個)ため、記憶学習の直後には運動の影響がないといえるという。その後の単語思い出しテストの正答数でも、24時間後では運動条件と安静条件間に差が見られなかったとのこと。4週間後では、運動条件の方がわずかに正答数が多かったものの、統計学的に有意な差は認められなかったとした。
それに対し、6週間後と8週間後時点での正答数は、6週間後では運動条件の方が1.5個多く(約10%増加)、8週間後では運動条件の方が1.2個多い(約8%増加)結果となり、学習前の運動が学習内容の長期的な定着(長期記憶)を強化することが示されたとする。ただし11か月後には、条件間での差は消失していたとしている。
-

単語思い出しテストの正答数の推移。運動条件(赤)と安静条件(青)の各時点での単語想起数(平均値)の時間経過が示されている(各時点での縦棒は95%信頼区間)。図中の「*」がついた時点が、運動条件と安静条件での正答数の統計学的な差が示されている(出所:中京大プレスリリースPDF)
今回の結果は、学習前の運動が長期記憶を強化し、その持続効果が少なくとも8週間後までは持続したことが明示されている。今回の研究により、運動による長期記憶向上効果はこれまで最長で1週間までしか示されていなかったが、より長期に及ぶことが明らかにされた。
今回の研究での実験対象は健康な大学生だったが、子供世代や社会人世代が学校や職場での学習効果を高める取り組みに応用できるよう、今後の研究の発展が期待されるという。また今後は、運動が長期記憶をどのように持続的に向上させるかのメカニズムを解明することで、ヒトの長期記憶の仕組みのさらなる理解につながる可能性もあり、多方面への発展が期待できるとしている。