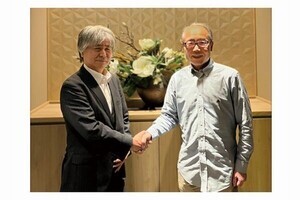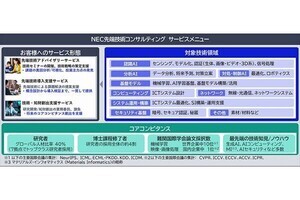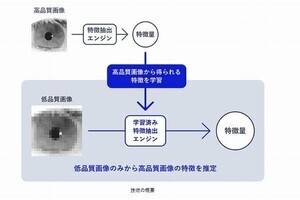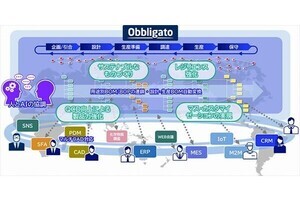NECは、「子育て支援の充実化」の社会課題と向き合い、男性育休の取得を当たり前とする社会の実現、およびそれを当たり前とする会社としてのカルチャーの醸成に向けて、経営戦略として「2025年度に男性育休取得率100%を目指す」ことを目標に掲げている。
本稿では、NECの男性育休取得率向上のための取り組みと、その一環として行われた東京都主催「育業」出前研修の一部始終を紹介する。
10月からスタートした「出産・育児」に関する新施策
「2025年度に男性育休取得率100%を目指す」というNECの経営戦略の背景には、若年層を中心に育休取得の意向が年々高まっていることや、I&D(インクルージョン&ダイバーシティ)の観点で、男性育休への取り組み状況が人材獲得競争力に直結する動きが強まっていることがある。
そこで同社は、「この領域で競合他社を上回りトップランナーとして認識され、人材獲得競争力で優位に立つためには、昨今一部の企業では実現されつつある男性育休などの取得率100%を早期に実現することが重要」と考えたという。
加えて。同社では「育休取得は組織と個人の成長機会にもなる」という点にも着目している。
メンバーの育休取得中にも、チームとして高い成果を上げていくためには、チーム全体で業務を標準化・効率化する工夫をし、一人ひとりがより高みを目指して、仕事の幅を広げていく必要がある。これにより、育休取得は当事者にとって育児経験を積むメリットになるだけではなく、チームとしてお互いに助け合い、高め合い、チーム力を上げるチャンスにもなると考えているという。
これらを背景として、同社は2024年10月から出産・育児に関する新施策を立ち上げた。具体的には、「事前(妊娠・出産前)」「妊娠」「出産」「育児」の4つのフェーズに分かれている従来の施策に、それぞれ新しい施策が追加される形となっている。
「事前(妊娠・出産前)」フェーズの新施策
「事前(妊娠・出産前)」のフェーズでは、従来は「育休ガイド(女性・男性・上司向け)の公開」「取得者インタビュー掲載」「セミナー実施」を行っていたの。そこに、「経営層からの発信」「東京都とのコラボセミナーの実施」「イントラの充実化」が加わった。
ポイントとしては、「社員とのコミュニケーション機会を増やす」「会社方針として、育休の取得を促進することのアピール」という2点が挙げられる。
「妊娠」フェーズの新施策
「妊娠」のフェーズでは、従来は、本人出産に関連する仕組みとして「妊娠通院休暇」を設けていたのに加え、「育休計画シート作成・提出の必須化」と「産前ペアレント・ファンドの支給」として子ども1人につき10万円が支給されることになった。
上司・本人がシートで整理しながら育休計画を相談することで、チームとしての支え方を模索できるようになるほか、産前にかかる費用を新たに一部サポートする。
「出産」フェーズの新施策
「出産」のフェーズでは、従来は、パートナー出産に関連する仕組みとして「産後パパ育休」「FF休暇(ファミリーフレンドリー休暇)」、本人出産に関連する仕組みとして「産前産後休暇」が用意されていた。これらに加え、パートナー出産に関連する仕組みである「配偶者出産休暇」として有給休暇10日の新設が行われた。
これに伴い、配偶者出産事由のFF休暇は廃止されている。
「育児」フェーズの新施策
「育児」のフェーズでは、従来は「育児休暇」と「産後ペアレント・ファンド」として子ども1人につき55万円を支給する制度を設定していた。これに加え、「1カ月以上の育休取得」と「育児両立シートの作成」を推奨することによって、一定期間以上の育休取得促進と育休復帰後の育児支援強化を目指している。
東京都主催の職場での「育業」支援に関する研修を実施
先般、NECでは男性育休取得率向上のための取り組みとして、東京都が主催する職場での「育業」支援に関する研修を実施。講師にはフリーアナウンサーの武田真一氏と厚生労働省 東京労働局 指導課 統括雇用環境改善・均等推進指導官の横山ちひろ氏を招へいした。
今回の研修のテーマとなっている「育業」は、東京都が推進する新たな育児支援の愛称で、「休暇」のイメージが根強い「育児休業」を「将来を担う子供達を育てる業務」として捉え直す試み。
育児は「未来を担う子どもを育てる大切で尊い仕事」であり、「育児休業」はみんなで協力するべき、という理念のもとに成り立っている。
研修では、この「育児休業」の現状や課題、なぜいま育業が重要なのか、という内容が語られたほか、「『育業』と聞いて思い浮かべること」「半年間の育業がもたらすメリットを考える」といったテーマで自身の考えを深めるグループワークも実施された。
同研修には管理職を含めた社員の約200人以上が参加しており、参加した社員からは「管理職として部下に育業を勧める心構えができた」「改めてチームとしての在り方を考える良い機会になった」といった声が上がっていた。