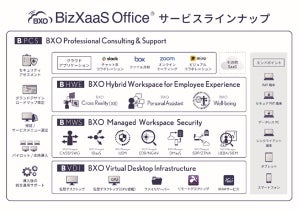ビジュアルワークスペース「Miro」を手掛ける米Miroの日本法人であるミロ・ジャパン(以下、ミロ)は10月31日、オンラインホワイトボードサービスについて、生成AIを搭載した「イノベーションワークスペース」プラットフォームとして提供開始することを発表し、説明会を開いた。アイデアのブレインストーミングからロードマップ作成、プロトタイピング、実行までの幅広い工程をAIで支援する。
イノベーション創出のための機能を強化
ミロは今年7月に、組織のイノベーション・ライフサイクル全体の管理を支援する新たなキャンバス「インテリジェント・キャンバス」のコンセプトを発表。Miro AIによって強化されたインテリジェント・キャンバスでは、生成AIによりドキュメント、ユーザーストーリー、ダイアグラムなどの自動生成が可能となった。また、プロダクトリーダー、アジャイルコーチ、プロダクトマーケターなど専門家の知識を備えるAIエージェントも利用可能となった。
今回はこれらの機能を強化したほか、プロトタイピングやAdobe Expressとの連携など、新たな機能を追加している。ミロの代表執行役社長である向山泰貴氏は「従来のオンラインホワイトボードからイノベーションワークスペースとなったことで、国や時間帯を超えてアイデアをまとめて仕事ができるようになる。あらゆる業務にAIを組んでいるので、ユーザーのみなさんが一緒に仕事をする場所を提供していけたら」とコメントしていた。
イノベーションワークスペースの新機能をデモで紹介
説明会では、今回追加された新機能の一部がデモで紹介された。デモはFlexbankという架空の企業がモバイルアプリを作成するという想定で進められた。まずは現状の課題とその解決策についてブレインストーミングで意見を出し合うシーンから始まる。
ブレインストーミング
ブレインストーミングでは従来のMiroと同様、ホワイトボードに自由に付箋で意見を出し合う。新機能としては、投票可能なスタンプ機能「インタラクティブスタンプ」を追加。これは、スタンプの内容に賛同する人がクリックすると票が集まる機能で、一定数以上の票が集まるとスタンプが変化する。
アイスブレイクの際などに有効な新機能が「スピナー」だ。スピナーはいわゆるルーレット機能であり、話を始めるときのテーマや、誰から話し始めるのかをランダムで選出する。これらの機能により、発言しやすい雰囲気を作り出し、アイデア創出やコラボレーションを促す。
アイデアの集約とドキュメント化
ブレインストーミングで発散したアイデアの数々。これらを集約して次のステップに進むためには、文書化する必要がある。これをサポートするのが今回アップデートされた「ドキュメント」機能。複数の付箋を選択すれば、ワンクリックでその内容を生成AIが文書化する。これにより、業務の効率化が見込める。
さらに、一度文書化した後であっても、追加で出た意見の付箋をドラッグ&ドロップで移動するだけで、その内容がドキュメントにも反映される。
会議の終盤にブレインストーミングの結果がすぐに文書化されることで、会議の達成感やチームの一体感が生まれるのだという。ドキュメントはその場で全員がアクセス可能なため、参加者の同意を得ながら必要に応じて修正やコメント追加も可能。
作成したドキュメントには、イラストやダイアグラムも挿入できる。新機能である「同期コピー」により、別のボード上で作成されたダイアグラムを挿入した場合には、元のボード上でダイアグラムが修正されるとその内容が反映される。
テーブルで情報を一元管理
アイデア出しと製品概要の策定が終了したら、次は具体的な開発工程に移る。ここでは新機能「テーブル」が役立つ。テーブルはキャンバス上のデータを表形式に集計できる。テーブルはGoogle スプレッドシートやJiraなどの外部ツールとも連携可能。プロジェクトに関わる全てのタスクを集約し、一元管理できる。また、各タスクは表形式だけでなく、タイムライン上のデータとしても閲覧・編集可能だ。
製品概要をブラッシュアップ
製品概要については、ステークホルダーからのフィードバックが得られることもある。これらのアイデアは追加の付箋に記載し、ドキュメントをブラッシュアップできる。また、ディスカッションの結果は、プロダクトリーダーの視点を持つ生成AI機能である「AIパートナー」によって具体的なアイデアに落とし込める。
プロトタイピング
製品概要が固まったら、いよいよプロトタイプを作成する。従来は数日から数週間かかるこの工程だが、Miroは生成AIによって数秒へと短縮している。このプロトタイプにはボタンや入力フォーム、画面遷移などをライブラリから任意に追加できるため、細部は後から人の手で調整可能だ。
開発工程のプランニング
開発ワークフローの策定にもMiroは有効だという。これもJiraなどの外部ツールと連携しており、作業負荷を確認しながら適切な作業者を割り当てることができる。また、カウンターウィジェットを備え、作業上限の見積もりと現状の差分を確認しながら余力を可視化する。
開発チームが使用している既存のツールとも連携しながら、開発工程の可視化と一元管理を可能としている。
マーケティングコンテンツの管理・編集
広告バナーやロゴ、イメージ写真など、アプリのマーケティングに必要なコンテンツもMiro上で管理可能。付箋を使ったコメントやコンテンツのレビューは、これまで通りの使い方と同様とも言える。しかしこれまでは、外部の編集ツールで作成した画像をMiroに貼り付け、レビューやコメントに従ってまた外部のツールで編集するなど、ツールをまたいで作業する必要があった。
今回新たに、Adobe Expressと連携したことで、Miro内で画像を直接編集できるようになった。Adobe Expressのレイヤー構造もそのままMiroに反映されるため、テキストの修正やロゴの挿入といった作業をスムーズに行える。
リリース後の分析
アプリをリリースした後のデータ分析も、Miroで対応できるという。Microsoft Power BIと連携しており、アプリのダウンロード数やアクティブユーザー数などをダッシュボードとして閲覧可能だ。
もちろん、ここでもMiroの従来からの機能であるオンラインホワイトボードを活用できる。データが可視化されているダッシュボードのすぐ近くで、付箋やスタンプを使った議論を始めることができる。