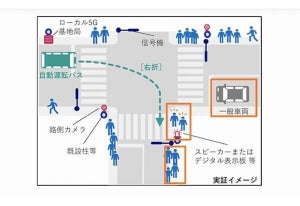NECは10月24日、報道関係者向けにエンタープライズ事業における市場動向や最新トピックスを紹介する「NEC Media meetup」を開催した。本稿では、製造業における生成AIの取り組みを紹介する。
本稿では、NEC Media meetup内で「製造業における生成AIの活用事例の紹介」というタイトルで、NEC スマートインダストリー統括部 プロフェッショナルの高野智史氏が説明した「クライアントゼロのによる活用事例」を紹介する。
減少する製造業の就業者
最初に高野氏は「製造業を取り巻く環境」というテーマで、労働人口減少や技術継承に関する業界の課題を語った。
「労働人口の減少により製造業の就業者数も減少しています。総務省の労働力調査では、2002年時点で製造業の就業者は1222万人だったが、2022年には996万人にまで減少していることが分かりました」(高野氏)
加えて同調査の中では、2040年には924万人にまで製造業の就業者が減少することが予想されており、著しい人材不足が危惧されているという。
また労働人口不足に伴い、ベテラン社員への負荷が高まることも課題の1つだ。ベテラン社員への負荷が高まることで、若手や中途採用者への技術継承に時間をかけられないことが問題視されている。
厚生労働省の調査では、2022年の段階で「技術継承に問題がある事業者」として59.9%が挙げられており、全産業の41.2%と比べてもかなり多い割合となってしまっている。
その中で、NECは「デジタル化の進展により、労働力不足への備えとしてナレッジは蓄積されつつあるが有効活用されていない」という課題を感じており、「経験が浅くノウハウが少ない若手でもLLM(大規模言語モデル)を活用することで問題を早期解決する」という方向性で、この課題を解決しようとしているという。
自社をゼロ番目のクライアントに
NECでは、自社をゼロ番目のクライアントとして最先端のテクノロジーを実践する「クライアントゼロ」という考え方のもと、まず同社が先んじて課題に取り組み、そこで得た経験をリファレンスとして顧客や社会に提供する取り組みを行っている。
今回の説明会では、クライアントゼロの活用事例として「現場トラブルへの対処方法レコメンド」「工程FMEA(Failure Mode and Effects Analysis:故障モード影響分析)の自動生成」という2つを紹介した。
現場トラブルへの対処方法レコメンド
現場トラブルへの対処方法レコメンドは、LLMを活用して製造現場での設備や品質不良、生産効率低下などの問題解決を支援するソリューション。2024年3月にNECプラットフォームズにて技術的実現性の検証が実施された。
これまでは「欲しい情報が探せない」「原因特定に時間がかかる」「熟練工に依存したトラブル解決」といった課題があり、若手はトラブル解決のために熟練工に聞いたり、日報から探したり……というさまざまな段階をふむ必要があり、品質低下や生産性低下・ロス増大を招いてしまっていたという。
この状況に対して同ソリューションを導入することで、熟練工のノウハウをデジタル化することに成功し、ナレッジの継承や生産効率維持・ロス削減に成功。「対話形式で誰でも簡単に情報を検索」「日報登録でますますナレッジが賢くなる」「匠が現場にいなくても早期に問題解決」といった成果を生んだ。
検証結果としては、RAG(検索拡張生成)を活用することで、AIハルシネーションを抑制しつつ、現場で過去に起きた事象や原因などの質問内容に合った情報を高い精度で引き出せることを確認した。
また、検索結果を向上させるための工夫として「プロンプトとデータソースで利用する用語の統一」「データの階層構造化」「ナレッジの要約、不要な文章の削除」「データの事前集計」といったデータの標準化・構造化が必要であることがわかったという。
工程FMEAの自動生成
2つ目の事例で紹介された工程FMEAでは、製造プロセスにおける潜在的な不具合や問題点を事前に特定し、製品やプロセスに与える影響を評価することができる。この分析を行うことで、問題が発生する前に対策を講じることができ、品質の向上やコスト削減、安全性の確保につながるという。
NECでは、LLMを活用してFMEAを自動で生成。製品品質の向上を支援するソリューションについて、2024年6~9月にかけて、業務適用効果および技術的実現性の検証を実施した。
FMEAを良くするために必要である、数多くのリスク項目を洗い出すことについて、今回の仕組みを用いることで実現できた一方で、AIの回答精度は100%ではなく、最終的に人により不要なものを省くチェックやレビューは必要であるということが分かったという。
同ソリューションを導入することで、「欲しい情報が探せない」「担当者によるスキルのバラつき」「製品の品質問題の発生」といった課題を解決することができ、誰でも簡単にFMEAを自動で作成できるようになるという。