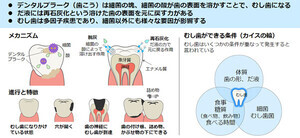富士通と帝京大学 冲永総合研究所(以下、帝大冲永総研)は10月18日、XR(AR:拡張現実やVR:仮想現実などの総称)や空間コンピューティング、生成AIなどのデジタルテクノロジーを活用して、体内の状態を深く理解することで生活習慣の改善に向けた意識向上やヘルスケアリテラシー向上をサポートするUX(User Experience)プラットフォームの共同研究を開始することを発表した。
研究背景
両者は2022年10月より、インフォームドコンセントにおいてXRや空間コンピューティング、生成AIを用いて、医師と患者のコミュニケーションギャップの解消を目指す研究を行ってきた。その研究成果として、患者の生体データから生成したバーチャル体内モデルや、AIメディカルサポーターのアバターなどの技術を開発。今回はこれらの技術を活用して、生活習慣改善の意識向上やヘルスケアリテラシー向上をサポートするUXプラットフォームの共同研究を本格的に開始する。
この研究では、健康診断の受診結果から生活習慣の改善が必要とされた受診者が、保健師との面談時または面談後にXRと空間コンピューティングを用いて、体内の様子をバーチャルで空間上に再現し、健康課題が潜んでいる箇所に対する理解を深める。これにより、生活改善に向けた健康意識と行動変容にどのような影響を与えるかを検証する。
また、生成AIを搭載したAIヘルスケアサポーターのアバターを作成し、生活習慣の改善に向けたフォローアップを行うことにより、受診者のヘルスケアリテラシーの向上などに与える影響も検証する。
研究の内容
研究ではまず、健康診断により生活習慣の改善が必要と診断された受診者や保健師などにインタビューを行い、生活習慣の行動変容を起こせない本質的な阻害要因を特定する。この阻害要因に対し、生活習慣の改善を必要とする受診者が行動変容を起こすためのアイデアを抽出する。
これと同時に、XRや空間コンピューティングを活用して内臓や骨格などをバーチャルに空間上で再現可能なプロトタイプや、生成AIを搭載し生活習慣病の予防について学習したAIヘルスケアサポーターのプロトタイプを作成。
健康診断の受診結果から健康課題を発見された受診者が3のプロトタイプを用いて、自身の体内の様子を空間上に表示しながら保健師と面談を実施することで、受診者の健康意識の向上や行動変容にどのような影響を与えるかを確認する。