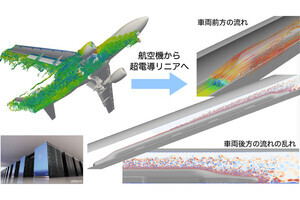最近、日本の経済産業省(経産省)や欧米諸国が参加するオンライン会議が開催され、中国による鉄鋼の過剰生産問題が議論された。
それによると、今日の世界における鉄鋼消費量が20億トン程度の中、2023年の過剰分は5億5100トンに達し、2026年までにそれは6億3000万トンあたりにまで増えるとの懸念が示されたという。欧米や日本は世界における鉄鋼の過剰生産が今後も続くと警戒し、欧米などは中国産鉄鋼に対する関税を引き上げるなどの防衛策を講じているが、第三国経由などが増えており、過剰生産によって国際市場が不安定化し、公正な貿易取引に悪影響を及ぼすことが懸念されている。
また、欧米諸国は中国政府が中国の電気自動車(EV)メーカーを補助金で支援し、安価なEVを大量生産させ、それを海外向けに輸出させていることについても懸念も強めており、中国製EVに対する関税引き上げなどの対抗策を講じている。
米バイデン政権も2024年春、中国製EVに対する関税をそれまでの25%から4倍の100%に引き上げることを発表したが、米国が輸入するEVの中で中国シェアは僅か2%であり、中国への強硬姿勢を国民向けにアピールするという政治的思惑が見え隠れする。また、カナダも今夏に中国製EVに対する関税を100%に引き上げることを発表するなど、中国による過剰生産に対する欧米の警戒が広がっている。
では、なぜ中国はEVや鉄鋼などを過剰生産を続け、欧米諸国はその中国の過剰生産を警戒するのか。資本主義や市場経済の原則に照らせば、中国がモノを大量に生産し、それを海外へ輸出することには何ら問題はないかも知れない。しかし、経済の武器化が進む今日の世界情勢においては、双方にそれぞれの狙いがあると考えられる。
世界経済で影響力を強めたいという思惑を持つ中国は、EVや鉄鋼など先端テクノロジーや戦略物資の分野で中国のシェアを拡大させることで、自らに有利な国際環境を構築しようという政治的狙いがある。
東南アジアのラオスやカンボジア、ミャンマー、南アジアのパキスタンなどは中国から多額の資金援助を受け、インフラ整備や都市開発などを推し進め、多くの中国企業が進出しているが、そういった国々は政治的に中国の従属国家のような状況に陥っている。中国に反発するような姿勢に徹すれば、資金援助を縮小、停止されるリスクが生じることになるが、EVや鉄鋼など先端テクノロジーや戦略物資の過剰生産を強化する中国の狙いはそこにあろう。中国は今後、世界各国が何を必要とするか、どのような分野、製品に需要が拡大するかなどを先読みし、それによって必要品の生産を強化し、自らに有利な国際環境を構築しようとしている。
そして、欧米はそれに対する警戒を強めている。仮に先端テクノロジーや戦略物資の分野で欧米が中国に遅れを取れば、欧米の対中国依存が深まる可能性があり、それは経済的、貿易的に欧米の脆弱性を露呈することになる。中国製EVが第三国経由も含めて欧米諸国の国内に流入し、それによって国内のEVメーカーが衰退することになれば、欧米は自然に中国依存を深めることになる。そうなれば、台湾問題など中国との間で生じている緊張が激化することが起こった際に、依存度の高い国は中国による経済的威圧に遭うリスクが高まることとなる。半導体を含めた先端テクノロジーや戦略物資の過剰生産をめぐる双方の対立は、今後さらに先鋭化していくことだろう。