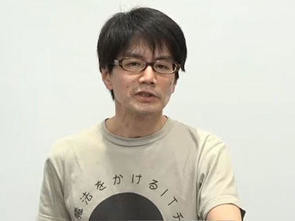先日、パシフィコ横浜で「Google Cloud Next Tokyo '24」を開催した、グーグル・クラウド・ジャパン。初日のキーノートに登壇した、星野リゾート 代表 星野佳路氏の講演を紹介する。
運営特化に舵を切った星野リゾート
同社では、Gemini for Google Workspaceを早期に導入している。星野氏はスキー愛好家としても知られており、登壇するなり「過去1年で76日滑りました。目標は年間80日、可能であれば100日スキーをする年をいずれは迎えたいと考えています」と述べた。
星野リゾートは1990年代前半にリゾート事業、観光事業、温泉・旅館・ホテルなどの運営に特化した。同氏は「当時は運営に特化する企業が日本に浸透していない中で、いち早く運営特化戦略に舵を切ったことは私たちの成長にとって大事な意思決定となりました。私の経営人生の中でも最も重要ものの1つでした」と振り返る。
現在、同社は「星野リゾート」を筆頭にサブブランド6つに加え、個別ブランドを運営しており、運営施設数は国内外含めて72にのぼる。
星野氏が経験した観光産業における3つの大きな変化
星野氏は「運営施設数を伸ばすプロセスの中で幸運なことに、観光産業における大きな変化を3つ経験しました。この変化に私たちは必死に食らいつきました」と述懐した。同氏が話す、3つの観光産業に関する大きな変化とは何か。
1つ目は「団体旅行周遊型」から「個人旅行滞在型」への変化だ。星野氏の父、つまり先代社長の時代はそこまで大きな変化はなかったが、バブル経済の崩壊や個人旅行市場の成長など、さまざまな要因に対応してきたことが古くからある観光産業の中でシェアを伸ばすことができたという。
2つ目はインバウンド。2023年における日本の旅行市場規模は28兆1000億円で、うちインバウンドの市場は5兆3000億円となっている。同氏は「まだまだ小さい市場ではありますが、今後は人口減少に伴い国内旅行市場は自ずとシュリンクしていくため、政府はインバウンドを成長させようとしています。そこにわれわれは真っ先に手を挙げて、成長させてきたという経緯があります」と話す。
3つ目は宿泊施設をはじめとした情報収集や予約、顧客の意思決定がオンライン上で完結しているということ。星野氏は1991年に星野リゾートの経営を継ぎ、1997年には楽天市場が開設、1990年代後半にさまざまなモノがオンライン上に溢れるようなった。
同氏は「私の経営キャリアと、ITテクノロジーが旅行産業を変革していった時代が完全にリンクしています。すごくラッキーだと感じているのは、最初から現在までの段階をすべてフォローすることができていることであり、ITは重要だという認識を持ち続けることができ、星野リゾートの成長につながりました。その結果として現在、同社における予約獲得の70%が旅行エージェントを介さないダイレクトブッキングとなっており、大きな武器になっています」と力を込めていた。
星野リゾートが「Gemini for Google Workspace」を導入した決め手
このような状況の中で、なぜ星野リゾートはGemini for Google Workspaceを導入したのだろうか。
星野氏は「生成AIに社員が慣れてもらうことを徹底していく、という意思決定を行いました。生成AIは今後の観光産業を大きく変化させるものになり得るため、いち早くフォローすることが次の成長、ひいては競争力の維持につながります」と、導入の経緯を語った。。そして、同社が生成AIを積極的に導入する理由について星野氏は4つの観点から説明した。
まずは「言語対応」だ。現在、同社のWebサイトは日本語、英語、中国語(簡体字、繋体字)、韓国語で展開している。しかし、上記以外の言語対応は容易ない。一方、Geminiでは69言語への対応が可能になってことから、同氏は「当社のWebサイトを69言語で紹介できることになります」と見解を語った。
続いては「正確性」。この点は同社だけに限らず、あまねく企業に共通するが、業務は正確性を伴わなければならないことから、従業員は相当な時間を費やしている。こうした作業に生成AIを活用すればポジティブな結果が得られるとの見立てだ。
次は「固定観念からの脱却」となる。星野氏は「大きな意思決定をする際は仮説を検証するために市場調査を行います。ただ、日々の意思決定をするときは市場調査を行う時間と予算はないため、自分の感覚を信じるしかない側面があり、ボトルネックになりかねません」との認識を示す。
その一例として同氏は社内での議論を紹介した。当初、星野リゾートの想定では60代以上の人はインターネットを使わず、スマートフォンで予約していないのではないかと推測。しかし、実際に蓋を開けてみると、予約している60代以上の人たちの25%超は同社のWebサイト上で旅行情報を把握し、20代はInstagramやYouTuberなどから情報を得ていることから、若年層より多い結果になったという。
同氏は「Webサイトをちゃんと閲覧してくれているのは実は60代以上の方々でした。これは、われわれが感覚的に話してることとは、まったく異なることが実際のマーケットの中で起こっている証です。そのため、固定観念からいかに脱却できるかということが、現場における日々の意思決定には非常に重要であり、われわれが生成AIに期待しているものの1つです」と説明した。
最後は「創造性の刺激」だ。同社では日々のブレインストーミング(ブレスト)を行っているが、生成AIを活用すれば人数を集める必要がなく、さまざまな角度から回答があるため効率化につながるとのことだ。
生成AIをパートナーにして、異なる分野にリソースを割く
講演の終盤に星野氏は「生成AIをパートナーに持つことは非常に重要。これらの4つは私たちの仕事をある意味、失くしてしまうという側面も確かにあるかもしれません。しかし、その分の時間とエネルギー、コストを異なる分野にかけられるになります」と強調する。
同氏が言及する異なる分野とは、生成AIによる多言語対応が可能になり国語力が重視されることが想定されることから「国語の表現力」、個人のオリジナリティや戦略性を打ち出すために「発想をひねる」、理想的な選択を行うための「選択肢を外す」、そして「個性の表現」を挙げている。
こうした4つのポイントに触れつつ星野氏は「これらはマネジメントの仕事です。その前に紹介した生成AIを積極的に導入する4つの観点は社員が担当していました。今後は社員1人1人が経営の仕事ができるようになります。社員1人1人が経営の仕事をしてくれれば、私はもっとスキーに行けるようになる。これが生成AIをパートナーにする最も重要な理由になります」と、冗談を交えながら講演を締めくくった。