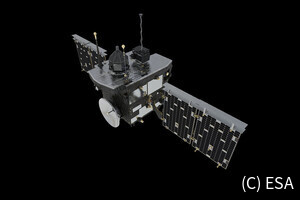横浜国立大学(横国大)と宇宙航空研究開発機構(JAXA)の両者は6月28日、真空中でイオン液体を含浸した「多孔質エミッタ」からイオンを放出し宇宙推進機として推力を発生させる物理メカニズムに関して、マルチスケールな解析を不要とする簡易な理論モデルを構築し、放出イオン電流の実験結果を精度良く説明することに成功したと共同で発表した。
同成果は、横国大の髙木公貴大学院生(JAXA 宇宙科学研究所(ISAS)所属/科学技術振興機構(JST) 創発プロジェクト・リサーチ・アシスタント)、JAXA 宇宙飛翔工学研究系の月崎竜童准教授、同・西山和孝教授、東京大学の山下裕介博士(現・米 スタンフォード大学)、同・鷹尾祥典准教授(JST創発研究者)らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学協会が刊行する応用物理学に関する全般を扱う学術誌「Journal of Applied Physics」に掲載された。
これまで人工衛星といえば、現在の区分でいう大型衛星が一般的で、トン単位の質量も普通だ(たとえば7月1日に軌道投入に成功した「だいち4号」は約3トン)。しかし近年はそうした大型衛星だけでなく、100kg以下の超小型衛星が注目されている(中には、質量1kg台の超軽量衛星もある)。そうした超小型衛星の代表としては、10cm×10cm×10cmの立方体を最小ユニット(「1Uサイズ」と呼ばれる)として規格化した「キューブサット」があり、1つの大学や民間企業でもそれほど予算や期間をかけずに開発できることもあって、その打ち上げ数は大きく増加中だ。
超小型衛星は、一度の打ち上げで多数を同時に軌道に投入しやすかったり、大型衛星の打上げの際の空いたスペースを利用する相乗りを利用できたり、国際宇宙ステーションに一度運んでそこから軌道に投入する方法なども取れたりすることから、大型衛星とは異なり「コンステレーション」(全地球規模で多数の衛星を配置すること)も構築しやすく、それによる通信インフラの整備が急速に進められるなど、新たな産業基盤として構築されつつある。
しかし超小型衛星のその軽量コンパクトさは、メリットであるのと同時に、デメリットでもある。そのサイズに適した宇宙推進器が存在しないのだ。従来用いられてきた化学推進機は高圧ガスの制約が大きく、イオンエンジンなどの電気推進機は電力が不足してしまうなど、良い推進機の選択肢が現状ほとんどない。そこで研究チームは今回、超小型衛星でも自由に宇宙空間を動力航行できることを目的とした新技術の確立を目指したという。
今回の研究では、高圧ガスを用いることなくイオン液体を貯蔵し、プラズマを生成することなく、推進剤となるイオン液体から直接イオンを放出して推力を発生させることで、大幅な効率改善を図る技術の確立が目標とされた。イオン液体を浸透させた多孔質エミッタの表面に高電界を加えると、イオンを効率よく放出させることが可能だ。そのため、世界中で宇宙推進機としての利用を目指した研究開発が進められているが、多孔質表面に存在するイオン液体界面からイオンが引き出される物理現象はマルチスケールにわたって複雑なため、どれだけのイオンが放出されるのかを予測するには時間を要する数値シミュレーションが必要であることが課題だったという。
今回は、まず約1mmの微小な突起形状を持つ多孔質エミッタの形状を正確に計測し、その形状から数値計算で表面電界が算出された。一方、真空装置内でイオン液体を含浸させたエミッタ表面に高電界を与えることで、放出されるイオンを電流値として直接計測がなされた。これらの電界と電流密度の関係を理論モデルで定式化し、マイクロスケールとナノスケールの異なる多孔質を用いて多孔質抵抗を変化させることで、イオンの輸送の違いがイオン放出に与える影響を調べることができたとする。
-

理論モデルの概要。多孔質エミッタの内部から表面に至るまでの流れがイオン放出を決定していることを表している。(出典は掲載論文より:licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND) license.)(出所:ISAS Webサイト)
そして、エミッタ内部のイオンの流れがイオン放出を決定していることを示唆する先行研究から着想を得て、多孔質構造によって抑制されるイオンの輸送をオーム則に基づく簡易なモデルで表し、しきい値電界を超える領域からイオンが放出されるとする定式化が行われた。その結果、複雑な表面の状態を考慮しない簡易なモデル化にも関わらず、モデルから予測される電流値は実験値と非常に良い一致を示すことに成功したとのことだ。
研究チームによると、今回構築された理論モデルを用いることで、計算コストを劇的に抑え、スラスタの形状設計に対する放出イオンを予測することが可能になるという。さらに、今後の推進機開発に今回の理論モデルを活用することで、高性能化へ向けた設計の効率化が期待されるとした。また今回のスラスタが実用化されれば、超小型衛星を使ったコンステレーションや深宇宙探査、フォーメーションフライト(編隊飛行)の実現が期待されるとしている。