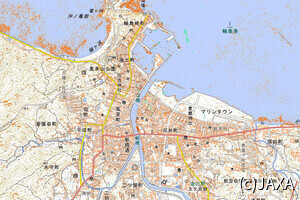関西大学(関大)とリコーは、関大などが開発した超小型人工衛星「DENDEN-01」にリコーの宇宙用ペロブスカイト太陽電池を搭載し、軌道上での実証実験を行うことを発表した。
関大などが開発した1Uサイズ(10cm×10cm×10cm)の超小型人工衛星であるDENDEN-01は、6月4日に宇宙航空研究開発機構(JAXA)への引き渡しが完了され、今秋に国際宇宙ステーション(ISS)に向けて打ち上げたのち、ISSからの放出実証実験を開始する予定。その中で今回搭載されたペロブスカイト太陽電池の評価もおよそ半年にわたって行われる見込みだ。
従来の衛星で用いられてきた太陽電池は、重量が大きく打ち上げにコストを要する上、宇宙線(宇宙空間を飛び交う放射線)による劣化や、充分に太陽光が当たらないと発電ができないなどといった課題を抱えていた。
そうした中、地上における活用でも注目が集まるペロブスカイト太陽電池について、低照度での高い発電量や宇宙線への高い耐久性、また将来的にはフレキシブル化や軽量化が可能であるという特徴などから、宇宙空間での活用に対する期待が高まっているとする。
リコーは2017年から、ペロブスカイト太陽電池の宇宙利用を目的に、JAXA「宇宙探査イノベーションハブプロジェクト」に参加。宇宙向けの太陽電池開発でノウハウを培ってきたことから、今回のDENDEN-01への搭載に至ったという。なお搭載されたペロブスカイト太陽電池は、同衛星用にモジュールを設計し取り付けやすい設計になっているとのことだ。
リコーによると、今回の宇宙実証では、衛星の傾きと照度に対しての発電量をモニタリングするとともに、宇宙空間での耐久性を評価するといい、取得したデータは関大・JAXA・リコーの3者で検証予定だとする。同社は、実用的なペロブスカイト太陽電池の直列モジュールを用いた宇宙実証実験を通じて、早期の市場投入に向け開発を加速させるとしている。