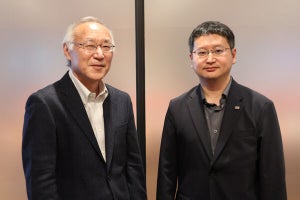消費者委員会は6月6日、食品表示部会を開催、主に機能性表示食品の食品表示基準改正の方向性について議論した。消費者庁食品表示課保健表示室長の今川正紀氏は「(今回の制度改正は)機能性表示食品の信頼性確保が目的」などと話した。
冒頭、消費者庁の今川室長が、5月31日の関係閣僚会合の内容について説明した。
<今後の対応案説明>
機能性表示食品の制度改正について、①健康被害の情報提供の義務化 ②機能性表示食品制度の信頼性を高めるための措置 ③情報提供のDX化、消費者教育の強化 ④国と地方の役割分担――が今後の対応案としてまとめられたと話した。
今川氏は、食品表示基準の一部改正の方向性についても説明した。
これまでに届け出の実績がないなどで、届け出資料の確認に特に時間を要すると消費者庁長官が認めるものについては、届け出資料の提出期限を、原則販売日の60営業日前から、特例として、販売日の120営業日前とすることを食品表示基準に明記することなどを盛り込んだと説明。届け出後、機能性表示をすることが適切でないことが判明した場合、機能性表示食品としての要件を満たさなくなり、当該表示ができなくなることを食品表示基準上明確化するとした。
機能性表示を行うサプリメントについては、GMPに基づく製造管理を食品表示基準における届け出者の遵守事項とし、関連する情報を届け出させることとするとした。
<4つの遵守事項想定>
届け出後、遵守事項を遵守しない場合、機能性表示食品としての表示ができなくなることを食品表示基準上明確化すると説明した。
届け出後の遵守事項としては、①サプリメント最終製品の製造についてGMPの遵守 ②健康被害の情報の収集と提供の遵守 ③届け出後の新たな科学的知見により機能性表示の根拠が最新のものになっているかどうかの情報収集 ④届け出後の遵守の自己チェックーーの4点を想定しているという。
複数の委員からは、「GMP遵守が、『最終製品の製造について』とあるが、原材料について必要ないのか」といった質問が、消費者庁に対して投げかけられた。これに対して今川室長は、「GMPの要件のかけ方については、今後検討していく。食品表示法の規定では、届け出者が対象となるため、最終製品の製造者の責任になると考えている。原材料の話もあったら、機能性表示として表示をする事業者に対して、GMPの遵守をかけていく方針だ」としていた。
中田華寿子委員は、「要件化をしていくと、いわゆる普通の健康食品が増えてしまい、消費者のリスクが高まってしまうのでは」と質問。今川室長は、「改正は、機能性表示食品の信頼性の確保が目的だと思っているので、制度をそのまま維持したいと考えている。一方で、健康被害情報の報告やGMPの義務など、やってもらう必要が出てくる。消費者庁の立ち入りなどで指導し、徐々に改善していってもらえれば」と話していた。