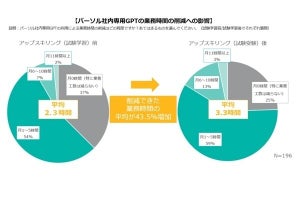生成AI(人工知能)を業務に活用しようとする動きが、業界・業種問わず広がっている。例えば、セブンイレブンでは、生成AIを活用し商品企画の期間を10分の1に短縮し、パナソニックでは、電気シェーバーのモーター設計に生成AIを活用している。
筆者も普段の業務で生成AIを使っており、企画立案のアドバイスをもらったり、原稿の誤字脱字などをチェックしてもらったりしている。明確な数字は算出できないが、生成AIにより業務効率化ができていると感じている。
企業向け研修などを手掛けるリブ・コンサルティングが4月に公表した調査結果によると、生成AIを日常利用(週に数回程度以上)している会社員の割合は4割を超えた。また、2割以上が「生成AIの成果を実感している」と回答した。
一方で、生成AIの活用にはリスクも伴う。情報漏えいや著作権侵害、プライバシー侵害などさまざまなリスクがある。また、生成AIは学習したインターネット上の大量のデータから、確率的に確からしい文章を生成しているため、事実と異なる文章を生成してしまう「ハルシネーション」といった課題も存在する。
企業はどのように生成AIと向き合い、どのように活用していくべきなのか。本稿では、生成AIを積極的に活用している組織の事例を紹介する。
社員2200人が生成AIを本格利用‐三菱HCキャピタル
リース事業などを手掛ける三菱HCキャピタルは、生成AIを積極的に活用している企業の1社だ。日立製作所の生成AIの専門組織「Generative AIセンター」と協力し、マイクロソフトの「Azure OpenAI Service」を活用した生成AIを構築、3月より全社員約2200人に展開している。三菱HCキャピタルは2024年度を「業務効率化の年」と位置付け、営業事務や審査業務、ヘルプデスク業務などにおける自動化や効率化を目指している。
同プロジェクトが始まったのは2023年10月。なぜ生成AIの本格活用を目指したのか。三菱HCキャピタル IT部 開発グループ 課長代理の西尾勇紀氏は「汎用業務に生成AIを活用してもらい生産性向上につなげたいと考えた。いち早く一般ユーザに生成AIに触れてもらえる環境を構築し、生成AIの活用アイデアを全社レベルで考えられる土壌を整えたかった」と、プロジェクトが動き出したきっかけを語る。
企業のなかで生成AIを普及させるためには、利用環境の整備だけでなく、生成AIを適用した業務別のシステムの作り込みなど、より多くの人が利用できるベースづくりが重要であると考えた同社は、中長期的なロードマップや利用ガイドラインなどを作成。同社の社内規定や法的要件などを踏まえた利用ガイドラインは日立が持つノウハウをもとに作成したという。
また、2024年1月以降、必要最小限の構成で標準的な機能の試行環境を構築し、社内の特定ユーザーでその機能の試行評価も実施。そこで得られたフィードバックを生かし、全社での利用開始に踏み切った。西尾氏は「試行評価では、生成AIの活用によって当社の情報が外部に漏れないか、万が一漏れてしまった場合に原因を突き止めることが可能なのかということを確認した」と話す。
具体的な活用例としては、全業務共通の文章要約やドキュメントのアウトラインの作成補助、外国語の翻訳のほか、各業務領域におけるヘルプデスク対応、営業・審査部門の与信関連業務支援などの個別業務に生成AIの利用を狙う。
三菱HCキャピタルは2025年度を「生成AIによって新事業を創出する年」としており、社内情報を含む知識データベースや業務特化型のサービス構築と本番稼働を目指している。今後は日立との協働をより強化し、対象となるユースケースの業務データを取り込み、ナレッジを強化した知識データベースを構築していく。将来的には、API連携によって社外サービスの情報も含めたデータ取得を可能とする業務間連携の強化も目指すとのことだ。
「生成AIの環境があっても、社員が使えないと意味がない。そのため、効果的なプロンプト(AIへの指示文)や、利用上の注意点などを社内向けの説明会を通じて周知している。現場からは『この業務に生成AIが使えるかもしれない』といった声が多く届いており、1週間あたりで約6時間削減できた事例もある。会社全体で生成AIの利用を深化させていきたい」(西尾氏)
医師や看護師が生成AIを活用、年間540時間削減へ
医療業界においても生成AIが活躍できる領域は小さくない。石川県七尾市能登半島にある恵寿総合病院では、2023年12月より医師や看護師が生成AIを活用し業務時間の削減を実現している。
医療ベンチャーのユビーが提供する診察支援サービス「ユビーメディカルナビ」の生成AI機能を活用し、医師による退院時サマリーの作成業務や、看護師による退院時の看護要約作成業務などを効率化した。退院時サマリー作成業務は約15分から5分と最大で3分の1にまで短縮できたという。
平均すると5分の短縮が見込まれることから、全病棟で年間約6500人の患者が退院、転出する同病院では、この効率化により年間で540時間の医師の作業時間削減を実現できることになる。
恵寿総合病院 理事長補佐の神野正隆氏は、「今年の4月に医師の働き方改革が始まったが、単に時間を短縮するのでは医療の質が落ちてしまう。時間あたりにやらねばならぬ仕事量が増えてしまい、かえって『働きづらい改革』になってしまう可能性もある。医師を含めた全ての職種がそれぞれ本来業務により専念できるようになるためには、生成AIといったテクノロジーの活用は欠かせない」と生成AIの活用に踏み切った背景を語る。
退院サマリーとは、入院患者の病歴や、入院時の身体所見、検査所見、入院中に受けた医療内容についてまとめた記録のこと。退院後の外来診療時などに活用され、主治医以外の患者に関わるすべての医療スタッフが、入院中の治療、診断情報を的確に把握するために重要な記録だ。一般的に、退院後の外来診察までの平均的な日数である「退院後2週間以内」に作成する必要があるという。
神野氏は「退院サマリーの作成を面倒くさがる医師は少なくない。また内容にも偏りが見られ、しっかり詳細を書く人や、数行だけしか書かない人がいる」と退院サマリーに関する課題をこう説明し、「カルテの情報をもとに生成AIがたたき台を作ることで、医師がストレスを感じることなく効率的にサマリーを作ることができる」と生成AIの効果を述べた。生成AIの導入によって、医師は生成AIが作成した情報に問題がないか確認し、必要に応じて修正を加えるだけでよくなった。
医師だけでなく、看護師の業務効率も向上している。次の受け入れ先での継続的な看護を目的に、看護師が患者の看護の経過、退院後のケアについてまとめる退院時看護要約では、最大1時間掛かっていた作業時間を15分に短縮できたケースも確認されたとのこと。
また、テキストだけでなくAIによる音声認識といった機能も活用しており、主に会議議事録の作成や、医療従事者間の情報連携時のサマリ作成の効率も高めている。
恵寿総合病院今後もテクノロジーを活用した業務効率化と医療のさらなる質向上の両立を目指す。「当院は年始に被災したが、新しい取り組みの手を緩めることなく、今後も積極的なチャレンジを続けていく」(神野氏)