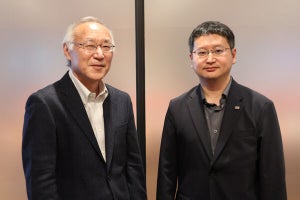1~4日間の短期間で数千万円から1億円以上の売り上げを作り出すマーケティング支援のWacker(ワッカー)。売り上げ直結型の支援は実績が豊富にあり、直近では新日本製薬と行った販促企画において、4日間で「4万個超」「売上高8500万円超え」の成果をあげた。成果をあげるための秘訣はどこにあるのか。「当社には勝ちパターンがある」と言う鹿田将斗CEOに聞いた。
<シナリオなしの企画>
当社がなぜ成果を出せているのか。それは、当社が実装する販促企画に「人格」を持たせている点にある。
「人格」をかみ砕いて説明する。例えば、企業が主となって紹介する商品などは、良いところだけにフォーカスする。これでは人の感情が上下することはないだろう。われわれは、この「感情」という部分を販促企画に落とし込む。これが、人格を持たせるという意味である。
販促企画の主となるのは「交渉型企画」というもの。この企画自体は、当社が先駆けだが、韓国では、すでに流行していた。
企画には大半が概要やシナリオが存在する。だが、当社には一切台本がない。これが大きなミソだ。台本やシナリオがないとできない企業が多いだろうが、当社としては台本なしの受け入れが難しい場合、支援はできないとはっきり伝えている。
良いところだけ紹介するのは、誰にでもできる。こうしたPRは世にごまんとあふれている。さらに、デジタルに対する免疫や見識があるユーザーには、これはPRだ、広告だとすぐに判断されてしまう。
昨今は、TikTokやYouTubeでも企画や台本をもとに作られたきれいな動画が増えている。だからこそ、予測できないリアリティーのある動画に価値が生まれる。
ユーザーがこうしたリアルなコンテンツに引き込まれ、結果的に再生回数が飛躍的に伸びる「バズり」が生まれる。当社が支援した交渉動画は300~400万回の再生数を誇っている。
各企業の方々が思っている以上にユーザー側のデジタルに対する見識は相当高い。こうした状況を踏まえれば、いかにもPRみたいなことをやっても意味がない。人格を持たせるために「汚い」「見せたくない」などの感情の部分にフォーカスすることに意味がある。
<熱量が視聴者に>
交渉企画に登場するのは、企業と当社が厳選したインフルエンサーだ。交渉を受ける企業も大変だが、インフルエンサーも苦労する。
インフルエンサーは企画を通じてファンのために頑張らないといけないという思いがある。この思いの熱量は視聴者にも伝わる。
▲多数の韓国スキンケアメーカーとインフルエンサー「2人目のエガチャン」を用いた施策では、2万セットが即日で完売し、売上高は約2.2億円を突破した
両者の熱量が歯車となって回り始めるとドラマのような形になる。これが売り上げという数字にも結び付く。
一方、販売する商品やブランドに対する企業の思いは強い。ただ、思いとは関係なく、企業である以上、販売数を伸ばさないといけない。結局、数字のために商品を売るロジックになる。
売っていくためには消費者を理解しなければならない。結局、ユーザー寄りの思考にならないとセールスと一緒に商品やブランドは育たない。
子どもを育てるように開発・育成してきた商品ブランドをユーザー寄りにするのは、開発担当者にとって大きな決断だろう。しかし、英断できたところは成果を出せている。一歩を踏み出す勇気も必要だ。
当社が一定の成果を出せるようになったのは、最初に仕掛けを行った韓国コスメブランド「メディヒール」がきっかけ。当時、メディヒール社からはオンラインの売り上げを伸ばしたいという要望があった。
熟考した結果、目を付けたのは韓国で売っていて日本では未発売の商品。未発売品が日本に来る話題を少しずつ膨らませ、日本ではどこで買えるのかとユーザーの期待値を上げていった。買える場所がないという「フラストレーション」に近いものを作り、その反動を生かした。未発売品はメディヒールの自社ECサイトで先行販売する流れを作った。
この結果、3日間で売上高は1億円を突破し、オンラインの売上比率は当初1%台だったが、約17%に引き上がった。
<OBM領域に進出>
これらの施策と成果が今の当社の勝ちパターンの土台だ。
今後も、引き続き成果にコミットすることにこだわるが、いろいろな事業展開もできるようになってきた。その中でも、製造からマーケティングまでをトータルで支援する「OBM」の領域に進出する。
化粧品メーカーやインフルエンサーとともに、ブランド開発やマーケティング展開、オフラインとオンラインでのプライベートブランド(PB)商品の開発などを手掛けていく。
ただ、インフルエンサー寄りの思考であることは変わらない。インフルエンサーは本気で取り組んでいる。本気という熱量とファンを大事にする姿勢を考慮すれば、消費者に近いインフルエンサー寄りの支援や施策を軸に展開していくことが重要だろう。