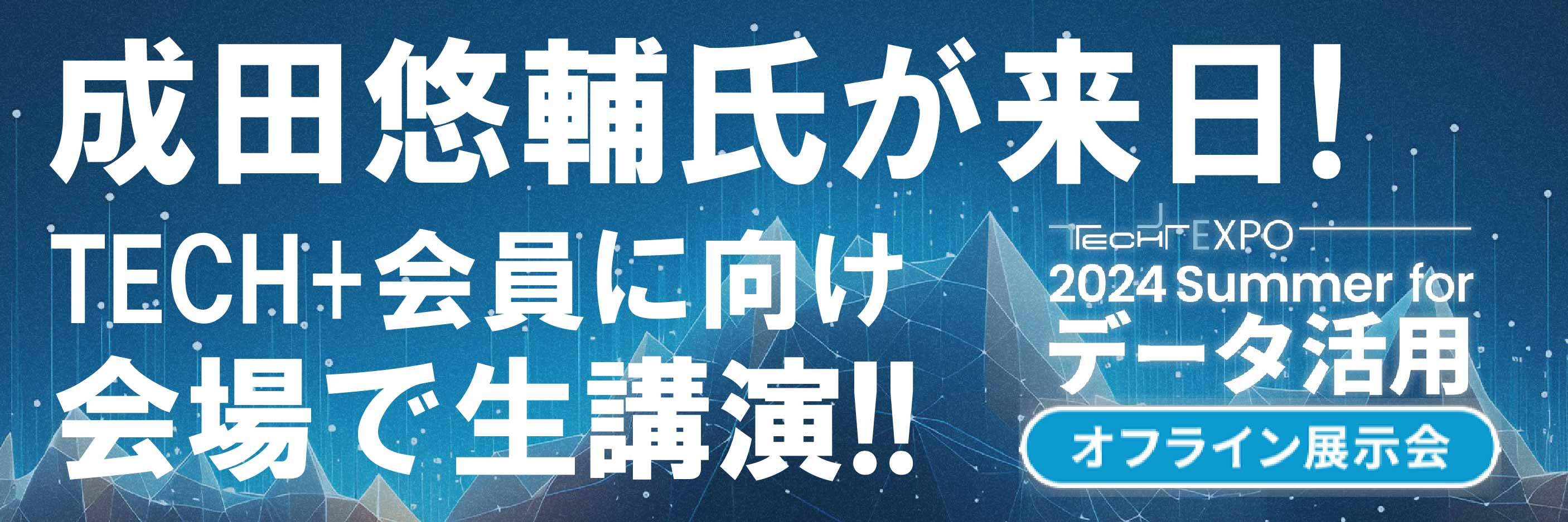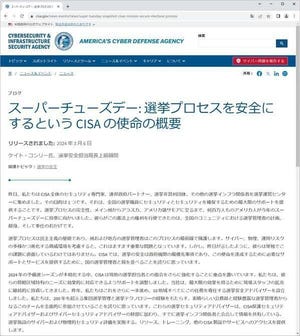分断・分裂が進む中で
世界中で分断・分裂が進む─。ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルとイスラム軍事組織『ハマス』との闘いをはじめ、各地で戦争や紛争が続く。
世界1の経済力、軍事力を誇る米国も〝アメリカ・ファースト〟を掲げるトランプ前大統領を筆頭に、自国のことで頭が一杯で、「他国のことなんか……」という様相。
それどころか、国内の格差も拡大するばかりで、自らの身を守るのに精一杯という感じ。
この格差問題にどう対処していけばいいのか?
「(世界中で)貧しい人の不満というのが溜まっている。これはもう社会保障しかないのだけれども、その社会保障をやるだけの力がどこにもないわけですよ」と語るのは、三菱総合研究所理事長の小宮山宏さん(東京大学元総長)。
スウェーデンなど北欧は、比較的格差の少ない社会を築きあげているという評価。社会民主主義的な体制づくりということで、所得のうち70%近くを税金として払い、格差の少ない社会体制にしているということである。
「リターンがあって、比較的格差が小さくて、という国をつくったわけですが、彼らが行動し始めたのは、10年位前。そこに1%の移民が入ってきて、新たな問題が生まれてきた」と小宮山さん。
以前は、国籍に関係なく、スウェーデンに居る人にはすべて同じ社会保障を与えるという形だったが、そうした考えにも微妙な変化が生まれているということ。移民にどう対応していくか? 国、あるいは国籍とは何か? という新たなテーマである。
格差問題にどう対処?
今の米国では、移民に厳しい目が向けられるが、元々は移民を受け容れ、移民の労働で国が支えられてきたという歴史である。
「移民否定なんてあり得ないけれども、もう束で入られたら、それを賄う能力が今のアメリカにはないわけですよ」と小宮山さん。
米国は移民問題、日本は東京一極集中ということで、形こそ違え、格差問題を抱えている。
人口減の中で、東京だけに人が集まり、地方が衰退し、〝消滅可能性都市〟も増えてきている。
アジアはアジアで、中国や韓国のように、出生率の低下に悩むなど、その国ならではの課題を抱える。
世界中が危機や課題を抱えている感じだが、明るい道筋を描くことはできないのか?
こうした質問に、「日本の課題ということで言えば、僕はあると思っています」と小宮山さん。
日本の課題解決力
「日本の未来をプラチナ社会で切りひらきたい」というのが小宮山さんの発想。
「再生エネルギーと、都市鉱山、それと毎年のバイオマスの成長。これを資源として、スポーツや文化の領域も同時に栄えるといった国づくりです」
小宮山さんはプラチナ社会の全体観をこう述べ、「いま地方の衰退という問題の本質は、第一次産業の衰退ということですよ」と強調。
農水産業の生産額は、約10兆円。GDP(国内総生産)の約550兆円から見ると、2%以下という水準。この現状をどう克服するか?
「(食料品を含めて)日本は資源を輸入しているわけですよ」と小宮山さんは次のように指摘する。
「いまエネルギーだけでも輸入額は30兆円以上。再生可能エネルギー、都市鉱山、バイオマスの成長を図るという産業構造にしていけば、海外に払うお金が国内に落ちることになる。それは大体地方に落ちますから、地方が元気になる」
10兆円の農水産業が50兆円の第一次産業に変わっていく─という小宮山さんの見立てである。
中長期ビジョンをしっかり立て国民の英知を発揮して、元気を取り戻そうということ。人口減、少子化・高齢化と嘆いているだけでは、何も変わらない。国民を勇気づけ、元気づける小宮山さんのプラチナ社会構想である。
竹内敏晃さんの〝体験〟
企業人の発想力、開発力、そして努力と根気に勇気づけられることがある。
電波の送受信に欠かせない水晶デバイス領域で、世界でその存在感を示すのが日本電波工業。同社は1948年(昭和23年)の創立。現会長・竹内敏晃さん(1943年=昭和18年4月生まれ)の父・正道さんが創業した会社。
戦前から、水晶振動子は国の重要戦略物資で、各国が開発にシノギを削ってきた。
「うちの親父はその頃、明電舎に勤めていて、技術開発に携わっていました」と竹内さん。
当時の明電舎社長は重宗雄三氏。重宗氏は戦後、政界に進出し、参議院議長を務めるなど、日本の進路づくりで活躍した人物。
「重宗さんに、水晶振動子の製造をやれと命じられて、製造ラインを一応つくりあげたと」
同社の水晶振動子は、零戦の無線機にも付けられていた。
戦争末期、父・正道氏は岩国(山口県)の製造拠点に居て、1945年(昭和20年)の8月6日、つまり原爆が投下された日の早朝、広島に汽車で出張することになっていた。
「その日は月曜日でね。親父の眼鏡をわたしが踏んでしまってね。その眼鏡のツルを直している間に、汽車が出てしまって、親父は広島に行けなかったんです」
該当列車が広島駅に着くのが、原爆炸裂の時刻と同じであった。もし、その列車に父・正道さんが乗り合わせていたら、その後の一家の運命も変わっていたと思う。
「もし、わたしが眼鏡を踏まなくて、父が広島に行っていたら、弟は生まれなかった」と竹内さん。
人は、天に生かされ、その中で精一杯努力して生き抜くしかない。そういう事を考えさせられる竹内さんの〝眼鏡談〟である。
和佐見勝さんの人材育成論
小売業に特化した3PL(物流一括請負)でロジスティクス業界をリードするAZ―COM丸和ホールディングス社長の和佐見勝さん(1945年=昭和20年5月生まれ)。
創業は1970年(昭和45年)。トラック1台から出発し、今では連結で1万7千人の社員を抱えるロジスティクス企業に育て上げた。低温食品物流などに強みを持ち、『桃太郎便』で知られている。
人手不足の中、物流業界はドライバーの残業時間が年960時間に縮減するよう法制化された。
こうした状況で、和佐見さんは、「この産業に魅力を感じてもらえるようにしていく」と語り、人材育成を最重要課題に掲げる。
埼玉県松伏町に3万5000坪(11万6000平方メートル)という広大な用地を取得し、ここに一大物流拠点と共に、人材育成センターもつくる計画。
「BCP(事業継続計画)を念頭に、流通業や食品会社はもちろんのこと、政府や東京都をはじめ各自治体とも連携しながら、BCPを追求していく」と和佐見さんは語る。「人の可能性を掘り起こしていく」という和佐見さんの心意気だ。