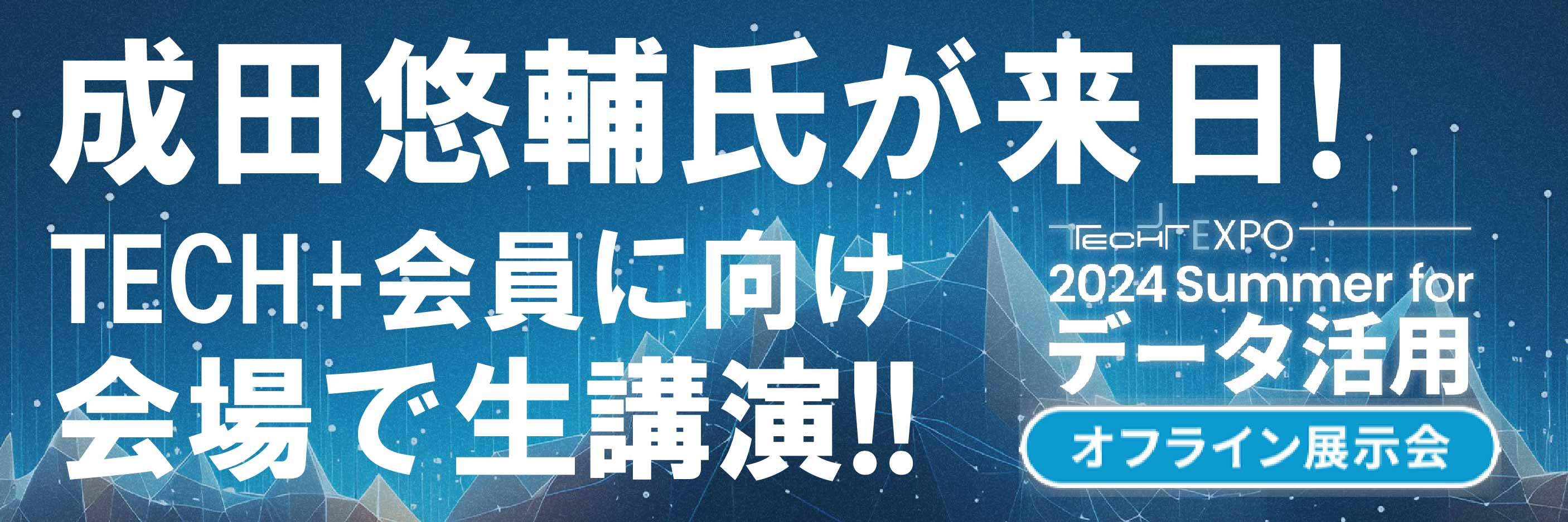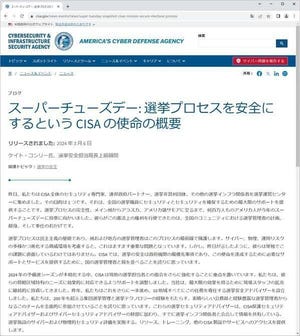2024年は日本の中長期的なエネルギー政策「エネルギー基本計画(以下、エネ基)」の見直し議論が本格化する時期にあたる。
エネ基の改定は3年に1度。21年10月に閣議決定されたエネ基では、太陽光や風力など再エネ電源を倍増し、主力電源化へ「最優先の原則で取り組む」としたが、大きく前進したとは言い難い。2030年度までの目標は絵に描いた餅となっている。
今回改定の大きなポイントは、原発の再稼働と再エネの拡大に向けて、具体的な策が出て来るか否かである。
再エネは、計画対比で遅れが目立つ風力や地熱を、如何に拡大できるかが問わる。順調に見える太陽光も、大規模発電で採算が見込める平地などの適地では、すでに設置が進んでいて、ここからペースを維持していくには、住宅への太陽光パネルの設置が必要になる。
日本はコストの面から言えば、海外に比べて高いことはある程度止むを得ない面がある。ただ、将来の予見可能性が低い状況は是正すべきである。
企業は将来のビジネス環境の見通しが立てば、その中で最適解を導き出すことができる。しかし、予見可能性が低い状態では、身動きが取れず、リスクを回避するため消極的になってしまう。とりわけ日本企業は、そうでなくてもリスク・テイクに消極的だ。少なくても、国は企業の消極姿勢を加速させないように振舞う必要がある。
企業にとって、DXとGXの実現は必須である。実現には、電力が欠かせない。産業面では、すでに生成AIなどデジタル技術革新が目覚ましく、デジタル関連の市場が急拡大している。
企業は供給構造の制約から使う電力を自由に選べない面がある。仮に、国内で製品を製造する際に、石炭や石油など火力発電が占める割合が高く、環境負荷の大きな電力を多く使わざるを得ないとすれば、脱炭素化に向かう世界の中で、その企業のブランド価値は下がり、金融市場からの評価も望ましくないものとなるだろう。
一方で、企業は立地を選択することはできる。各国は産業政策を強化し、世界から企業誘致を積極化している。
ここで心配なのは、日本企業が強くなったとしても、国内の立地が選択されなければ、日本に雇用や税金は落ちて来ない。日本企業と国の稼ぎは違う。エネルギー政策の如何によっては、この乖離がどんどん大きくなるだろう。
日本はアジアと近く、製造業のラインナップが揃っていることなど、有利な点を世界にアピールしていくはずだ。このままでは、エネルギーが足を引っ張ってしまう。政治が混迷しているからと言って「エネルギーを動かすことは難しい」という言葉では済まされない。30年ぶりのチャンスを活かすためにも、予見性があるエネ基を作ることが必要だ。