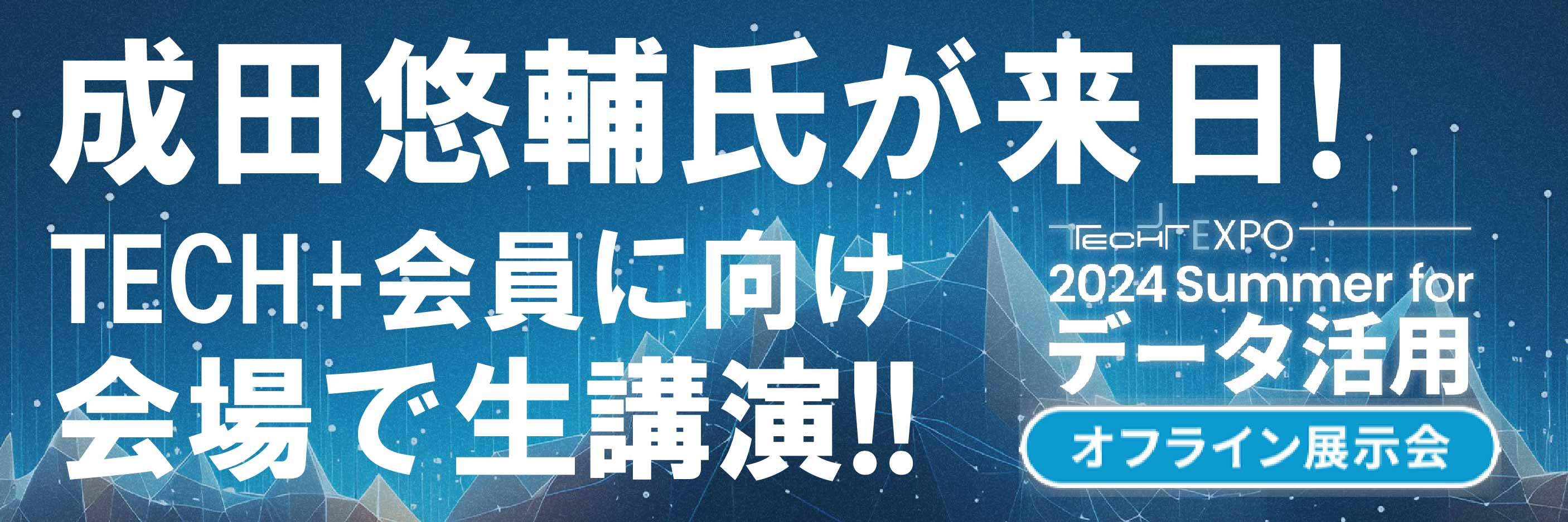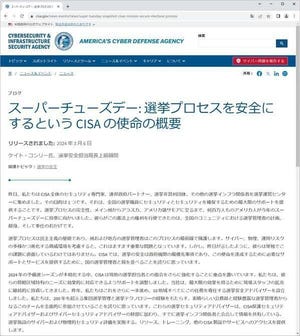「金利が付く時代」を地方銀行はどう生きていこうとしているのか─。地銀最大手・横浜銀行を中核とするコンコルディア・フィナンシャルグループ社長の片岡達也氏は今、「ソリューション・カンパニー」への転換を進めている。単に融資をするのではなく、成長を考える企業、あるいは経営改善が必要な企業など、違う悩みを抱える先にソリューションをあわせて提案する存在を目指している。その戦略の中身とは─。
日銀の政策変更をどう見ているか?
「大きな転換期に来ている。特に2023年度後半から、物価、賃金、消費、企業業績などパラダイムシフトの動きが起きている」と話すのは、コンコルディア・フィナンシャルグループ社長(横浜銀行頭取)の片岡達也氏。
年始からの日本を取り巻く経済環境を見ると、日経平均株価が1989年12月の3万8915円を超える4万円台の新高値を付け、大企業のみならず中小企業にも賃上げの動きが本格化している。コロナ禍の影響も小さくなる中、「景気全体としては明るい兆しが出てきている。全国的にも、神奈川県内を見ても、人の流れがコロナ前に戻ってきている」(片岡氏)
ただ、リスクもある。国内でいえば24年年始に発生した能登半島地震からの復興は道半ばで、その後も各地で大規模な地震が相次ぐ。世界を見てもロシア・ウクライナ戦争は継続し、中東の紛争が広がりを見せるなど、地政学リスクが収まる気配はない。中国経済の先行き不透明感も消えない。
そんな中、日本銀行は24年3月19日の金融政策決定会合でマイナス金利の解除、YCC(イールドカーブ・コントロール=長短金利操作)の撤廃などの政策変更を決め、日本に再び「金利が付く時代」が訪れた。
他の銀行と同様、グループの横浜銀行と神奈川銀行は4月1日から、それまで年0.001%だった普通預金金利を年0.02%に引き上げている。マイナス金利で苦しんだ銀行にとっては、預金に力が戻り、個人にとっては多少ではあるが金利の恩恵が及ぶことになる。
「銀行業界、我々にとってイールドカーブがしっかりできてくることはプラスに働く。金利動向によっては債券の評価損も見込まれるが短期的な話。中長期的にはイールドカーブが正常化し、資金収益にもプラス」
ただ、時間軸はまだ見えないが今後、新規の借り入れや借り換えをする個人にとっては、支払い利息負担が増す形になる。実際、一部のネット銀行では住宅ローンの基準となる短期プライムレート(短プラ)を引き上げるところも出てきている。「マイナス金利解除は、個々のお客様ごとに違った影響を与えることになるだけに、お客様に寄り添いながら仕事をしていくことが大事」と片岡氏。
これは個人だけでなく企業も同様。コロナ禍の中で実行された実質無利子・無担保の「ゼロゼロ融資」の返済が始まっている。経営が厳しい企業は、それでも返済に苦しんでいる中で、ここに利息がつくとさらに状況は厳しくなる。
「企業によって負担感が違うので、どういう影響があるのかを見ていくことが重要。場合によっては経営改善支援や既存の借り入れの見直し、金利上昇局面になった際のヘッジなど、様々な『ソリューション』を提供していく」
本部から現場にノウハウが移転
その意味で、地域に根ざした銀行である地方銀行の役割が問われる局面。「神奈川、東京のお客様が成長しなければ、我々の持続性も担保できなくなる」
「ソリューション」はコンコルディアFGにとって重要キーワード。同社は長期的に目指す姿として「地域に根ざし、ともに歩む存在として選ばれるソリューション・カンパニー」を掲げて、「ソリューション・カンパニーへの転換」を打ち出している。
個人に対しては、例えば日本がインフレに向かう中で、「新NISA」のスタートなどもあり資産形成の重要性が高まっている。ここにソリューションをいかに提供するかが問われる。
企業の悩みは様々だが、例えば今、東京証券取引所の要請もあり、上場企業でPBR(株価純資産倍率)1倍割れの企業はこの改善に乗り出している。ここに対応する資本政策を含めたアドバイスも重要な仕事。
また、前述のように中小企業は今後、金利負担が重荷になる可能性がある。仮に金利が1%上がった場合、1%以上の収益を稼がなければならなくなるから。こうなるとコンコルディアFGの仕事は財務面のアドバイスにとどまらなくなる。
「『金利のある世界』では成長支援が今後ますます必要になってくる。成長を支援することで我々が金利をいただくことができるようになる」と片岡氏。単に、「世の中の金利が上がっているから」というのではなく、顧客に付加価値を認めてもらうことが大事だということ。「そこで勝敗が決まってくる。まだ不十分なところもあるが、ソリューションをベースとしてやっていく」(片岡氏)。
これまでソリューション・カンパニーへの転換に向けて取り組んできた中で、徐々に変化を感じられることがあるという。以前は本部中心で、しかも経験豊富なキャリア採用の人材を中心とした専門チームで取り組んでいた。一方、営業店は案件を取り次ぐといった限定的な仕事が主だった。
それが今は、専門チームが培った知見、ノウハウが営業店に伝播し、本部と連携しながらではあるが、営業店が中心となって案件のクロージングまで行えるようになってきた。
片岡氏自身、横浜銀行頭取、コンコルディアFG社長に就いて以降、地元財界、顧客企業のトップなどと会った際に「横浜銀行は、いろいろな相談に乗ってくれるようになったね」、「こんな提案をもらったよ」などと声をかけてもらえるようになった。「これは非常に嬉しいことだった」と片岡氏。
東日本銀行が再生 成長路線に回帰
これまでコンコルディアFGは、地銀最大手である横浜銀行は強いものの、グループを形成する東日本銀行が課題を抱えていた。18年7月には営業成績を上げるために行っていた不適切融資と、その審査体制に対して、金融庁から業務改善命令を受ける事態に。
背景には「対等の精神」を謳って統合したことから、東日本銀行側が横浜銀行に飲み込まれまいと〝背伸び〟をしてしまったことにあるという見方が強い。
そこで業務改善命令以降は横浜銀行が関わって再生を進めてきた。その過程で片岡氏も19年から2年半、東日本銀行取締役を務め、改革を進めてきた。
2期連続の赤字に沈んだ時期もあったがその後、横浜銀行出身で前頭取の大石慶之氏らの奮闘もあり、24年3月期決算では3期連続最終黒字の見通し。創立100周年の24年に頭取を生え抜きの助川和浩氏に交代。
「東日本銀行の行員も頑張ってくれたが、お客様が支えてくれた。また、横浜銀行出身、東日本銀行プロパー、関係なくお客様が受け入れて下さったことは回復の土台になった」
コストや人員の削減など〝荒療治〟を打った時期もあったが、「世の中が変化する中、東日本銀行だけが変わらなくていいなんていうことはない」という変化の必要性を片岡氏も、前頭取の大石氏も、東日本銀行の行員に説いて回った結果、徐々に意識も変化していった。
さらに23年4月には同県内の第2地銀、神奈川銀行を連結子会社化。これによって神奈川県の地銀は「1県1グループ」となった。片岡氏が神奈川銀行に統合の検討を打診したのは22年8月のことだったが、元を辿れば10年ほど前から検討していた課題だった。なぜ今、子会社化に踏み切ったのか?
片岡氏は「私が東日本銀行に行っていなければ、もしかしたら、このような判断はしなかったかもしれない」と振り返る。
横浜銀行と東日本銀行の統合でコンコルディアFGが誕生したのが16年のこと。東日本銀行が成長軌道に回帰し、グループ一体で歩むことができるまでに、かなりの時間を要している。「風土が違う会社同士が同じ方向に向かって成果を上げていくのは1年や2年ではできない」というのが実感だった。
そのため、「先々大きな変化が、これまで以上のスピード感で起きてくる。環境変化が起きてからの経営統合ではお互いに不幸になる。もし統合するのであれば前向きに、お互いが健全な時にやった方がいい。そしてシナジーを出すのには時間がかかる」という考えから、神奈川銀行のグループ化を決断。
今後は横浜銀行の持つ営業ツールやシステム、資金を神奈川銀行に提供して取引を深めていくと同時に、横浜銀行がフォローしきれていない顧客をカバーしてもらうなど相互補完関係を築いていく。
片岡氏には「地域の中で、金融機関同士が競争するのは意味がない」という考えがある。メガバンクがグローバルの中で日本をどう成長させるかを考えているのに対し、地域金融機関は、拠点を置く地域をいかに成長させるかが役割。
そのため、地域金融機関同士で健全な競争をしながらも、連携できるところは連携をして、共に地域の成長に貢献することが大事だということ。そうした考え方に基づき、東京では21年に東京きらぼしフィナンシャルグループのきらぼし銀行と提携。これにとどまらず、東京の地銀とも連携を模索していく考え。
「人への投資」をいかに進めるか
グループの中核である横浜銀行に課題はないのか。
24年度までの中期経営計画で打ち出した目標に対しては順調に推移しているが、片岡氏が考える課題は大きく2つ。
1つは「人的資本投資」。時代の変化の中で人材が流動化している。その中で「横浜銀行に対してロイヤリティ(愛着)を持ってくれる人を、どれだけ確保できるか」が課題。
そのために人事制度の改定、専門人材の育成、実力主義でポストに登用するといった施策を進めている。
現場からの発案による、新たな取り組みも始まっている。25年入社の新卒採用活動から、総合職の採用において「Talent+(タレントプラス)採用」という新たな応募枠をつくった。応募者に「自己PR動画」を提出してもらい、その学生時代の経験や、得てきた成果を伝えてもらう。これによって、これまでの横浜銀行にはいなかったようなタイプの人材を採用し、会社に変化をもたらすことを狙う。「こうしたことをボトムアップでやってくれたことが嬉しい」
売り手市場で応募者の選択肢は多く、転職を見据えて就職する人も増えている。「我々も、それを前提として物事を考えていかなければいけない」と片岡氏。
もう1つは「企業価値の向上」。そのために、今以上に「資本の有効活用」を進めていく必要があるというのが片岡氏の考え。株主への還元を進めていくだけでなく、グループの成長に向けて資本を振り向けていくことが求められている。
ソリューションの拡充の他、既存ビジネスのさらなる成長、デジタル化、さらにはM&A(企業の合併・買収)などに活用していくことを考えている。
行員の意識も変わってきている。顧客のニーズが変化し、ソリューション・ビジネスを深めていく中で「我々銀行がサポートできる余地が広がってきている」から。
今、目の前にいる企業に伴走していくことはもちろんのこと、10年後、20年後に向けた〝種〟を蒔いていくことが必要。その一例として、23年4月から、赤字のスタートアップでも成長性や将来性があると見れば融資する「ベンチャーデット」への取り組みを始め、すでに融資実績も出てきている。
神奈川銀行との真の意味での融和はこれからだが、横浜銀行が県内の大企業・中堅企業、東日本銀行が東京・神奈川の中小零細企業、神奈川銀行が県内の中小零細企業といった形で、エリアの顧客を「深掘り」できる体制が整った。
24年度は現中計の最終年度。すでに次期中計に向けた議論が始まっている。片岡氏は「次期中計のポイントは成長」と力を込める。「今の延長線上の成長と、プラスアルファの成長を神奈川、東京のマーケットをベースにしてつくっていくか。資本効率を上げながら成長できるか」
30年間成長が止まっていた日本の時計の針が、「金利が付く時代」への回帰で動き始めた。その中で個人、企業が成長できるためのソリューションを提供できるかが、コンコルディアFGの成長を左右することになる。