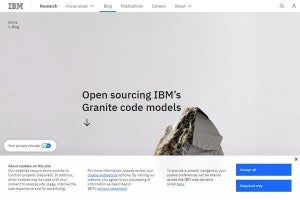IBMのAI&データプラットフォーム「IBM watsonx」が昨年の「Think 2023」で発表されてから、ちょうど1年が経過しようとしている。本稿では、IBMにおいてソフトウェアの製品開発総責任者を務める、IBM Senior Vice President, Products, IBM SoftwareのDinesh Nirmal(ディネシュ・ニルマル)氏にインタビューを紹介する。
Dinesh Nirmal(ディネシュ・ニルマル)
IBM Senior Vice President, Products, IBM Software
IBMソフトウェアの製品開発総責任者。新製品とイノベーション、ソフトウェア製品とテクノロジーの方向性、戦略、サポート、エコシステムの開発を担当。AI、インテリジェント・オートメーション、機械学習、デジタルレイバー、データおよびAIガバナンス、データ・サイエンスに関する深い専門知識を駆使し、顧客のデジタルトランスフォーメーション・ジャーニーを支援し、最も差し迫った課題に取り組むことで知られている。
IBMに25年以上在籍し、それ以前はIBMのデータ・AI・オートメーション担当ゼネラル・マネージャーとして、ソフトウェア・ポートフォリオの事業戦略、技術開発、オペレーション、セールス・マーケティング、財務全般の推進を担当。
「IBM watsonx」を軸としたAIにおける3つの戦略
--まずは、最近のIBMにおけるソフトウェア関連の動向について教えてください。
ニルマル氏(以下、敬称略):IBMのコアストラテジーはハイブリッドクラウドとAIです。ハイブリッドクラウドは、どのようなクラウドであってもファイアウォールの裏側でサービスが提供できるクラウドという意味において、それを成功させるものがRed Hat OpenShiftをはじめとしたRed Hatのオファリングです。これにより、一度開発すればどこでも実行できる状況を担保できるようになります。
一方、AIは生成AIのソリューションをハイブリッドクラウド上で利用できるようにすることが他社との差別化要因になります。生成AIは「IBM watsonx」を軸に「プラットフォーム」「データ」「ガバナンス」の3つを戦略の柱として位置づけています。
生成AIをエンドツーエンドで活用できるIBM watsonxでは3つのコンポーネントで構成されています。まずは「watsonx.ai」です。当社の独自モデルは、責任を持って用意したデータセットで学習したものであり、AIを利用して訴訟の憂き目にあったとしてもデータの出自がハッキリとしています。
データに関しては「watsonx.data」があります。モデルの学習のためには膨大な非構造化データが用いられます。これにより、例えばベクトルDBやRAG(Retrieval Augmented Generation:検索拡張生成)、Q&Aといった、さまざまな機能がサポートされます。
ガバナンスについては「watsonx.governance」です。これは、モデルをデプロイする際に、セキュアであることやリスク、コンプライアンスを担保します。お客さまが生成AIを使う際、ないしはデプロイするときには常にリスクが付きまといます。
モデルが劣化するかもしれない、バイアスを持っているかもしれないといった不安要素や、ヘイトなどへの対応が必要なりますが、watsonx.governanceでカバーできます。また、国別や地域別の規制にも対応できます。
これらの戦略のクリティカルパスはAIモデルとなります。IBM独自のモデルに加え、Hugging FaceやMetaなどとパートナーシップを締結しており、モデルのエコシステムを構築していくことを重視しています。
また、昨年12月にはMetaと「AI Alliance」を立ち上げ、生成AIに関して単一の観点・理解により、さまざま業界でどのように利用されているのかを網羅的に把握するためのアライアンスとなります。
--IBM watsonxで最近の特徴的なサービスは、どのようなものがありますか?
ニルマル:IBM watsonxプラットフォーム上で使われるソフトウェアで興味深いものとして「IBM watsonx Orchestrate」があります。これはAIを活用して、デジタルレイバー(自動化ツールやAIを利用して作成されたソフトウェアロボット)をオーケストレーションするというものです。
通常の従業員であればペルソナ、クレデンシャル、スキルという3つの要素で構成されますが、デジタルレイバーは「APIコール」「ボット」「ワークフロー」といったものになります。これらを人があたかも作業しているかのように、スムーズに実行するものがIBM watsonx Orchestrateとなります。
IBM watsonx Orchestrateは、ある意味でアシスタントとして市場に提供されていますが、IBM社内でも活用しています。例えば、人事や財務、調達部門で導入しています。
もう1つは「IBM watsonx Code Assistant」です。開発者やITオペレーターが自然言語プロンプトを使用して、速く、正確にコーディングできるように支援する生成AIを活用したコード生成機能を備えています。
コードから別の言語に変換したり、説明可能にしたり、文書化したり、自動化したりすることなどができます。最近、特にお客さまから評判が良かったのはCOBOLからJavaへのコード変換です。
さらに、生成AIを活用したITの自動化も重要な領域になります。コスト最適化や可視化を行うためApptioやTurbonomicなどを買収しており、OPEX(Operating Expense:事業運営費)を年間30%削減という成果を出しています。
一方、ソフトウェア戦略のおいて重要になってきているのがセキュリティ、特にデータセキュリティです。当社でも、この分野に多くの投資を行っており、データ量は年々増加していくことから、いかにモニタリングし、どのようなデータセキュリティ関連のルールを整備するのかは、お客さまにとっても重要になっています。
また、サステナビリティとしてお客さまがどのようにグリーンITを実践していくかということもあるほか、アプリケーションのモダナイゼーションも注目を集めています。
このような課題に対して、IBMではグローバルレベルのサポートを提供できており、NPS(ネットプロモータースコア)は80以上のスコアを得ており、お客さまの評価は高いものになっています。
watsonxはIBMにとって最大の賭け
--IBMの戦略として現在、特に注力しているものは何でしょうか?
ニルマル:当社の“賭け”がIBM watsonxです。まずは、IBM社内で生成AIを活用して、生産性の向上や最適化を行い、そこで得た知見と合わせてお客さまに提供し、生産性向上や最適化の課題に取り組んでもらうことを目指しています。
ここ数カ月の間で社内で複数のプロジェクトが走り始めており、特に重視しているのは開発者チームがコードモデルを全員が使い、コード生成したり、文書化したりする取り組みを行っています。意図的に生成AIを社内で幅広く利用することが戦略の第一歩になります。
パートナーシップで特筆すべきことは、最近では北海道の半導体製造におけるRapidus(ラピダス)との協業があり、いかに当社がIBM watsonxと生成AIを最大の賭けとして取り組んでいるのかを示すものとなります。社内、お客さまにとっても大きな成果を生み出しつつあります。
--AIプラットフォームを提供しているAWSやGoogle Cloudなどとは、どのような差別化を図っていますか?強みを教えてください。
ニルマル:3つあります。1つは、先ほども述べましたが、モデルの出自が明らかだということです。学習に利用するデータの出自はお客さまにとって信頼性を担保するためにも重要です。そのため、独自のモデルをファインチュー二ングするにあたっても学習に使われるデータの出自が明らかということは、これからも重要視されていくに違いありません。
2つ目はハイブリッドクラウドという観点です。AWS(Amazon Web Services)やGoogle Cloudにしろ、ハイパースケーラーの場合は独自のクラウドを重視する傾向にあります。しかし、お客さまにとって重要なことは、複数のファイアウォールにまたがって内側でどうするかということです。
特に、自社のプライベートなデータをパブリッククラウドには載せたくないと思われるお客さまが多い中で、ファイアウォールの外側でプラットフォームが活用できることは大きなメリットになりますか。
そして、3つ目は単体で何かをやろうとするのではなく、多くのパートナーとの連携により、さまざまなイネーブルメントを行い、成功を積み重ねて、複数のベンダー間でそれが可能になれば初めてお客さまに真の価値が提供できるようになります。だからこそ、エコシステムを構築しています。
日本におけるwatsonxの展開はどう考えているのか?
自社におけるデータ活用は重要ですが、IBM watsonx.dataで企業における混在したデータの整備をどのように支援できますか?
ニルマル:データ関連では、さまざまな作業が必要になります。データのクリーニングを行うことで初めてエンジニアがETL(Extract:抽出、Transform:変換・加工、Load:格納)が可能となり、クリーニング後は構造化されたフォーマットに転換しなければなりません。永続的なデータレイヤを提供することは重要な役割ですが、いかにデータのクリーニング、ETLを行うツールの提供ということもポイントになります。
また、データのカタログ、メタデータなどがあることでデータガバナンスが効いてくることから、お客さまが使える形のデータに可能な限り早くアクセスすることが価値になるため、こうした状況を実現するための支援ができます。
現在、お客さまの最大の課題はデータそのものではなく、信頼できるデータに対して、いかにデータサイエンティストがアクセスできるかです。これができて初めてモデルを作成することが可能になります。
そこで、当社はData Product Exchangeを当社では発表しています。これはデータをカタログするサービスとなり、データサイエンティストがモデルを学習させるための信頼できるデータに早くアクセスできるようにするものです。
IBM watsonx.dataのユースケースとして考えられるのは、RAGやQ&Aなどです。そのためにベクトル専用のデータベースとして「Milvus」を用いています。Milvusはエンタープライズ用のデータ分析基盤となり、大量のデータを効率的に処理することを可能とします。例えば、インデックス機能や検索の高速化などが図れます。
日本における投資やユーザー獲得に向けた施策について教えてください。
ニルマル:投資については、開発ラボを設けていることから、日本の人材を確保したうえで日本のお客さまが次世代生成AIの活用を支援できます。
日本語の基盤モデルやサポートなどが日本独自のものとして挙げられることに加え、IBM watsonx.aiのMZR(マルチゾーンリージョン)によりクラウド上のデータを国外に出すことがないようにガバナンス対応しています。また、前述したIBM watsonx Orchestrateによるワークフローの自動化、最適化を支援できます。
NTTデータとは昨年末に保険業界における従業員の生産性向上を図るため、IBM watsonx Orchestrateで支援することで協業に合意しています。
これは大きなチャンスであり、IBM watsonx Orchestrateを活用することで、ボットの効率や生産性の向上が見込まれるからです。NTTデータ社内においてもパフォーマンスの課題はありますし、彼らのお客さまに対して成果を提供できるようになるという意味では拡大していくと考えています。
保険業界に限らず、金融機関、製造業、ITなどでは役立つものであり、スキルや一連のタスクを人があたかも行うように定義でき、どのような業界でも当てはまると考えています。