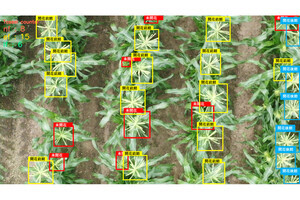東京大学(東大)と玉川大学は4月12日、野生種8種と栽培種2種のトマトの光合成特性を比較調査した結果、一般的な栽培種よりも優れた光合成能力を持つ野生種を発見したと共同で発表した。
同成果は、東大大学院 農学生命科学研究科の吉山優吾大学院生、同・矢守航准教授、玉川大学大学院 農学研究科の小林孝至大学院生(研究当時)、同・大学 農学部 先端食農学科の田淵俊人教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、植物生物学に関する全般を扱う学術誌「Journal of Experimental Botany」に掲載された。
植物は光合成により光からエネルギーを生産しており、作物の成長や収量を左右する重要な要素。つまり、光合成能力を向上させた作物を開発することで、生産性のさらなる増加が期待できるとする。近年は野生種の光合成が注目されており、栽培種より優れた光合成能力を持つ野生種のイネも報告されているが、野生種と光合成の研究はイネなどの穀類に限られていたという。
-

野生種トマトは南米のアンデス山地の太平洋沿岸を主な原産地としており、湿潤な環境から過酷な環境まで、さまざまな生育環境に適応している。さまざまな野生種と一般的な栽培種を用いた解析の結果、栽培種と比較して高い光合成能力を持つ野生種が発見された。さらに、平均気温が高く、降水量も多い環境で自生していた種であるほど、小サイズで高密度の気孔を持ち、その結果、優れた光合成能力を示すことが明らかにされた(出所:東大Webサイト)
トマトは、世界で約1.9億トンと最も多く生産されている園芸作物で、南米のアンデス地方とガラパゴス諸島を原産地とし、野生種は数万年にわたってそれらの地域のさまざまな環境に適応して自生しており、未知の多くの機能性を保有している可能性があるという。中には過酷な高山環境に適応して自生するものも存在するため、光合成能力の高い野生種の存在が期待される。しかし、そのほとんどが調査・研究されていない状況だったとする。そこで研究チームは今回、原産地に自生する野生種と栽培種のトマトの光合成特性を網羅的に調査することによって、栽培種育種に活用できる可能性を探索していくことにしたとする。
今回の研究では、野生種8種に加え、栽培種2種が栽培され、ガス交換測定装置を用いて、それぞれの光合成特性が測定された。暗黒状態から一定の強光を照射した光合成誘導の解析では、「S.lycopersicumvar.cerasiforme」や「S.chmielewskii」など、複数の野生種が、栽培種よりも強光を照射してから短時間で光合成速度と「気孔コンダクタンス」(気孔を介した大気から葉内へのCO2輸送の効率を表す指標)を上昇させ、なおかつ、定常状態において高い光合成速度と気孔コンダクタンスを示すことが確認された。
-

野生種と栽培種の光合成特性。(A)光合成速度の時間変化。(B)光合成速度の最大値。(C)光合成速度の最大値の50%値に到達するまでに要した時間。(D)気孔コンダクタンスの時間変化。(E)気孔コンダクタンスの最大値。(F)気孔コンダクタンスの最大値の50%値に到達するまでに要した時間。添付されたアルファベット(a~f)が異なるトマト種間には、有意差があることが示されている(出所:東大Webサイト)
次に、定常状態における光合成特性と光合成誘導の特性の相関関係が解析されると、光合成誘導が速い野生種は、気孔コンダクタンスの光応答が速いだけではなく、定常状態における気孔コンダクタンスと光合成速度が高いことも判明。また、光合成誘導反応で高い光合成能力が示された野生種は、野外の日中光環境を再現した野外変動光を照射した時の光合成速度の積算値も高いことがわかったという。光合成速度の積算値と光合成誘導や気孔コンダクタンスの光応答性も、高い相関関係が示された。つまり、光強度の変動に合わせて気孔が素早く開閉応答することによって、野外変動光下でも高い光合成能力を示せることが解明された。
-

光合成誘導反応における各パラメータの相関関係図。(A)Amaxとt50Aの相関関係。(B)Amaxとgsmaxの相関関係。(C)t50gsとt50Aの相関関係。(D)t50gsとgsmaxの相関関係。(E)Amaxとt50gsの相関関係。(F)gsmaxとt50Aの相関関係(出所:東大Webサイト)
続いて、栽培されたトマトの葉の気孔のサイズと、気孔密度の測定が行われた。観察の結果、トマト種によって、小サイズで高密度の気孔を持つ葉と、大サイズで低密度の気孔を持つ葉に分類されることが判明。さらに、気孔特性と光合成特性の関連性も解析が実施された。すると、小サイズで高密度の気孔を持つトマト種の方が、光合成速度の最大値の50%値に到達するまでに要した時間が短いことから、優れた光合成能力を発揮するという関連性も突き止められた。気孔が小さいことは、単位面積あたりの孔辺細胞の体積が小さいことを表している。孔辺細胞の体積が小さいと、気孔開閉を制御するK+イオンの濃度変化が激しくなるため、気孔開閉が迅速に行われると考えられるという。
-

野生種と栽培種における光合成の変動光応答。(A)野外変動光の光量子束密度。(B)野外変動光照射中における光合成速度の時間変化。(C)10時間の測定で記録された光合成速度の積算値(ASUM)とt50Aの相関関係。(D)ASUMとt50gsの相関関係。(E)ASUMとAmaxの相関関係。(F)ASUMとt50gsの相関関係(出所:東大Webサイト)
これらの先進的な科学技術に基づいた知見に加えて、今回の研究で用いられた野生種トマトの自生地環境(気温・降雨・標高)や実用化に向けた栽培特性についての知見を用いて、気孔・光合成特性との関連性の解析が実施された。その結果、年間降水量が多い環境に自生する野生種トマトは、気孔密度が高くなる傾向が得られたとする。また、標高が高く、平均気温が低い環境に自生する野生種トマトは、光照射に対する光合成速度の上昇が鈍いことも確認された。つまり、平均気温が高く、降水量も多い環境で自生していたトマト種であるほど、優れた光合成速度を示す傾向がわかったのである。
-

野生種と栽培種の気孔特性。(A)気孔サイズ。(B)気孔密度。棒グラフのY正軸方向は向軸面。Y負軸方向は背軸面のデータを表す。(C)背軸面の気孔サイズと気孔密度の相関関係。(D・E)Amaxと背軸面の気孔サイズと気孔密度の相関関係。(F・G)gsmaxと背軸面の気孔サイズと気孔密度の相関関係。(H・I)t50Aと背軸面の気孔サイズと気孔密度の相関関係。(J・K)t50gsと背軸面の気孔サイズと気孔密度の相関関係。添付されたアルファベット(a~e)が異なるトマト種間には有意差があることが示されている(出所:東大Webサイト)
これらの結果は、野生種トマトが栽培種を成立させるに至る過程を解明する、新たな研究の方向性を見出すきっかけになる可能性もあるという。そして今後、これらの野生種が持つ有用な光合成形質を栽培種トマトに導入することができれば、トマトの生産性向上に大きく貢献できることが期待されるとしている。