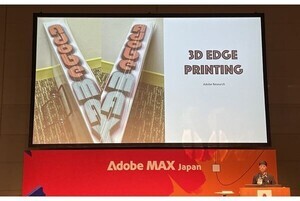2024年から日本でも「合理的配慮の提供」が求められる「ウェブアクセシビリティ義務化」。開始までの残り日数が少なくなっている中、日本での対応はどの程度進んでいるのだろうか。
今回は、米国のアドビでエンタープライズ向けDocument Cloudのグローバル製品およびマーケティング戦略を統括している山本晶子氏にウェブアクセシビリティの義務化に関する潮流を中心に、日本と米国のDX(デジタルトランスフォーメーション)の進み方の違いを聞いた。
プロフィール
米国Adobe, Inc. デジタルメディア事業部 Document Cloud プロダクトマーケティングディレクター
1999年米国Adobe, Inc.に入社。ビデオ編集ソフトPremiereの開発、アドビストアおよびCRM基幹システムの立ち上げにビジネスアーキテクトとして従事した後、Acrobatのプロダクトマネージャーとして製品戦略と仕様の決定に携わる。プロダクトマーケティング部門の立ち上げにより現職。エンタープライズ向けDocument Cloudのグローバル製品およびマーケティング戦略を統括。
「ウェブアクセシビリティの義務化」とは?
--そもそも「ウェブアクセシビリティの義務化」とはどのような内容なのでしょうか?
山本氏(以下、敬称略):米国司法省が「Americans with Disabilities Act (ADA)法」がウェブコンテンツにも適用される」という立場を初めてとったのが1996年で、Webサイトに掲載しているドキュメントについて、どのような健康状態の方でもきちんと理解ができるようにしましょう、という取り組みです。
米国では「イコールオポチュニティー」という言い方をするのですが、色弱もしくは全盲の方であっても同じようにサービスを受けられるようにサービスを提供しなさいというのが主な目的になっています。
--米国から始まった取り組みなのですね。これが日本でも義務化されるということでしょうか?
山本:日本は2024年4月に障害者差別解消法の改正が施行されることに伴い、2024年6月から一般企業にも「合理的配慮」が義務化されます。
個人的には多様性に配慮した非常に良い流れだと思っているのですが、ただ、やはり大手の企業ほど、この義務化に相当焦っている印象を受けます。
社内にウェブアクセシビリティを進めるためのノウハウは蓄積されている一方で、対応には人手が足りないというのが現状です。通常、Webサイトにタグ付け(Webページに表示させる情報を指定する文字列を付けること)を行う際は、目で見て、内容をチェックした上で行います。
そのため、人海戦術を必要とするケースが多いのですが、一気に多くのWebサイトを変更するためには人が何人いても足りないという課題があるのです。
--アドビではその課題解決のためにどのようにアプローチしているのですか?
山本:アドビが提供しているAcrobatやAPIを使用して作成されたPDFには文書の構造・順序を定義し、画像に代替テキストを提供するためのタグ付けがされています。アクセシビリティを確認する機能を使って最終確認を行っていただくことによってスクリーンリーダーに対応したPDFを完成することができます。
またAcrobatには読み上げ機能(Read Out Loud)があるため、お客さまはその機能を使って、サイトにあるPDFの内容を理解することができます。
金融業界で進むウェブアクセシビリティの取り組み
--各社がウェブアクセシビリティの対応に追われているというお話でしたが、特に対応に力を入れている業界などはあるのでしょうか?
山本:弊社が最近大きいお話をいただく機会が多いのは、銀行や証券会社、投資会社などの「金融業界」です。
ウェブアクセシビリティは、生まれつきの障害を持つ方々に配慮するという意味合いももちろんありますが、加齢や白内障などの病気による視力低下の方に配慮するという意味もあります。特に投資を行う人は年齢層が高めの方が多いため、業界としてその点に注力する企業が多くなっていると聞いています。
また、普段から投資に関わっている業界ということもあって、「企業の評価」に敏感なのもこの業界の特徴です。世界的に「多様性に配慮した企業であるべき」という考え方はマストになりつつあり、その点をクリアしなければ顧客離れが考えられます。
--金融業界に限らず、多様性や環境問題などの問題に注力する企業は多そうですね。
山本:特に「Generation Z(Z世代:1990年代半ばから2000年代前半生まれの世代)」と呼ばれる世代は、会社やサービスの選び方として、「どれだけその会社がコーポレートレスポンスビリティを果たしているか」という点を気にしているので、より企業としての注力度合は高まっていると言えます。
アドビとしても、PDFの活用を促進することで、ペーパーレス化を進めて環境問題に立ち向かっていきたいと考えています。
--ペーパーレス化という言葉が出ましたが、日本と海外を比べて、ペーパーレス化推進の速度に違いはあるのでしょうか?
山本:日本に比べて海外はかなりペーパーレス化が進んでいると思います。特にイギリスやドイツといったヨーロッパは、かなり意識を高く持ってペーパーレス化に対応しています。もちろんアメリカでもペーパーレス化はかなり進んでいて、仕事をしていても、ほとんど紙は見なくなりました。
日本でも意識を高く持って進めている企業も多くいると思いますが、名刺の文化がなくならない現状を見ると、他国と比べるとまだ進み始めたところなのかな、と感じます。ペーパーレス化は、環境問題への配慮という面だけでなく、セキュリティ面でも重要な意味を持つので、日本での推進にも注力していきたいですね。
--ペーパーレス化以外にアドビとして注力している分野はありますか?
山本:個人的には、ドキュメントの処理をさまざまなデバイスで行えるような世の中になってほしいと思っています。現在、書類の確認や契約書へのサインなどといった業務を行う際は、デスクトップから行う方がほとんどだと思います。
しかし、弊社のAcrobatなどは、スマートフォンのWebサイトから確認することができるため、この使い方をしていただければ、より働き方の多様性を高められるのではないかと考えています。
以前、弊社が行った調査で「ビジネスパーソンの6割がPDFを書き換えられないと思っている」という結果も出ましたが、まずは弊社の製品を知っていただいて、こういった固定観念を打ち壊していきたいと思っています。