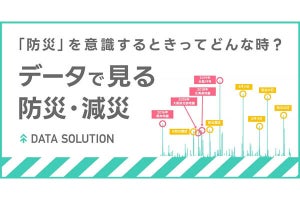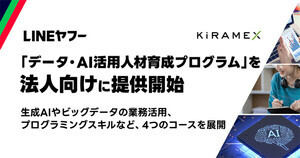今年は元日に能登半島地震が発生し、大きな被害をもたらし、今も回復に向けた取り組みが進められている。加えて、3月に入ってからは千葉県で地震が頻発し、関東地方も予断を許さない状況にある。
そうした中、LINEヤフーは能登半島地震発生から数日で、「Yahoo!防災速報」アプリにおいて被害状況を反映した「災害マップ」を公開した。同社はいかにして迅速にサービスリリースを行ったのか。
今回、同社の「Yahoo!天気・災害」プロダクトリード 田中真司氏に、「Yahoo!防災速報」の開発や活用術、能登半島地震に関する同社の取り組みなどについて聞いた。
14種類の防災情報を入手可能
LINEヤフーは、Webサイトでは「Yahoo!天気・災害」サービスにおいて、災害情報を提供しており、また、災害情報を提供するスマホアプリとして「Yahoo!防災速報」を公開している。
同アプリでは、気象情報、豪雨予報、地震情報(震度3以上)など14の防災情報を提供している。地震情報に関しては、事前に設定しておいた地域で震度3以上の地震が発生すると、アラートが鳴り、同サービスを利用している人も多いだろう。
田中氏は同アプリについて、「スマホアプリなので、プッシュ通知が強みです。ユーザーの方々は置かれている状況がさまざまです。「Yahoo!防災速報」ではユーザーが情報が必要な場所を設定できるので、個人に特化した情報を届けることができます」と語る。
「Yahoo!防災速報」がリリースされたのは遡ること2011年7月で、東日本大震災をきっかけに生まれたサービスとなる。当初はメール版だったが、同年12月にiPhoneアプリ、翌年3月にAndroidアプリがリリースされた。
覚えておられる方もいるだろうが、東日本大震災では東京電力の発電所が被害を受けたため、電力不足が起こり、毎日計画停電の予定がアナウンスされていた。
しかし、それを知らせる手段がなかったため、「Yahoo!防災速報」で地震や津波の情報に加えて電力供給に関する情報の提供を始めたという。
「身に迫っている危険な情報、ユーザーに知ってほしい情報を届けたかった」と田中氏は語る。ただし、復興が進むと電力不足も解消されたことから、「Yahoo!防災速報」では気象災害の情報提供にシフトした。
「防災タイムライン」で自分の家族に合わせた災害への備えを
田中氏は、「Yahoo!防災速報」の運営において難しい点として、情報の発信元が複数あることから、データのフォーマットがバラバラであることを挙げる。そこで、同社においてデータのフォーマットを統一することにより、アプリという単一のプラットフォームからユーザーに適切な形でさまざまな情報を届けている。
「Yahoo!防災速報」では、位置情報を用いて、現在地に情報を通知する。また、任意で最大3地点の情報を登録しておくこともできる。つまり、ユーザーの増加とともに通知のパターンも増えるため、データの管理が煩雑になる。ここでも同社の技術力が生かされ、スピーディーな通知が可能となっている。
田中氏は、今後起こりうる災害への備えとして、「Yahoo!防災速報」で特に使ってもらいたいサービスとして、災害時の防災行動をまとめておける「防災タイムライン」を紹介した。「防災タイムライン」は自宅周辺の「ハザードマップ」を確認でき、緊急時に避難する「避難所」や「緊急連絡先」を登録することができる。
災害時の行動は、「お年寄りがいるか」「子供がいるか」など、家族構成によって異なってくる。備蓄品も同様だ。「防災タイムライン」で家族構成を入力すると、必要な備蓄品を表示してくれる。ほぼ日本全国、いつ大規模地震が来てもおかしくないが、災害時の行動をシミュレーションできている人はどのくらいいるだろうか。
田中氏は「防災行動を起こすタイミングは自分で決めることが大事です」と話す。自分事として認識していなければ、いざとなった時にその通りに行動に移すことができない。「Yahoo!防災速報」では、「防災タイムライン」にユーザーが事前に登録したさまざまな条件に合わせてプッシュ通知をしてくれる。
交通情報の提供とアイコン表示を開始
さて、能登半島地震への対応について、「地震、津波の情報をいち早く提供することが私たちの使命ですが、滞りなくできました」と田中氏は話す。能登半島地震においては、北陸地方にとどまらず、東京、名古屋、大阪でも地震が発生し、配信の件数が多かったが滞りなく提供できたそうだ。
田中氏は、「災害マップ」における初めての取り組みとして、交通情報の提供を挙げた。山間部では地震や大雨により道路が崩壊し通行止めになることがある。液状化や地割れの被害もあり、能登半島地震でも道路の崩壊が多く見られた。通行止めの情報を知らずに現地に行って引き返すことになったら、多くの人の時間が無駄になる。とはいえ、災害発生時の正確な交通情報を知ることは難しい。
そこで、同社は日本道路交通情報センター(JARTIC)に相談して、情報を提供してもらうことにした。加えて、田中氏とは異なる事業部が運営している「Yahoo!カーナビ」というサービスが平時からJARTICと連携していたため、そのコネクションを生かして年始でもスピーディーな連携を実現できた。このようにさまざまな人たちと連携して、交通情報の提供にこぎ着けた。
「能登半島地震でもそうでしたが、災害発生時はどこで何が起こっているかわかりません。本来の『災害マップ』の思想は、ユーザー同士が災害の状況を共有しあうことで避難行動を支援するというものでしたが、能登半島地震ではそれに加えて、現地の支援に関する情報を可視化して、避難生活に役立ててもらうことにしました」(田中氏)
今回、自治体の公開情報などから情報を集め、給水所、入浴・シャワー、支援物資拠点、トイレなど、避難生活に必要な情報が一瞥できるよう、「災害マップ」上のアイコンで示せるようにした。SNSなどを活用して、これらの情報を得ることもできるが、地図を見て一目でわかれば非常に便利だ。
能登半島地震は1月1日に発生したため、「Yahoo!防災速報」のチームの皆さんも休暇に入っていたが、Slackでやり取りをして、オンライン環境で上記のようなサービスの開発を行ったそうだ。皆さんの連携の甲斐あって、アイコンもどんどんブラッシュアップされたとのこと。
「被災者の方々の役に立ちたい」という気持ちが、「Yahoo!防災速報」のチームの皆さんを奮い立たせたのであろう。この熱意と共に、それを具現化できる仕組みが同社に備わっていたのも大きい。
同社はもともとどこでも働ける仕組みを整備していたが、それが、まさに機能したといえよう。普段から、チームのメンバーは、東京、名古屋、北海道とバラバラの地域で働いており、リスク分散にもなっている。
もっとパーソナルな情報を届けていきたい
ここまで作りこまれた「Yahoo!防災速報」だが、田中氏は「まだまだ発展途上です」と語る。「今や、ユーザーの皆さんが1人1台スマートフォンを持っています。インターネットのよさを生かして、一人一人に合わせた、パーソナルな情報を提供していきたいです」と同氏。
先述したように、「Yahoo!防災速報」では、ユーザー個人の「防災タイムライン」に合わせてプッシュ通知を行うが、「もっと細やかなアドバイスがしたい」と田中氏はいう。
そのためには、「われわれが被災地の状況を今以上にリアルタイムで把握し、ユーザー皆さんのニーズや状況により合致した情報発信ができるようにしたい」と語る田中氏。
災害発生時は自分に必要なデータを少しでも早く手に入れることが重要となる。災害大国に生きる私たちは災害発生時に備えたデータ活用を考える必要があるといえよう。