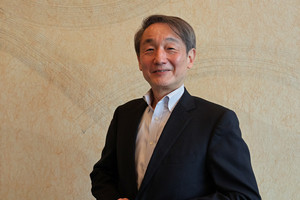オリンパスは2月26日、グローバル規模での人材戦略と人事制度の変革について語る記者向けのラウンドテーブルを都内で開催した。昨年に引き続き人事・総務担当役員の大月重人氏がスピーカーを務めた。昨年も示された基本戦略となる3本柱について、本稿ではそのアップデート状況にフォーカスしてお伝えしたい。
コアバリューを策定し新たな3本柱を設定
VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性の頭文字を取ったもの)の時代とも呼ばれる現代は、以前に増してHR(Human Resources:人的資源)の重要性が高まっている。
そうした中でオリンパスは2018年に、「世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現」をパーパス(存在意義)として定め、真のグローバルメドテックカンパニーとなることを目指し変革中だ。特に人材管理と次世代の人材育成、組織の簡素化、グローバル化と企業風土改革などに挑戦している。
今年打ち出している人事戦略の3本柱は「コアバリュー改定」「人事制度の真のグローバル化」「健やかな組織文化、働き方改革」だ。なお、昨年の3本柱を見ると「HR組織自体のグローバル化」「人事制度の真のグローバル化」「健やかな組織文化、働き方改革」となっている。
「HR組織自体のグローバル化」はこの1年で体制の構築と社内外への浸透が進んだ一方で、コアバリューは1月に改訂したばかりであり今後の浸透が必要になるとして、柱を入れ替えたとのことだ。
1本目の柱:コアバリュー改定
同社は2018年に定めたパーパスの下では、社員が持つべき5つの価値観をコアバリューとして定めた。その5つとは、「誠実」「共感」「長期的視点」「俊敏」「結束」だ。しかしコアバリュー策定から約5年が経過し、状況は変わりつつある。
以前に主力事業としていたカメラ事業および顕微鏡事業を売却し、医療に専心する企業へのシフトを図ったのも、そうした変化への対応の一つ。また、これまで地域ごとに運用していた各事業はグローバル化が進み、国内外の部門や地域を横断するチームも増えているという。加えて、FDA(アメリカ食品医薬品局)からWarning Letter(警告書)が出されたことを受けて、コンプライアンスへの対応も一層進めている。
このような状況の変化の中で、自社のあるべき姿を示して将来へ向けた大きな目標を再確認するためにも、今回のコアバリュー改定に至ったとのことだ。
新たに定めたコアバリューは、「誠実」「共感」を引き続き残しながら、「イノベーション」「実行実現」「患者さん第一」を加えた計5つ。なお、「長期的視点」「俊敏」「結束」も重要な要素であることに変わりはないため、行動様式として明瞭化している。
今後は新しいコアバリューと行動様式を日常の業務プロセスに浸透できるよう、リーダー層向けのトレーニングや、企業文化としての定着度確認、HR部門での実装など、およそ3年かけて認知と理解を高めていく方針。
2本目の柱:人事制度の真のグローバル化
人事制度においては、評価や等級など全社員のタレントマネジメントをグローバルで統一した。評価のタイミングは年1回で、成果の評価だけでなく、コアバリューに基づく行動評価、およびそれらを合わせた総合評価の3つの要素により5段階で評価される。
グローバル共通の評価制度を確立したことで、社員が世界のどこにいても同じシステムを使えるようになり、適材適所の人材配置が可能になるのだという。また、パフォーマンスマネジメントの過程にコアバリューを反映させることで、世界中の社員がコアバリューの発揮が重要であると理解し同じ方向を見て仕事ができるようになる。能力開発も評価に組み込んでおり、全社員が学び成長する文化の醸成も狙う。
等級制度は、特に管理職層においてグローバルで職責を基準とした等級体系に切り替えた。各自が担う職責基準を国内外で共通化しているが、非管理職についてはまだグローバルで共通化はできていないそうだ。現在までに国内のグループ会社も含めて制度を共通化している。
報酬制度に関しては、日本国内で共通化を図っている。職責が基準となる報酬水準とした。なお、報酬制度については各国や地域によって水準が異なるため、今のところグローバルで共通化する予定はないという。
3本目の柱:健やかな組織文化、働き方改革
同社の働き方のテーマは「Open」である。部門間の壁をなくすことでコラボレーションを加速する。また、エンゲージメントと生産性をさらに向上させて革新的な価値をステークホルダーに提供していく。グローバル化や大退職時代に対応すべく、エンゲージメントを強化して誰もがベストパフォーマンスを発揮できるようにするための施策だ。
まず、働き方を変えるためにABW(Activity Based Working)を取り入れた。本社を移転した八王子キャンパスに加えて、在宅勤務やシェアオフィス、サテライトオフィスなど、自身の業務内容に応じてどこが最適なのかを各自が判断していくマインドへと切り替えている。
出社日数や頻度に制限はないが、各チームにABWワークショップの実施を促している。これは、働き方についてチーム内で対話し同意を得ることで、自律的な働き方を選択できる企業風土を醸成するための一歩となる取り組みだ。
働く場所についても、ABWを実現できるよう、出社する目的に応じて機能や職種ごとに適切に使えるオフィスレイアウトへと再編した。特に本社機能を備え開発拠点でもある八王子キャンパスでは、隣のラボが何をやっているか分かるよう脱サイロを目指したオープンな空間などを設けている。
同社は今後について、自立したジョブ型人材の柔軟な働き方も支えられるよう、労務管理や福利厚生制度全般を変革する予定だとしている。現在までに評価制度や、採用および教育方針を定めたが、今後は勤務・休暇、福利厚生・社宅・寮、異動・転勤といった制度についても検討していく方針。