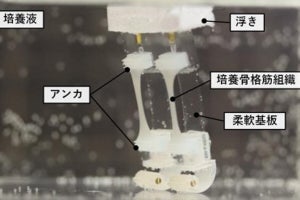電気通信大学(電通大)と大阪大学(阪大)の両者は2月15日、咀嚼(そしゃく)して食べられる可食素材でできたロボットを開発し、動いている状態で食べた際に知覚や食感が変化することを明らかにしたと共同で発表した。
同成果は、電通大 機械知能システム学専攻の仲田佳弘准教授、同・伴碧特任講師(常勤)、同・山木廉大学院生(研究当時)、同・堀部和也特任助教(常勤)、同・高橋英之招へい准教授、大阪大学大学院 基礎工学研究科 システム創成専攻の石黒浩教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米オンライン科学誌「PLOS ONE」に掲載された。
-

今回開発された可食ロボット。(a)可食部および可食部に空気を供給するチューブを接続するための部品の3Dモデル。(b)断面図。可食部の内部には2つの空気室があり、そこに同時に空気を供給すると縦方向の振動、交互に供給すると横方向に揺れる動作が生じる。(c)可食ロボットの実物。(d)実験のため、3Dプリンタで製作された持ち手を付けた可食ロボットの画像(出所:電通大プレスリリースPDF)
これまでにも可食素材を用いたロボットの開発は行われていたが、それを食べた時の心理的な影響についてまでは研究されていなかったという。そこで研究チームは可動部をすべて食べられる素材でロボットを作り、それを食した際の知覚、味覚、および食感を調査することにしたとする。
今回開発された可食ロボットはゼラチンと砂糖が主原料で、内部に空洞のある構造が作られており、そこに空気を入れて膨らませることで駆動する仕組みとのこと(空気圧駆動)。駆動にモータなどの食べられない素材を用いていないため、可動部すべてを食べられるのが特徴で、形状も食すことが考慮されており、口に入れやすいスティック状に設計されている。
この可食ロボットを用いて、2つの実験が行われた。第一の実験では、参加者がロボットの見た目からどのような印象を受けるのかが調査され、ロボットの基本的な設計と動きに焦点が当てられ、参加者の感覚的な反応が探られた。
そして第二の実験では、参加者が実際にロボットを食べた上で評価を行った。動いている状態のロボットを食べる条件と動いていない状態のロボットを食べる条件の2条件で実施され、参加者によりロボットを食べた際の印象、味、および食感の評価が実施された。印象と味の評価は、あるトピックに関する多段階の選択肢を含むアンケートを使用し、回答者が各項目に対してどの程度同意するかを測定するための尺度である「リッカート尺度」が用いられた。また食感の評価は、複数の「オノマトペ選択肢」から得られた感覚に近いものを選択する手法が採用された。なおオノマトペとは、「コリコリ」、「ガブ」、「ムニャムニャ」など、特定の音や動作、感触や感覚などを表現するための言葉(擬音語・擬態語)のこと。
第一の実験の結果、参加者は、動く可食ロボットを観察した際、縦方向に振動するよりも横方向に振動する動作に対して生きているような感覚を強く抱くことがわかったという。また、第二の実験の結果、参加者は、動いていない状態のロボットを食べた条件よりも、動いている状態のロボットを食べた条件において、ロボットに対して知性、感情、生き物らしさ、罪悪感、および新鮮さをより強く知覚することが報告されたとした。さらに、食感をオノマトペで表現した際、条件によって異なる表現が使用された。以上のことから、動いているロボットを食べる際に、特定の印象や感覚を得ることが示されたとする。
今回の研究によって提案される新しい概念「Human-Edible Robot Interaction(HERI)」、つまり人が食べることができるロボットとの相互作用には、大きな可能性が秘められているという。HERIは、動いているロボットを食べる際の印象に関して、異なる文化間での差異を探る機会を提供し、新しい食体験やエンターテイメント性の高い食事の創出へとつながる可能性があるとする。さらに、口腔刺激を通じた脳活動の促進といった医療分野への応用も考えられるとしている。
HERIの研究は、また、人文科学、社会科学、生物学、心理学など、多岐にわたる学際的な研究分野での議論を刺激するという。特に、ヒトの食行動における動物的要素や、動く物体がヒトの食欲や食行動にどのような影響を与えるかという視点が重要とする。生きているように見えるロボットを食べる経験は、食育における哲学的議論を広げ、生命とは何か、ロボットを食べる際に生じる感情やバイオエシックス(生命倫理)に関する理解を深めることになると考えられるとした。
従来のヒト-ロボット間の相互作用研究とは異なり、HERIはロボットを「食べる」という経験を通じて、アンケートでは捉えられないヒトの無意識的に行われるプロセスや、生き物やロボットに対する態度を探る新しいアプローチを提供できる可能性があるとする。このような研究は、今後もさまざまな分野での議論を促し、学際的な研究の発展に貢献することが期待されるとしている。