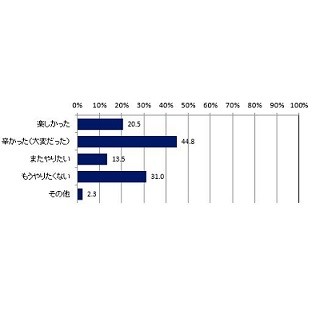フロンティアコンサルティングは1月31日、「ワークステージトレンド2024」に関する調査結果を公表し、記者向けに説明会を開いた。調査の結果から、社会や他者への貢献実感度や貢献の志向度によって、ワーカーが働く環境に対する印象や期待に差が見られたとのことだ。
「ワークステージトレンド」とは
「ワークステージトレンド」とは、同社による造語だ。従来のオフィス空間が表す事業所や事務所の概念を超えて、一人一人のワーカーが輝きながら働ける場として、単なる場所だけでなく、場所と機会を融合させた概念を示す。
ワーカーが働く環境作りにおいては、場所の提供だけでなくさまざまな機会の提供も求められる中で、そのノウハウの蓄積や運営の整備が課題となっている。ワークステージトレンドでは、働く場所を従来のオフィスからワークステージへと昇華するべく、環境作りに関する新たな課題とその解決策を探る。
ワーカーの貢献実感度・志向度に応じた4つのタイプ
今回フロンティアコンサルティングが実施した「オフィスワーカーの働き方に関する市場調査」には、従業員5人以上の企業に勤務するオフィスワーカー、20代から60代の男女2000人が参加した。
調査ではまず、現状の働く環境において社会や他者への貢献を実感しているか、および、今後社会や他者への貢献をより身近に実感したいかを確認。その結果によって、調査対象を4つのグループに分けている。その4グループは以下の通り。
・実感志向型(貢献している実感があり、より身近な実感を希望するワーカー)
・実感非志向型(貢献している実感があり、より身近な実感を希望しないワーカー)
・非実感志向型(貢献している実感がなく、より身近な実感を希望するワーカー)
・非実感非志向型(貢献している実感がなく、より身近な実感も希望しないワーカー)
全体における4グループの割合はそれぞれ、41.6%、7.4%、17.4%、33.8%だ。企業規模別にみると、上場企業とその他(非営利法人や公法人など)で特に実感志向型の割合が高い傾向が見られたという。反対に、非実感非志向型は非上場企業に多かった。
企業の従業員数に応じて規模別に傾向をみると、5000人未満までは企業規模が大きくなるにつれて実感志向型の割合が増加する傾向となった。
フロンティアコンサルティングでデザイン部の部長を務める稲田晋司氏は「上場企業や規模の大きな企業は広範囲でサービスを提供できるようになるほか、CSRや社会貢献活動にも注力できるようになるので、それを社員が実感しやすいのではないか」と分析してみせた。
4グループのストレス状況について質問したところ、実感志向型と実感非志向型はストレスが少ない傾向が見られた。社会や他人への貢献を実感している人ほどストレスを抱えていない人の割合も高くなるようだ。
学習意欲に関する質問からは、「実感志向型」および「非実感志向型」はリスキリングや趣味などを含めて自主的な学習に取り組む意欲が高いことが明らかになっている。
社会貢献を実感・志向している人に共通する特徴は?
現在働く環境について質問すると、社会や他人への貢献の実感があり、今後より貢献の実感を得たい「実感志向型」の人は、勤務先の整備状況が場所、時間、雇用形態のいずれにおいても柔軟性が高い傾向が見られた。
一方、将来的な働く環境の柔軟性に対する意向は、現状の実感度合いにかかわらず、「実感志向型」と「非実感志向型」で高い傾向となった。
続いて、テレワークの実施状況を聞いたところ、特に貢献の志向度が低い「実感非志向型」と「非実感非志向型」でテレワーク率が低い(勤務先への出社頻度が高い)ことが明らかになった。
テレワークの実施に対する意向を聞くと、「非志向型」よりも「志向型」の人の方がテレワークを希望している人の割合が多かった。ただし、テレワーク率が90%または100%を希望した「実感志向型」の人の割合は「非実感非志向型」の半分ほどで、実感度と志向度が高いほど週1日以上の出社を希望していることがうかがえる。
テレワークのメリットに関して、社会や他人への貢献を実感している人は、そうでない人と比べて「社外のコミュニティに参加できる」と回答する人の割合が多かった。また、実感を志向する人ほど、テレワークのデメリットとして「上司や同僚など働く仲間とのコミュニケーションが減る」「相手の状況や様子を確認できずにコミュニケーション効率が下がる」など、コミュニケーションに関連したデメリットを挙げた。
4つのグループがオフィスをどのように認識しているかを質問したところ、志向型は非志向型と比較してオフィスを「チーム作業やコラボレーションを行う場」と捉えており、実感志向型の人は「働く仲間との信頼関係を構築する場」と捉えていた。非実感型や非志向型の人ほどオフィスを「集中して作業を行う場」と捉えているようだ。
働きがいのある環境作りために
休暇中などにリゾートや観光地から一時的にテレワークを行う行為や、通常はオフィスで行う業務やミーティングをあえて場所を変えて行う行為は、「ワーケーション」と呼ばれる。
ワーケーションを経験したことがある人に対し、今後もワーケーションを実施する意欲があるかを質問すると、貢献実感度や志向度が高い人ほど「思う」「やや思う」と回答していた。
ワーケーション未経験者に今後の実施意欲を聞くと、全体的にワーケーション実施意欲はワーケーション経験者よりも低かった。今後ワーケーションをしたいと回答した人の割合は「実感志向型」と「非実感志向型」で多かった。
ワーケーションを希望する理由は、貢献の実感度や志向度が低い人ほど「気分転換になるから」と回答。その一方で、実感度や志向度が高い人は「地域の活性化や貢献につながるから」や「生産性の向上が期待できるから」と回答する人の割合が高かった。
一連の調査結果を受けて、稲田氏は「社会への貢献性が今後の企業価値になっていくだろう。そこに対して意欲のある社員を育てることがますます重要となるはず。貢献の実感や志向が強い人ほど、地域の活性化や生産性の向上をしっかり見据えて活動できることが分かったので、柔軟な制度やワーケーションなどを活用しながら実感志向型の社員を育てていくのがよいのでは」とコメントした。