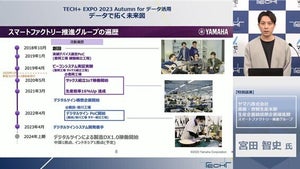ガートナージャパンは11月13日~15日「Gartner IT Symposium/Xpo 2023」を開催した。ゲスト基調講演には慶應義塾大学 医学部 医療政策・管理学教室 教授の宮田裕章氏が登壇。「デジタル革命の先にある新しい社会」と題して、デジタル化が進んだ社会がどのように進化していくのか、そこで企業はどのように在ることが求められるのかについて語った。
世界に取り残された日本の現在地
宮田氏は冒頭、これまで人類が社会を形成してきた歴史に言及した。同氏によれば、「“Society 4.0”の段階で、日本は情報技術をうまく使いこなせなかった」という。4.0においては、化石燃料を扱う企業よりもGAFAM(Google, Apple, Facebook(現:Meta), Microsoft)のようなデータを扱う企業が価値を高めることになった。同氏は複数のデータを引用し、経済成長において日本が海外に差をつけられてしまったことを示す。
「日本は旧来から行き渡ったインフラや方法論から離れづらかった、というメンタリティ的な側面もあると思います。何より技術の流れに乗れなかったことが“失われた30年”を作ってしまった原因かも知れません」(宮田氏)
世界的なビジネスの潮流を宮田氏はどう見る?
「この先の時代では、デジタルで未来を描くことが重要になります」(宮田氏)
宮田氏曰く、デジタルの発展によって、これまでは見えてこなかった社会問題などが可視化され、目を背けられないものになっているという。
例えば、米国から広がった人種差別抗議のスローガン「Black Lives Matter」や、ウイグル自治区で行われていた強制労働による問題なども、今の時代だからこそ浮き彫りになった側面もあるというわけだ。
「今までのビジネスは短期の利潤を追求するものでした。しかし、デジタルによって可視化された社会では、サステナビリティに配慮できていない企業はすぐに浮き彫りになります。悪評が広まってビジネスはうまくいきません」(宮田氏)
労働者における企業選びにおいても、企業が労働者を選んで採用するわけではなく、労働者が企業のことを見定めて選ぶ時代に突入しているという。つまり、「労働者が働くに値するような社会貢献ができているか」が企業選びの重要な要素になっているのである。
いかにデジタルで未来を描くか
宮田氏は改めて「デジタルで未来を描く」ことの重要性を強調する。
「技術の発展によって、これまで物理法則的には実現しなかった多様な繋がりが生まれています。そうした中で、どのように現在と未来をつなげていくのかがデジタルの重要な役割になります」(宮田氏)
ここで宮田氏が人々のWell-being実現にデジタルを有効活用している事例として紹介したのは、中国の生命保険会社が提供しているアプリだ。
同アプリでは、オンライン問診やサプリ・処方薬のEC機能だけではなく、健康に関するさまざまな情報が提供されている。いざ、病気の疑いが出た際には、適切な医者の紹介やカウンセリングもアプリ上で提供されるという。利用者の身体に病気が見つかってから活躍するイメージが強い保険事業者が、日ごろから利用者の健康増進に目を向けていく。これは、デジタルがあってこそ生まれたビジネスモデルと言えるだろう。
また同氏は、今後の社会におけるデジタル活用のヒントとして、データや資源の共有を挙げた。これまでは、「共に生きる」という概念がなかなか成立せず、綺麗ごとに終始しがちだったが、現在はデータや資源を容易にシェアできる時代になった。ただし、「それらを有効活用するには、一つの分野だけではなく複数分野で共有していくことがカギとなる」と宮田氏は説明する。そこで重要なキーワードとなるのが「Co-Innovation-Ecosystem」だ。
「食習慣一つを例にとっても、食べることで健康にも影響を及ぼしますし、その食べ物がどこで誰に作られたか、といったことも可視化される時代になっていきます。他の領域に関しても、多様な軸の中で未来は作られていきます」(宮田氏)
世界は可視化され、繋がっていく。これを前提として、働くこと、生きることに一人一人の行動が影響を与えていると同氏は話す。だからこそ、「Well-beingなどを意識しながら、社会にも目を向けていく2つの要素のバランスが必要」なのだと語り、講演を締めくくった。