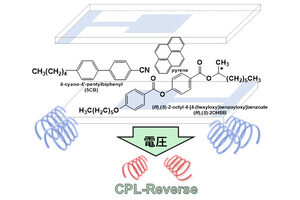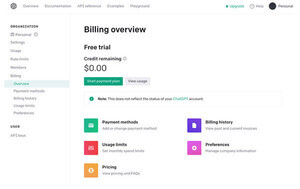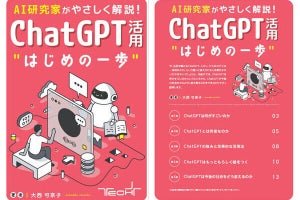昨今、さまざまなデジタルサービスに生成AIが組み込まれ、業務にAIを活用することも珍しくなくなってきた。そうなると注目されるのがAIスキルを持つAI人材だ。実際のところ、AI人材採用はどれほど活発化しているのだろうか。また、AIスキル以外にどのようなスキルが求められているのだろうか。
LinkedIn社は2023年8月、ビジネス特化型SNS「LinkedIn」の登録者を対象に、AIに関するスキルの動向について分析するグローバル調査「The Global Future of Work Report: State of AI@Work」を実施した。今回、その調査結果を踏まえ、同社APAC(アジア太平洋地域) ヘッドエコノミストであるペイ・イング(Pei Ying)氏に、AIの台頭が採用市場に与えた影響とAI人材採用の現状について聞いた。
日本におけるAI人材の採用状況
本題に入る前に「AI人材」の定義について確認しておきたい。
LinkedIn社が定義するAI人材とは、「AI関連職種として採用された人材」、または「1つ以上のAIスキル(機械学習やディープラーニングなど、AIに関するスキル)を有する人材」のことだ。AIスキルを持つエンジニアはもちろんAI人材だが、仮にAIスキルを持っていなくても、データサイエンティストやAI関連のプロダクトマネージャーといった職種であればAI人材と見なす。
また、同社では特定のスキルと一緒に使われることの多いスキルを「隣接スキル」として設定している。例えば、AIスキルの隣接スキルとしては「マーケティング業務におけるチャットボットの最適化」などが挙げられる。同社の定義では隣接スキルだけ持っていてもAI人材には分類されないが、導入したAIを実際に活用するのは現場であるため、隣接スキルを持つ人材は今後の企業において重要な位置付けになるだろう。
これらの点を踏まえた上で、LinkedIn社の調査を見ていこう。
まずAPAC各国における2023年のAI人材採用数は、2016年の同調査時と比べて大きく上昇している。例えばインドネシアでは20%増、シンガポール14%増、オーストラリア12%増といった具合だ。
なお、唯一インドだけは6%減となっているが、これはイング氏曰く「インドは2022年のAI人材採用数がとりわけ多かったため、その反動で下がっているのでは」とのこと。減少幅も大きくはないので、2023年のインドは例外と言えそうだ。
このようにAI人材採用を強化しているAPAC各国だが、中でも最も伸びを見せているのが実は日本である。日本のAI人材採用は2016年と比べると24%も増加しており、企業がAIに注目していることが見て取れる。また、調査によると経営層の多くは採用の強化だけでなく、従業員にAIスキルを習得させるためのスキルアップの方法を模索しているという。
なぜ日本企業は、APACの中でもAI人材の採用や育成に積極的なのか。
「日本は少子高齢化が進んでおり、人材採用がなかなかうまくいかない状況です。そこで効率化や生産性向上のためにAIを活用していこうと考えている企業が多いのだと思います。また、日本政府はAIを推進する方針を掲げてデジタル化を進めています。政府、そして企業のリーダーがAIに対して積極的だからこそ、日本は他国よりもAI人材の採用が進んでいるのではないでしょうか」(イング氏)
AIの活用が広がるほど、より重要性が増すスキルとは?
今後、あらゆる業種で現場へのAI導入が進んでいくのはもはや間違いない。その過程においては、多くの人が「業務そのものも変化する可能性が高い」と予想していることが調査からもうかがえる。例えば営業職では、全体の69%が「これから半年間で自分の仕事にAIを使う頻度が上がるだろう」と回答しているのだ。
さらに、イング氏は「当社では、AIや生成AIの影響により、2015年から2030年までの間に必要とされるスキルが65%変化すると予想しています」と語る。
より重要性が増すと予想されているのは、創造性や問題解決力、コミュニケーション能力、柔軟性、倫理観といった人間らしさを示す“ソフトスキル”だ。LinkedIn社の調査によると、オーストラリアの経営層の74%、インドの経営層の71%が「AIスキルよりもソフトスキルの方が組織にとって価値がある」と回答しており、日本を対象とした調査でも、今後AI活用が広がる中で最も重視するスキルとして「コミュニケーションスキル」が上がっている
経営層がソフトスキルを重視する理由は、それが今のところAIで代替できない部分だからだ。昨今ブームになっている生成AIは、ソフトスキルに近い能力を一定程度備えているが、まだ人間の代わりにはならない。生成AIでコミュニケーション用のテキストを作らせることはできるが、相手によって話す声のトーンを変えたり、ボディランゲージを駆使したりできるのは人間の特権だ。AIは「できること」であれば人間よりもはるかに高い能力を持つが、「できないこと」については人間には全く及ばないのである。
「AIの活用が広がるほど、人間だけが持つソフトスキルの価値は高まっていくでしょう」とイング氏は予測する。
AIは「仕事を奪う」のではなく、「仕事を変化させる」
以前から、「AIが人の仕事を奪う」可能性についてはそこかしこで議論されてきた。少し前であれば、単純作業はAIに取って代わられるが、クリエイティブな仕事はAIにはできないと見なされていた。それが生成AIの登場以降、「クリエイティブな仕事であってもAIに取って代わられるのではないか」といった論が有力になっている。
しかし、今回のLinkedIn社の調査とイング氏の話を考え合わせると、「AIは仕事を奪うのではなく、仕事を変化させる」と言った方が適切なのではと思わされる。AIは完璧ではなく、仕事に対する責任もとらない。そうであるならば、仮に単純作業をAIに任せるようになったとしても、少なくとも人間には「AIの間違いをチェックし、AIの結果に責任を持つ」といった新たな仕事が生まれるはずだからだ。もっとも、単純作業を人が手で行っていた時代に比べると、全体の業務効率は圧倒的に向上するだろう。
「AIはあくまでもツールです。人が行っていた仕事のうち、AIが得意とする部分は任せてしまう。それで生まれた時間を、人にしかできない仕事に使うことで、より効率的な仕事ができるでしょう」(イング氏)
例えば、LinkedIn社は2023年10月、同社が提供するeラーニングプラットフォーム「LinkedInラーニング」に、一部地域から順に「LinkedIn Learning's AI-powered coaching」の導入を始めると発表した。これは、同社のインストラクターの知見を基に開発された生成AIを用いて、キャリアに関するフィードバックを提供する機能だ。また合わせて、AIが優秀な候補者を推薦する採用サポート機能「Recruiter 2024」の段階的な提供を開始したことも発表している。膨大な過去データを基に最善を予測するのはAIの得意とするところであり、人はその予測結果を見て判断し、生かすことに集中できるというわけだ。
* * *
LinkedIn社の調査では、日本を含むアジア太平洋地域でAIスキルやAI人材のニーズが大きく高まっていることが裏付けられた。今後、生成AIをはじめAIの活用が進めば、ビジネスプロセスや業務内容が大きく変化することはほぼ間違いないだろう。それに伴い、経営層の多くが、AIを活用する現場の人々のソフトスキルに注目している。
いわゆるAI人材を目指すなら、当然AI関連スキルの習熟が求められる。だが、AI活用が急速に広がりつつある今、キャリア形成においてはこれまで以上にソフトスキルが重要になっていくのかもしれない。