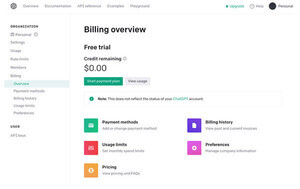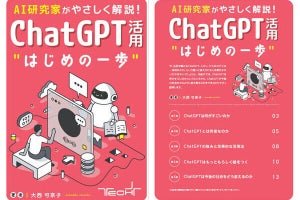急速に進化を続けるAIをどのように活用していくのかが議論を呼んでいる。現状はまだ手探りだが、少しずつ具体的な活用法も見え始めているようだ。そんな中で注目を集めるのが、自治体によるAI活用である。最近では、横須賀市がいち早くChatGPTの活用実証を行ったことで話題となった。
はたして、AIの活用で行政や市民サービスはどう変わるのか。官民の連携をどのように進めていけばいいのか。10月24日に開催されたnote主催のイベントでは、「自治体・企業・政策の課題を解決するAI活用」をテーマにパネルディスカッションが行われた。本稿では、その内容を基にAI活用の現状と将来を考えていく。
横須賀市で行われたChatGPT活用実証の成果
登壇したのは、デジタル庁 デジタル社会共通機能グループ グループ長 楠正憲氏、Govtech協会 代表理事/PoliPoli 代表 伊藤和真氏、横須賀市経営企画部 デジタル・ガバメント推進室長 寒川孝之氏、note CXO 深津貴之氏だ。
noteは横須賀市とも連携しており、地方自治体の生成AI活用の知見をまとめた「自治体AI活用マガジン」を運営するなど、AI活用について積極的な動きを見せている。同社でCXOを務める深津氏も横須賀市のAI活用に関わっており、すでに官民連携の取り組みは始まっていると言える。
では、具体的に横須賀市ではどのようにAI――ChatGPTを活用しているのか。
横須賀市が発表した活用実証の結果報告によると、約半数の職員が実際にChatGPTを活用。最終アンケートに回答した職員のうち、約8割が「仕事の効率が上がる」「利用を継続したい」と回答するなどポジティブな結果が得られたという。
一方で、ChatGPTの利用用途に向かない「検索用途」での利用が約3割あったり、不適切な回答が返ってくるケースが見られたりもしたとのことだ。
この点について深津氏は、「ChatGPTをGoogleの代わりに使う人が多いが、それは適切ではない」と指摘する。
「ヒアリングする際の質問票を作ったり、作成した資料のレビューをさせて壁打ちしたりする(のがお薦めの使い方)。いきなり『◯◯は何?』と質問するのではなく、どこにChatGPTを使うと自分の業務が楽になるのかを考えるべきなのです」(深津氏)
さらに深津氏は、ChatGPTを使いこなすコツとして「プロンプト(質問文)から入るのではなく、業務フローから入るべき」と説明する。
ChatGPTは何かしら自然言語を入力すると、それに対して答え(のようなもの)を返してくれる。その精度が高いため、どうしても「質問に答えてくれるAI」と捉えられがちで、プロンプトが注目される傾向にある。
しかし、それでは単なるGoogle検索と変わらない。ChatGPTで仕事を楽にするのであれば、先に“業務フローのどこにChatGPTが活用できるのか”を考えるべきなのだ。
こうした深津氏のアドバイスを基に行われた横須賀市のChatGPT活用は一定の成果を上げ、全国的に話題となった。ニュースが出た後は、全国の自治体からChatGPT活用に関する問い合わせが殺到したという。
寒川氏は、「あまりにも電話が鳴りっぱなしだったため、チームメンバーがChatGPTの取り組みについて対応するチャットボットを作ってくれました」と笑顔で当時を振り返った。
政府におけるAIへの対応の流れ
では、自治体に対して政府の動きはどうか。
楠氏によると、デジタル庁におけるAIへの対応の流れは次の通りだ。
まず、2023年2月に自民党AI PTが発足。4月にはOpenAIのサム・アルトマン(Samuel Harris Altman)氏が来日し、岸田総理と面会を行った。その2週間後にはAI戦略チームが発足し、ワークショップなどを実施。10月18日には、行政における生成AIの適切な利活用に向けた技術検証の環境整備に関する企画競争調達公示が行われている。
「ルールができるまで(ChatGPTの利用を)禁止すべきではないかという議論も一瞬出てきて、これはまずいと思いました。そこで、今までのルールで統制はできるということを申合せして、検証環境の構築やワークショップの実施をしました」(楠氏)
中でも苦しんだのは、プロンプトの扱いだったという。というのも、ChatGPTにプロンプトとして機密情報を入力することはセキュリティ上できないからだ。しかし、行政文書を入力できないとなると、行政におけるChatGPT活用の意味が薄れてしまう。
そこで、9月15日に「機密性2」にあたる情報をプロンプトとして扱えるよう、ガイドラインの改訂が行われた。この点は、今後の政府および自治体におけるAI活用において重要なポイントになっていきそうだ。
「まだまだ(生成AIは)危なっかしい道具でもあるので、ルール整備も進めなければならないし、データ整備も含めて国としてやることはたくさんあります」(楠氏)
官民の協力で行政サービスを革新する「Govtech」
一方で、民間の動きはどうなっているのか。
注目したいのが、パネルディスカッションに登壇した伊藤氏が代表理事を務めるGovtech協会だ。
伊藤氏によると、「Govtech」とは「Govemment」と「Technology」をかけ合わせた造語であり、「官民の共創により、行政の非効率を改善し、国民にとってより一層ユーザーフレンドリーな公共・行政サービスを持続可能な形で提供できるテクノロジーやサービス」を指すという。
例えば、オンライン行政手続きを行えるサービスや、住民向けのデジタルサービスなどが民間企業から多数生まれているが、こうしたサービスがGovtechである。
特にAI領域に関するGovtechについては、「これから開拓していくフェーズ」だと伊藤氏は言う。
「政府のデータをいかに使いやすくしてもらえるかが重要です。データをオープン化することで使いやすくなり、Govtechが盛り上がっていくでしょう」(伊藤氏)
ChatGPT活用が話題になったこともあるのかもしれないが、横須賀市に対してもすでに民間企業からアプローチがあると寒川氏は言う。
「民間企業からご提案をいただき、例えば相談内容を生成AIで要約するなどの試みを行っています」(寒川氏)
イベントの最後には、参加者から「ChatGPTの成果物を公開する際のチェックは、個人のモラルに依存するのか、組織としてチェックする体制を整えているのか」という質問があった。
これに対して楠氏は、「ウォーターマークが入る画像生成AIもあるが、一方でGoogle Colabで動かした場合はマークが入らなくなってしまう。そうした問題に対しては、ルールを整備することが重要になる」と指摘。「まさに今、官民で議論しているところ」と述べた。
楠氏が言うように、生成AIの生成物に関する権利問題などのトラブルは未だ結論が出ていない状態だ。横須賀市では、「ChatGPTが生成したものをそのまま使うと問題になる可能性があるので、必ず職員の目で確認するようにしている」(寒川氏)とのことで、やはり現状は人によるチェックが欠かせないようだ。
ただ、こうした懸念については何もAIだけの問題ではないと楠氏は言う。
「生成AIは人の脳を模倣しているため、人間でも同じトラブルは起きる可能性があります。ですから、人間に対しても同じようなリスクマネジメントは必要なのです。そもそも仕事に責任を持って取り組んでいれば、すでにやっていることなのではないでしょうか」(楠氏)
一方で、深津氏はそれほど心配はしていないという。
「短期的には問題になるかもしれませんが、長期的には(生成AIを使うことは)辞書や計算機を使うのと近いところに着地すると思います。一方で、安全保障やセキュリティを考える場合は、(生成されたものが)どのAIのデータセットに誘導されたのかを検証する必要も出てくるでしょう」(深津氏)
さまざまな課題や懸念を抱えつつも、政府や自治体における生成AIの活用は着実に進んでいる。生成AIに関するガイドラインの策定や活用実証など、本格的なAI活用に取り組む土台は整い始めているのではないだろうか。欧米諸国に比べて遅れを指摘されることもある日本のAI活用だが、今後の躍進を期待したい。