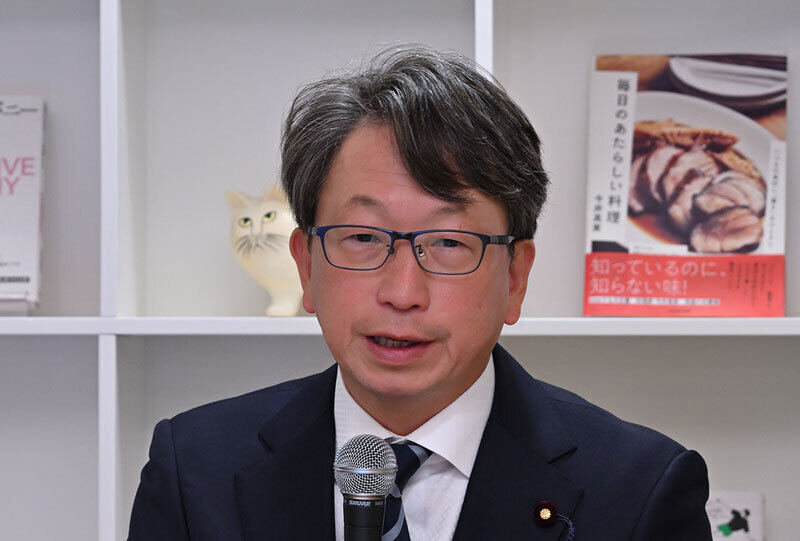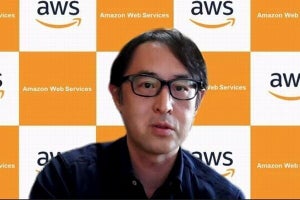昨年から一大ムーブメントとなっている生成AI。企業だけでなく、自治体なども生成AIの活用に乗り出している。そうした状況を後押しするのが、日本政府が打ち出すAI戦略だ。
その中心にいる議員の1人が衆議院議員 自民党AIPT座長 平将明氏。ChatGPT公開のわずか半年後には自民党デジタル社会推進本部「AIの進化と実装に関するプロジェクトチーム」座長として「AIホワイトペーパー ~AI新時代における日本の国家戦略~」を公表するなど、積極的に動いている。
そんな平氏が、10月24日に開催されたnote主催のイベント「生成AIはこう使う! 自治体・企業・政策の課題を解決するAI活用」に登壇。「日本の発展のために行政・民間でどのようにAIを活用していくか」をテーマに講演を行った。
日本政府が取り組むAI関連政策とは
ChatGPTが公開され話題となったのは2022年11月のことだ。突如訪れた生成AIブームは世界中を飲み込み、大きなうねりとなっていった。こうした波にいち早く乗ったのが日本政府である。ChatGPT公開からわずか半年後の2023年3月30日には「AIホワイトペーパー ~AI新時代における日本の国家戦略~」を公表し、AI活用における基本指針を策定した。
同ホワイトペーパーをまとめたのは、自民党デジタル社会推進本部「AIの進化と実装に関するプロジェクトチーム」。その座長を務めるのが平氏である。
もともと同チームは、科学技術基本計画について調査・検討を行うことを目的に設置された科学技術イノベーション政策推進専門調査会から、平氏がAI領域を引き取るかたちで誕生したものだ。平氏によると、「最先端のメンバーがサイバー空間でつながっており、(AI関係の)事象があると瞬時にやりとりを行うため、24時間以内に最新の情報がつかめる」のだという。
通常、AIに関する政策をとりまとめるためには長い時間がかかる。なぜなら、AIは複数の行政組織を横断する事案だからだ。そこを平氏をはじめとする政治家が主導することで、政策や戦略のスピーディーな策定を可能にしたのである。
なぜ平氏はそれほどまでにAIへの対処を急ぐのか。その背景にはAI領域に関する危機感がある。
「日本は正直、AIに関して遅れています。OpenAIに続いてメタからはLlama 2など、どんどんLLM(大規模言語モデル)が出てきていますが、海外のビッグテックに任せてばかりだと安全保障上も問題があります。なぜなら、ファウンデーションモデル(基盤モデル)は中がどうなっているかわからないからです」(平氏)
そこで日本政府は、国内におけるファウンデーションモデル開発の支援に乗り出している。具体的にはCPUやGPUといった計算資源の強化、そしてデータセットの支援だ。
「(海外製のLLMでは)英語なら的確な答えが出せるのに、日本語だとうまくいかないなどのバイアス問題があります。そこで日本語のデータをできるだけ提供することで、バイアス問題を解決しようと考えています。OpenAIのアルトマンCEOとも同じ話になり、協力を約束してくれました」(平氏)
さらに、スタートアップ支援についても進めていくという。2023年5月、日本政府は「グローバル・スタートアップ・キャンパス」を東京に創設することを表明。世界から若手研究者を招聘し、スタートアップの創出へ向けて様々な取り組みを行う計画だ。
ファウンデーションモデルを“使い倒す”
前述したように日本独自のファウンデーションモデルの研究は進めなくてはならない。一方で、これから海外のビッグテックに追いつくのは難しいのが現状だ。
そこで、日本国としては「ファウンデーションモデルを使い倒す」ことを基本的な立場として考えていくと平氏は言う。
「リスクはありますが、しっかりと管理した上で徹底的に使うというのが日本の基本姿勢です。この基本姿勢は国によって違いがあり、EU諸国は規制ありき、アメリカはファウンデーションモデルが“悪さ”をしないように管理・監督しながらガイドラインを作っています」(平氏)
AIにより起きる可能性のある法的問題。この点について日本はどう向き合うのか。平氏は「AIに関しても既存の法律で対応できる」と考えている。
もちろん、AI時代に備えて法律を変えていくことも必要だが、それはすでにデジタル化の流れの中で行ってきた経緯があり、同じ手法が使えるはずだ。また、あくまでもアイデア段階だが、ファウンデーションモデルとスペシフィック(特定用途)モデルをかけ合わせることで「AI法制局」のような仕組みを作り、最終的にはAIが自動的に条文を最適化してくれるところまで持っていきたいと平氏は語った。
「法律をスピーディーに変えられなかったことで、“失われた30年”になってしまいました。AI法制局なら(法改正にも)アジャイルに対応できます」(平氏)
さらに重要なのは、政府がハードロー(法的な強制力)で進めるのではなく、民間団体をつくり監査するなどのソフトローで進めることだと平氏は言う。
「DFFT(Data Free Flow with Trust:信頼性のある自由なデータ流通)を打ち出したとおり、日本は日本の価値観に基づいて進めていきます。ゆるいレギュレーションの下、スタートアップに資金があるようにすべきだと私は考えています」(平氏)
AI領域における日本の“勝ち筋”は?
平氏は「政府AI」という構想も持っている。これは、政府共通のクラウドサービス利用環境「ガバメントクラウド」に関連して稼働する政府主導のAIである。
政府AIで考えられる活用法は主に2つある。
まず、行政の問い合わせ窓口だ。都や区を問わず、24時間対応可能な問い合わせ用にAIを活用。さらに政策立案や政府答弁などでも活用する構想もあるという。
もう1つがロボティクスにおける活用だ。平氏によると、もともと個別最適化されたAI活用については日本は強みを持っており、またロボティクス領域も日本の得意とするところだという。
従来のAIと生成AIをかけあわせ、自分たちのフィールドで勝負することが、AI分野における日本の勝ち筋だと平氏は見ているのだ。
こうした動きを加速させるのが政府の推進するデジタルマーケットプレイスである。これは、デジタル庁とあらかじめ契約した事業者がデジタルサービスをカタログサイトに登録し、そこから行政機関が最適なサービスを選んで個別契約する仕組みだ。
この取り組みは、特にこれまで行政への参入が難しかったスタートアップに大きな恩恵をもたらすものであり、AI分野においても大きな期待が寄せられている。
平氏は最後に「社会にAIとの共存を臨む雰囲気があるか、怖いと感じる雰囲気があるか(に分かれる)。ヨーロッパなどは“ターミネーター”的なイメージを強く持っており(AIを怖がる雰囲気があるが)、日本は“ドラえもん”の国。だからこそAIと共生していけるはず」と述べ、AI分野における日本の持つ可能性を強調した。
平氏が語ったように、これから世界がAI時代を迎えるにあたって日本の動きはこれまでになく早いように感じる。ファウンデーションモデル開発で世界のビッグテックに遅れを取っているのは事実だが、ロボティクスをはじめとする別領域との組み合わせなど、日本らしいAI戦略で勝負すべきだろう。