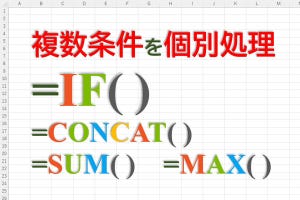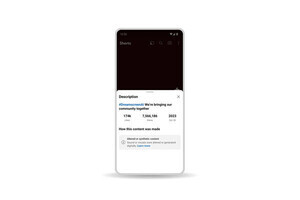さまざまなシチュエーションにおいて、何かを「待つ」時間は発生する。特に、人気のレジャー施設や話題の飲食店、世界的芸術家の展示会など、多くの人が足を運びたくなる場所では待ち時間が生まれることが多い。終わってみると、楽しみにしていた体験よりも待ち時間の方が長くストレスフルだった、なんてこともあるはずだ。
体験自体の印象をより良いものにするためにも、待ち時間をただ悶々と過ごすのではなくもっと有意義に使うことはできないのだろうか。
そんな待ち時間の課題をデジタルで解決するものとしてリクルートが提供するのが、受付・順番待ち管理システム・アプリ「Airウェイト」だ。同社、SaaS領域プロダクトマネジメント室 Airプロダクトマネジメントユニット AirプロダクトマネジメントグループでAirウェイトを担当する蔦田慎史氏は「ウチのオカンでも使えるシンプルさ」だと同アプリについて語る。
なぜ、それほどシンプルなアプリが、これまで解決できていなかった待ち時間の課題を解決できるというのか。蔦田氏にその理由を聞いた。
「待ち時間」は周辺の環境にも悪影響を与える
蔦田氏曰く、Airウェイトを導入しているのは、飲食店のほか、ホテル、美術館などの施設運営をする企業がほとんどだそう。また、直近では物流業者や病院などへの導入も増えているという。
導入前の企業の課題に共通していることは、来客の待ち時間だけではない。来客がその場で待ち、滞留していることが原因で起きる周辺環境の悪化も顕著な課題だ。
例えば、人気観光施設の入り口に数十メートルの行列ができた場合、敷地外のエリアまで列が及ぶことがある。その際、待っている人のおしゃべりの声がうるさかったり、ゴミのポイ捨てがあったりと、近隣の住民にまで迷惑をかけてしまうケースが後を絶たないそうだ。施設としても、本来接客や施設運営を持ち場にしているはずのスタッフのリソースを、一時的にとは言え整列やクレーム対応に奪われてしまうのは不本意だ。
「導入前の企業さまからは、(整列作業によって)ただでさえスタッフの業務効率が悪くなってしまっているのに、さらにお客さまからクレームを受けてしまうことも多いと聞きます。エンゲージメントへも悪影響があり、担当者の方もかなり困っているようですね」(蔦田氏)
特定の観光スポットでの滞留や周辺での“たむろ”などからは、オーバーツーリズム問題が発生するケースもあり、現場だけの課題ではないようだ。
蔦田氏は「観光地が作りたい世界観を作れなくなってしまう」と、待ち時間を起点とした悪影響への懸念を示した。
「シンプルで使いやすい」を追求し、課題解決をサポート
こうした課題に対して、シンプルなUI・UXでメスを入れられることがAirウェイトの何よりの強味だと蔦田氏は語る。
同アプリでは、「受付する」ボタンを1タップすると「レシート」が発行される。そこに印字されたQRコードにアクセスすれば、リアルタイムで待ち時間を把握できるため、利用者は自分の順番が近づくまで他の場所に行くことも可能だ。一時帰宅してひと休みすらできるかもしれない。それならば、長い待ち時間であっても、ただ並んで待つだけの時間はほとんど0にできる。
一方、導入側は、iPadとレシートプリンターがあれば、専用の受付アプリケーションをダウンロードするだけですぐに利用を開始できる。これまでスタッフの肌感覚や目視によるカウントで算出されていた待ち人数や来場数などのデータが可視化されることもメリットだ。
Airウェイトでは、2014年に作られた初期モデルからユーザーテストを入念に行い、常に「シンプルで使いやすい」を追求してきたそうだ。
「かなり古くからアプリを作っているので、当時から導入していただいている企業さまとも必要機能についてディスカッションしてきました。企業さまから挙がった課題を、リクルート側で議論していくプロセスもすでに定着しています。長年積み重ねてきた“一日の長”がありますね」(蔦田氏)
先ほど例に挙げたような観光地での導入は、待ち時間を解消することで他のスポットへの送客増も期待できる。蔦田氏は「待ち時間で数時間も費やしてしまうもったいなさを解消できる」とし、目指す理想像についても語ってくれた。
「将来的には、観光地全体の待ち時間マップのようなアプリを作ってみたいです。自治体のデジタル化には町おこしが紐付くケースも多いので、観光客の方に喜んでもらえるような体験づくりをお手伝いしたいですね」(蔦田氏)
「やりたいことができるように」簡単に始められるデジタル化
導入側では、来訪者の待ち時間を管理することで導入側が求める施設やイベントの雰囲気づくりや、スタッフの業務効率化につなげることができる。
蔦田氏は「本来やりたいことがやれるようになって欲しい」と、導入企業への思いを語る。
「企業さまの中にはデジタル化を『小難しいシステマティックなことをやらなくてはいけないのか……』と気後れして、ついつい放置してしまう方も少なくありません。それに対して、『今日すぐにできる』というくらいの温度感で始められるのがAirウェイトの持ち味です。その感覚が広く伝わればと思います」(蔦田氏)