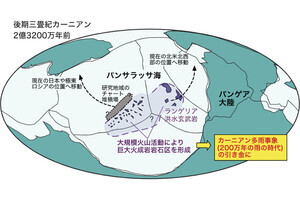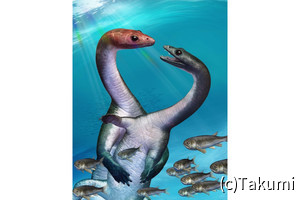北海道大学(北大)は11月17日、2016年に北大などが発見した約7000万年前(白亜紀後期)のモンゴルに生息していた恐竜「アルバレッツサウルス類」(以下、AS類)のほぼ完全な全身骨格を詳細に分析した結果、新属新種であることが判明し「ヤキュリニクス・ヤルウイ」(Jaculinykus yaruui)と命名したことを発表した。
同成果は、北大大学院 理学院の久保孝太大学院生、北大 総合博物館の小林快次教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米オンライン科学誌「PLOS ONE」に掲載された。
AS類は、主にモンゴル、ほかに中国とアルゼンチンの白亜紀の地層から発見されている恐竜で、獣脚類「マニラプトル類」に属し、1本指で非常に短い前肢と鳥のような特徴を多く備えた非常に奇妙なグループとされる。また獣脚類の仲間では、鳥類につながる系統とは独立して、全長が1m以下になるまで著しく小型化したという進化的な特徴を持つ。しかし華奢で小さいが故に、これまでの化石記録の多くはとても断片的で、系統関係や生態復元の基礎である解剖学的情報が限られていたという。
そうした中、2016年8月にモンゴル・ゴビ砂漠南西部のネメグトにて、北大とモンゴル古生物・地質研究機関による合同調査で発掘されたのが、これまでで最も保存状態の優れた進化型AS類の全身骨格化石だ。そこで研究チームは今回、同化石を用いてAS類の包括的な解剖学的記載、その進化史を復元するための系統学的解析、そして保存されていた姿勢を記載した上での生態学的解釈を行ったとする。その結果、以下の固有の特徴から新属新種であることが判明したとしている。
- 背腹方向に高い鼻口部のある前上顎骨
- 頭頂骨にある内側にカーブしたparasagittal crest
- 腹側から見て湾曲の弱い、直線的な下顎骨
- 手根中手骨にある大きく発達した内側突起
- 大腿骨の遠位部にある外側突起の発達
- 脛骨の近位部にある内側突起の大きな発達
今回発見された新属新種は、小柄でとても長い後肢とよく発達した爪から、「素早く小さな竜の爪」という意味の「ヤキュリニクス・ヤルウイ」と命名された。「Jaculus」はギリシャ神話に出てくる小さな竜の名前、「onykus」はラテン語で“爪”を意味し、種小名の「yaruui」は“素早い”を意味するモンゴル語「яаруу」に由来しているという。
そして研究チームは、ほかのAS類とどのような系統関係なのかを調べるため、新種のヤキュリニクスを含めた118分類群と596個の特徴を用いた系統解析を行った。その結果ヤキュリニクスは、派生的(進化型)なAS類「パルヴィカーソル亜科」であり、ネメグト盆地から産出したAS類のほかの仲間「シュヴウイア」と単系統を形成していたことが判明したとのこと。なおヤキュリニクスは、ほかの進化型AS類と共通する特徴に加え、シュヴウイアと共通する特徴も確認されたという。
また、数多くの進化型AS類が生息していたネメグト盆地は、乾燥した環境と湿潤な環境、またそれらが入り交じる環境が分布していたと考えられ、系統関係から、彼らは湿潤な環境から乾燥した環境に適応・多様化していったことがわかったとする。
さらにAS類の特異な特徴として、機能する手指が第1指(親指)のみという手骨格の特殊化がある。これまで、原始的なAS類「バンニクス」から進化型のシュヴウイアにかけて、発達した第1指に対して第2指・第3指が著しく退縮し、さらに中国で見つかった「リンヘニクス」では、第2指・第3指が完全に消失した1本指の手骨格が知られていた。それに対しヤキュリニクスの手骨格は、大きく発達した第1指と非常に退縮した第2指からなる2指性が化石からわかり、特殊化の過程における中間的な状態であることが確認されたとしている。
それに加えてヤキュリニクスは、骨格要素の多くが関節した状態で、なおかつ頭部は胴体に埋めるような状態で、長い頚部や尾部は湾曲して胴体を包み、また後肢は座るように畳まれた姿勢で保存されていた。これらの事実から、ヤキュリニクスは死亡時に急速に埋没され、捕食者や分解者による分解作用を免れ、死亡時の姿勢のまま保存されたと推測されたという。
この姿勢は、鳥類が見せる休眠姿勢(体温低下防止のための体温調節行動とされる)に非常に類似しており、これまでの化石では鳥類に近縁な恐竜「トロオドン類」のごく少数の標本でのみ知られていたが、今回の発見により、鳥類の休眠行動の起源は原始的なマニラプトル類恐竜まで遡ることが示されたとする。
ヤキュリニクスは、AS類の詳細な解剖学的情報を解明すると同時に、鳥類のような特性(特徴や行動)が、鳥類に分岐する以前の恐竜類の間で、広く分布・進化が進んでいたということを強調しているという。研究チームは今後も、モンゴル産の新たな化石が追加されることにより、恐竜から鳥類への進化過程やその背景の理解が進むことが期待されるとしている。