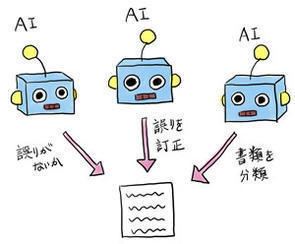ChatGPTやStable Diffusionといった生成AIの話題が本格的に盛り上がり始めてから約1年。そのビジネス活用における可能性が大きな注目を集めていることは、言うまでもない。だが、多くの企業はまだ方向性を模索する段階にあるというのが実情だろう。
そうした中で2023年4月、DMMから20億円の投資を受けて設立されたのが生成AIサービス事業を展開するAlgomaticだ。同社を率いる代表取締役 CEO 大野峻典氏は、東京大学にて深層学習を用いた研究プロジェクトに従事した後、2018年にAIソリューションを展開するAlgoageを創業、2020年にDMMグループにM&Aでジョインした経歴を持つ“エンジニア経営者”である。
すでにAlgoageを経営する立場にありながら、なぜ大野氏はこのタイミングで新たに生成AIを扱う会社を設立したのか。設立翌月に提供を開始した「シゴラクAI」とはどのようなサービスなのか。Algomatic設立の背景と、大野氏が見据える今後のビジョンについて聞いた。
新市場へ先行することには大きなメリットがある
――2023年の4月に、大規模言語モデルなどの生成AI技術を活用したサービスの開発・提供を行うAlgomaticを創業されました。いち早く生成AI領域に特化して起業された理由を教えてください。
大野氏:一言で言えば、将来生まれるだろう生成AI市場で勝つためです。私は2018年に機械学習・深層学習を用いたソリューション開発を行う企業としてAlgoageを創業し、その後M&AによってDMMグループへジョインしました。Algoageでは主にチャットボット事業を展開していたのですが、そこにとどまるのではなく、何か爆発的に成長できるような事業を作っていきたいとずっと考えていました。
そんなときに世の中で話題になり始めたのが生成AIです。これまでにも文章や画像を生成するAIはあったのですが、その精度が一気に上がるきっかけとなったのが2022年に登場した画像生成AIのStable Diffusionと、文章生成AIのChatGPTでした。
その進化を目の当たりにしたとき、これはチャンスなのではと思いました。今後、必ず生成AI領域で新しい成長事業が生まれるはずだと確信したのです。
その段階で具体的なサービスのイメージを持っていたわけではありません。ただ、こうした新しい市場が生まれる場合、先行することには大きなメリットがあります。優秀な人材を先に採用できることもそうですし、とにかく動き回って試行回数を重ねることでナレッジを獲得できることもそうです。
そうした想いをDMMの亀山会長にぶつけたところ、やってみようということになり、20億円の投資を受けてAlgomaticの創業に至ったというわけです。
――すでにAI関連の事業を行っているAlgoageで新たに生成AI事業を立ち上げるのではなく、新会社を設立したのはなぜでしょうか。
大野氏:自分自身のマインドシェアを、100%生成AI事業に割くべきと考えたからです。Algoageの事業として立ち上げると、どうしても既存事業とのシナジーを考えてサービスを開発することになります。それはそれで重要な展開ですが、私としてはそうした既存のアセットにとらわれない領域でも生成AI事業に取り組むべきだと考えました。
失敗から学んだ新規事業の“本質”
――生成AIを活用した事業は、本当に市場として成立するのかも含めてまだ混沌した状況にあると思います。その中で事業を展開する際、何が重要になってくるでしょうか。
大野氏:やはり重要なのは、市場のニーズだと思います。当然と思われるかもしれませんが、AIのような未知の部分も多い市場では必ずしも技術的な種(シーズ)があるからサービスが生まれるわけではないんです。私自身も過去に多くの失敗を繰り返してきました。
例えば、新しい技術を見つけたときにすごくワクワクして、その技術を使ったサービスを作ったとします。でも、お客さまからすればそのサービスに使われている技術が新しいかどうかなんてどうでもいいんですよね。生活の中で使うなら生活を豊かにするサービスがほしいし、仕事で使うなら業務で成果を上げられるサービスがほしいわけです。
大事なのはニーズがある、つまりマーケットがあること。それにもかかわらず供給が不足している領域であることです。
そして、もう1つ重要なのが、マーケットがあるのに供給が不足する状況を作っている原因が“技術革新”であることです。例えば、インターネット黎明期はWebサイトを作成するニーズがすごく多かったのに、その技術を持っている企業がまだ少なかったため、そこにチャンスがあったわけです。さらに言うなら、その革新的技術を持つ企業が出てきたことで、初めてニーズが顕在化するケースもあります。技術力に強みを持つ私たちが狙っているのは、そのようなマーケットなのです。
Algomaticが狙うマーケットは?
――具体的にAlgomaticが狙っているマーケットはどこでしょうか。
大野氏:Algomaticは1つの事業に集中するために作った会社ではなく、生成AIに関するさまざまな事業やサービスを作っていく会社です。ですから、現時点ではまだ決まったマーケットを見ているわけではなく、生成AI周りの幅広いニーズを拾ってサービスを提供している段階です。
例えば、現在Algomaticが提供している「シゴラクAI」は、「生成AIを使いこなしたい」というニーズに対するソリューションです。ChatGPTやStable Diffusionは使いこなしさえすればとても便利なツールなのですが、AIに指示を出す「プロンプト」をうまく書くのは簡単ではありません。生成AIにやらせたいことがあっても、プロンプトでつまずく人は少なくないと思います。
それなら、「プロンプトテンプレートや専用プロンプトを利用することで、ITツールに慣れていないデスクワーカーでも、生成AIをもっと簡単に使いこなせる」サービスはきっとニーズがあるはずです。そこで開発したのがシゴラクAIになります。
――シゴラクAIの特徴について教えてください。
大野氏:シゴラクAIはChatGPTの活用における問題を解決するツールです。プロンプト問題もそうですが、ChatGPTには入力した文章が学習に使われてしまうというセキュリティ上の課題もあります。一方でシゴラクAIはAPIを利用しており、入力した文章は学習されません。API経由のデータは学習に使われないというのは、OpenAI社がはっきりと公言しています。
また、プロンプトのテンプレートも豊富に用意しています。文章の要約や添削、アジェンダの作成にはもちろん対応できますし、営業であればトークスクリプトや提案資料の作成、開発ならプログラムのコードの変換や追加、人事部門なら採用スカウト文のように、各職種ごとにプロンプトを用意しています。自社専用のオリジナルのプロンプトを開発することも可能です。
なぜ成果を出せるのか? 生成AI領域の課題とAlgomaticの野望
――ニーズをくんだサービスということですが、具体的にどのような企業から引き合いがあるのでしょうか。
大野氏:さまざまな規模の企業からお問い合わせをいただきますが、特に多いのは大企業です。業種で言うとマーケティング領域とは特に好相性で、導入いただける企業も多いですし、成果も出ています。例えば商品のコピーを考えたり、ペルソナのたたき台を作ったり、コンテンツマーケティングのための記事を作成したりといった、アイデア出しや文章作成業務が多い作業でよく使われています。
シゴラクAIが成果を出せる理由は、「AIでできること」と「現場のワークフロー」の2つをどちらもよく理解した上で提供されるプロダクトだからです。我々が技術面に強みを持つことは当然として、現場のワークフローについてはお客さま自身の方が当然詳しいので、当社のカスタマーサクセス担当者がお客さまに張り付きながら設計を進めています。ニーズをしっかりと満たすという意味でも、技術と業務理解、この両輪が重要です。
――今後の展望についても教えてください。
大野氏:シゴラクAIに続く生成AIサービスの開発も進めていきます。例えば、もっと特定のユースケースに特化したサービスなんかも良さそうですね。
課題もないわけではありません。生成AIの精度がどこで頭打ちになるのかや、英語と日本語で精度が違いすぎる点、法律面での整備が追いついていないといった懸念材料もあります。
ただ、すでにChatGPTの競合サービスも出てきていますし、性能面で一部追い抜いているものもあります。例えば、Anthropicが提供する「Claude(クロード)」はChatGPTよりもはるかに大量のプロンプトを処理できます。その意味で今後も生成AIは競争で進化し続けるでしょうし、関連サービスも盛り上がっていくでしょう。
生成AIのテクノロジーはよくインターネット黎明期やスマホシフトに例えられますが、まさにそれくらいの転換期にあると感じています。今から波に乗ることで、5年で1,000億円、10年で1兆円くらいのスケールの事業を作るのも夢ではありません。それが、このタイミングでAlgomaticを創業した理由なんです。