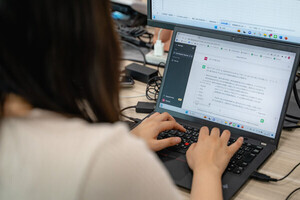「ChatGPT」をはじめとする生成AI(人工知能)の得意技の一つに「文章の要約」が挙げられる。どんなに長い文章でも要点を分析し、分かりやすい短い文章にまとめてくれる。試しに小誌のニュース記事を300字以内で要約するようChatGPTに指示したところ、必要最低限の情報量に絞って返してくれた。
一方、昨今の生成AIブームが起こる前から、文章の要約サービスを展開している企業がある。本の要約サービス「flier」を運営するフライヤーは、そのうちの代表的な一社だ。
同社は、ビジネス本を1冊あたり10分で読める要約形式で提供。話題の新刊やベストセラー本など厳選した1冊を毎日追加している。2023年8月現在、約3300冊の要約を公開しており、会員数は累計で108万人を、法人契約は累計830社を超えた。筆者も通勤時間やお昼休みのお供として愛用しており、要約本の詳細が気になって書店に足を運んだこともしばしばある。
しかし生成AIの登場によって、「要約サービス」を生業にしてきたフライヤーが何かしらの影響を受けていることは間違いないはずだ。フライヤーは今、どのような転換期を迎えているのだろうか。代表取締役 CEOの大賀康史氏に直撃した。
要約ビジネスに生成AIは活用できるか?
フライヤーでは、編集部6名、外注ライター約50名の体制で本の要約を行っている。選書委員会と出版社、著作権者の許諾を得た本でなければ要約できない。出来上がった要約も確認してもらって初めてflierのサイトに公開できるという。
「『すべての本は必ず誰かを救っている』という共通認識をもって、本の素晴らしさを損なわない要約を心掛けています。当然ですが、要約ではすべての内容をカバーすることはできません。ですので、『紹介しきれなかった内容がほかにもある』ということをしっかりと伝え、書籍の購入につなげることも正しい姿勢だと思っています」
要約に対してこだわりを持っているフライヤーだが、驚いたことに、生成AIブームの到来をポジティブに捉えている。実際に、5月よりChatGPTを活用した要約にも挑戦。夏目漱石著の『坊っちゃん』といった著作権フリーの古典作品をChatGPT(大規模言語モデルはGPT-4)に要約させ、その後に編集部が全体を整えている。AIを活用した要約は、「クラシックコレクション」という名目で2~3カ月に1点の頻度で配信していく方針。
大賀氏は、「人並外れたスピードで要約できることは大きなメリット。ですが、ChatGPTは最新のモデルであっても、本1冊レベルの長い文章の文脈を扱うことが苦手です。なので、主人公が全く違う場面で登場してしまうといったことが起こってしまいます。今は古典作品をおよそ1500字ごとに分割して読み込ませているので、ほとんど編集者の手で要約しているのが現状ですね。クオリティは絶対に妥協できません」と、サービスへの応用の難しさを語る。
しかし、大賀氏の生成AIに対する期待は変わらない。「AIが革新技術であることは間違いありません。ここ数年の進化は特にすさまじく、できることは日進月歩で増えています。今、インターネットを使わないビジネスモデルって考えにくいじゃないですか。それと同じように、『AIを使わない事業はあり得ない』という時代がやってくると思っています」(大賀氏)
CEO「生成AIによって淘汰されることはない」
では今後、要約サービスは生成AIによってどのように進化していくのだろうか。大賀氏はこう答える。
「著作権、つまり著者へのリスペクトは絶対に必要なので、要約すべてを生成AIに任せることは考えていません。ですが、そもそものAIの強みの一つである『自然言語処理』を活用して、読者の属性に沿った選書プログラムを用意したり、読書傾向をAIが分析してサービス改善につなげたりしていきたいと考えています」(大賀氏)
つまり大賀氏は、「要約サービス自体が生成AIによって淘汰されることはない」と考えているようだ。確かに、人間が全く関与していないコンテンツを読みたいと思う人間は少ないかもしれない。筆者の場合で考えると、興味本位で1回だけ読んだ後は一切読まないことは容易に想像できる。書き手の気持ちに触れられることは、その文章を読む一つの醍醐味だ。
かといって、大賀氏はAIの恩恵を受けることを諦めてはいない。フライヤーでは、社員がAIのトレンドを常にキャッチアップできるよう、日本ディープラーニング協会が認定している「E資格」と「G検定」にかかる受験料と参考書費用などを全額補助している。現在、半数以上の社員が同制度を活用している。大賀氏はすでにG検定に合格しており、今はE資格に向け猛勉強中だという。
「ターミネーターのような、シンギュラリティ(人間の脳と同レベルのAIが誕生する時点)を超えた世界になるとは思っていません。仕事の進化という意味でもむしろチャンスの方がずっと大きいはずです。大事なのは常に学び続けること。これから環境が変わることはほぼ確定しているので、AIを脅威とはとらえずにポジティブに付き合っていく事が大事です」(大賀氏)