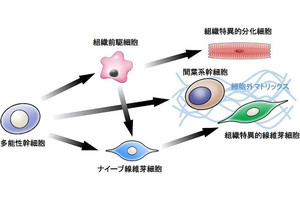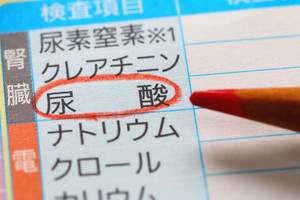名古屋大学(名大)は8月24日、血液透析を新たに開始した約4万人の末期腎不全患者における1日あたりの尿と、心臓突然死を含む心血管病死亡および非心血管病死亡リスクとの関連性を解析し、残存している腎機能を失うことが、心臓突然死を含むあらゆる死亡リスクの上昇と関連すること、そしてその背景の1つに栄養指標が悪化する傾向があることを明らかにしたと発表した。
同成果は、名大大学院 医学系研究科 腎臓内科学の岡崎雅樹助教(臨床研究教育学)は、米・カリフォルニア大学アーバイン校 腎臓内科のKamyar Kalantar-Zadeh教授、米・ミシシッピ大学 腎臓内科の小尾佳嗣助教、同・大学 腎臓内科のTariq Shafi教授、米・テネシー大学 腎臓内科のCsaba Kovesdy教授らの研究チームによるもの。詳細は、国際腎臓学会が刊行する腎臓病に関する全般を扱う学術誌「Kidney International Reports」に掲載された。
日本には約35万人の末期腎不全患者が存在し、定期的な透析治療を受けることで健康や生命を維持している。技術の進歩に伴い、腎不全患者は長期間にわたって生存できるようになったが、透析患者の5年生存率は依然として、胃がんや悪性リンパ腫を患うがん患者と同程度かそれ以下だという。
腎不全患者は、腎臓の働きが大きく低下し老廃物を十分に体の外へ出すことができなくなってしまったがために、体内で生じた老廃物の尿毒素が、自分自身の体に蓄積していってしまう。その結果、臓器に負担がかかってしまうのである。
そこで研究チームは今回、全米規模の透析患者の大規模データを用いて、ある程度自分の腎機能が残っている患者は、食べたものを自分の尿で体の外へ排出する余力があるために心臓にかかる水分蓄積の負担が少なく、心臓突然死を含む心血管病死亡リスクが低いという仮説を立て、検証を行ったという。
今回用いられたデータは、2007年~2011年にかけて、米国内のある大規模透析グループで新たに透析治療を開始した18歳以上の20万8820名の対象者のうち、蓄尿データを有しており、かつ週3回の血液透析を60日以上受けた合計3万9623名が解析の対象とされた。定期的な血液透析を開始した時点で残存している腎機能(腎尿素クリアランスもしくは1日尿量)が低い順にグループ分けが行われ、最大1000日間の追跡期間が設定され、心臓突然死を含む心血管病死亡および非心血管病死亡リスクに着目して解析が行われた。
残存腎機能(腎尿素クリアランス)と原因別死亡リスクについての調査では、中央値548日の観察期間中に、2772件の心血管病死亡(1905件の心臓突然死を含む)および2198件の非心血管病死亡が発生した。透析治療スタート時の残存腎機能が低いほど、死因に関わらず死亡リスクが有意に高い傾向が認められたという。
患者の治療背景を分析すると、残存腎機能が低い患者は、タンパク質摂取の指標である標準化蛋白異化率が有意に低い傾向があること、1回の血液透析中に透析器で水分を体から抜き出す速度(限外濾過速度)が大きい傾向にあることが判明した。この機械的に体から水分を抜き出す速度が大きすぎると、患者は透析治療後に疲労感や筋痙攣、立ちくらみといった辛い症状を感じやすくなることが広く知られている。
次に、残存腎機能(1日あたり尿量)の6か月後の変化と、原因別死亡リスクについて調べられた。週3回の血液透析を新たに開始してから6か月後の蓄尿データを得られた1万2169名を対象とした二次解析の結果、1日あたりの尿量を失う速度が速いほど、心臓突然死および非心血管病死亡リスクが高くなる傾向が確かめられた。さらに、統計的精査を行った結果、残存腎機能が患者の余命にもらす利益の一部分は、透析治療中に水分を体から抜き出す速度が穏やかになることで説明されることが明らかにされた。
今回の研究成果により、血液透析患者の長期的な健康を考える上で、わずかでも残っている腎臓の機能を保つための治療戦略を開発する必要性が確認された。
また研究チームは、腎臓が本来ヒトの健康を保つために担っている役割を研究することにより、腎不全と共に生きていかざるを得ない患者にとって、健康的な生活を守るために必要な新しい治療法の開発につながっていくことが期待されるとしている。