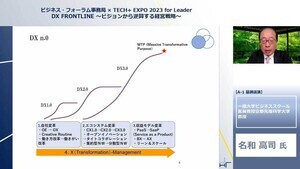電子帳簿保存法(以下、電帳法)の改正やインボイス制度のスタートによって、経理部門が大きな影響を受けることは間違いない。
しかし、これは「経理のDXを推進するチャンス」だと経理がよくなる社 代表で税理士の児玉尚彦氏は言う。
7月21日に開催された「TECH+セミナー 経理業務変革Day 2023 Jul. 法令改正に適した経理DX」に同氏が登壇。電帳法の改正、新制度によって経理はどう変わるのか、経理部門のDXにおいてどのように対応すべきか、その際の注意点などを解説した。
経理もアナログからデジタルへと変化
講演冒頭で児玉氏は、「経理の手法もアナログからデジタルへと大きく変化しつつあり、この数年で特に影響が大きいのが電帳法の改正とインボイス制度のスタート、そしてクラウド化の3つ」だと述べた。これら3つの大きな変化に対して、経理部門としてどう対応するかをしっかりと見据える必要があるという。
社内のデジタル化やデータ連動が進めば、社外との取引もデジタルインボイスのデータでやり取りできるようになり、全ての経理事務が自動化される。言わば“デジタル経理モデル”に移行できる。最終的に、人間はAIに自動仕訳や会計の仕事を任せ、その結果を判断するスタイルになる。ここまで進むために、まずDXの最初の段階である紙書類の電子化、つまりデジタイゼーションによって環境の整備をすることが重要だと児玉氏は語る。
紙文書のデジタル移行について、注意しておくこともある。まずは改正電帳法への対応だ。2024年1月から電子取引データの原本保存が義務化されるので、2023年のうちに保存の方法をしっかり決めておかなければならない。会計システムを使っている場合、電帳法に対応した設定を忘れないようにすることも必要だ。
2023年10月スタートのインボイス制度では、請求書や領収書のフォーマットを変えるだけでなく、会計システムの対応も必須である。そこで児玉氏が推奨するのは、「Peppol」というインボイス制度に準拠した標準規格を使うことだ。Peppol対応であれば、全ての企業が請求書を同じフォーマットでやり取りでき、自動的に会計システムに取り込めるようになる。
改正電帳法とインボイス制度で経理実務はどう変わる?
改正電帳法とインボイス制度によって、経理の実務も変わる。1つ目の変化は帳簿書類の保存方法だ。帳簿書類のうち、電子取引については2024年からデジタル原本のままでの保存が義務化されるが、会計帳簿や紙発行書類については今後も紙での保存がある程度認められる。
ただ、会計帳簿は会計システムの電子データで保存することができ、紙書類はスキャンや撮影した画像で保存することも可能なため、早めに全てデジタルに移行して一元管理することが望ましいと同氏は言う。
インボイス制度について児玉氏は、「領収書、請求書に全てインボイス番号の判別が必須となることが厄介」だと指摘。例えば経費精算の場合、領収書にインボイス登録番号があるかどうかをまず確認する必要が発生するのだ。
番号があれば国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで正規の番号かどうかを照会し、それから会計仕訳という流れになる。番号がない場合は課税仕入れできないが、2023年10月からの3年間は仕入税額相当額の80%、次の3年間は50%の控除が可能になる経過措置があるため、免税取引なら取引の日付も確認しなければならない。
消費税区分が異なれば、仕訳や税額計算も変わってくるため、処理はかなり煩雑になる。児玉氏は、番号の有無だけ確認する、金額が一定以上の場合のみ確認するなど、どこまで取り組むかを制度がスタートする前に決めておくことを推奨した。
これがデジタル経理になれば、インボイス登録番号も自動処理ができる。領収書をスキャンして経費精算システムなどにアップロードするだけで、AI-OCRで文書を読み取ることが可能だ。
この際に注意すべき点として児玉氏は、経過措置判定や税区分処理もシステムに連携するよう設定しておくことと、経費精算システムと会計システムが異なるベンダーのものである場合は、正しく連動ができているか確認しておくことを挙げた。
請求書や領収書といった証憑書類データが会計伝票と連携しているかも要確認事項だが、これを簡単にしてくれるのが証憑管理ストレージサービスだ。
領収書の画像データをストレージサービスにアップロードすれば、自動的にデータ化して会計仕訳に変換し、領収書と関連付けてくれる。自動化しておくことで、二重計上などのミスや不正を防げることが利点である。
「このようなシステムを社内で開発するのは難しいですが、JIIMA認証(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会による電帳法対応システム認証制度)のシステムを使えば良いのではないでしょうか」(児玉氏)
請求書については、今後はデジタルインボイスが普及していくと児玉氏は見ている。先述の規格・Peppolでデジタルインボイスの標準仕様がすでに定められているので、全ての会計システムはPeppolに対応することになっているそうだ。
デジタル化した後の経理の仕事とは
こうしたデジタル化により、経理社員は事務作業から解放されることになる。「将来的に、(経理社員の業務は)システムが行った処理の結果を検証するだけになる」と児玉氏は言う。
「事務作業をコンピュータや非正規職員、クラウド、アウトソーシングなどに移行できる環境になったと考えてください」(児玉氏)
経理社員はこの空いた時間をリスキリングやアップスキリングなど、自身のキャリアアップに当てることができるようになり、業績管理や財務管理などのマネジメント業務に注力できる環境となる。DXによって、経理社員に求められるスキルも事務作業から経営管理へシフトすることになるのだ。
「事務作業だけでは評価が上がりにくいものです。しかし、これまで事務作業に取られていた時間を経営管理や財務管理に充てることで、経理社員の評価は上がっていくのではないでしょうか」(児玉氏)
経理DXに失敗しないために
児玉氏はこれまで数多くの企業の経理DXに伴走してきたそうだが、必ずしもDXが成功するとは限らないと語り、いくつかの失敗例を挙げた。
まず計画段階では、法定期限の直前まで改正電帳法やインボイスへの対応が間に合わず、漏れが生じるケースも散見されるという。新しいシステムに対応するためには、テスト、検証、運用フォローなど、やらなければならないことは多い。あらかじめデジタル化の方向性を見据えて年間スケジュールを組むなど、「経理のDX計画を定めることが必要」だと児玉氏はアドバイスする。
自分の部署だけをデジタル化しようとして、結果的にDXがうまく回らなくなる例もある。データは他の部門や取引先からも入ってくるので、「取引の発生から計上、決済まで全体を把握した上で、経理部内だけでなく全社を見通してデジタル化を考えるべき」(児玉氏)なのだ。
経理管理職やDX推進担当者の完璧主義が邪魔をすることもあるという。児玉氏は、AI-OCRのスキャンで文字認識のエラーが1割だけであっても、「このシステムは使いものにならない」とデジタル化を先延ばしにしてしまった例を挙げた。同氏は、「担当者だけでは、システムが法制度に適合しているかが確認しきれないので、すでに認証を得ているJIIMA認証に準拠したシステムを利用すれば良いと割り切るのも手段」だと話し、「日頃からミスが許されない経理担当でも、効率化できる部分がある」と続けた。
また、会社に独自の経理業務スタイルがある場合に、自分たちのやり方にこだわるあまり市販ソフトやクラウドサービスの導入が進まないこともあるという。ベンダーが提供する標準システムをカスタマイズすれば、相応のコストも時間もかかる。この点について児玉氏は、標準システムを使いながら、例外処理だけを個別に対応することを推奨した。
講演の最後に児玉氏は、デジタル化によって経理社員の仕事を奪われたと思うのではなく、早めにコンピュータに仕事を渡すことで「自分のキャリアアップができるようになったと考えるべき」だと述べ、早めにデジタル化することを促した。
「デジタル化によって生産性を上げ、経理社員のキャリア形成につなげていくのがこれからの時代です。経理の皆さんは早めにDXを進めることで、成長発展につなげていきましょう」(児玉氏)