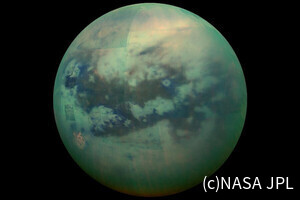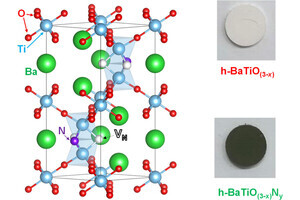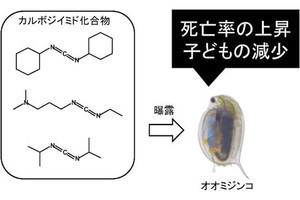東京工業大学(東工大)は8月2日、タンパク質の材料となるペプチドによる「立体ジッパー」構造を人工構築することに成功したと発表した。
同成果は、東工大 科学技術創成研究院 化学生命科学研究所の澤田知久准教授らの研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行する機関学術誌「Journal of the American Chemical Society」に掲載された。
アルツハイマー病の原因物質とされるアミロイド線維(アミロイドβ)は、βシート構造に富んだ線維状のペプチド凝集体からできているタンパク質だ。βシート構造は、正確には平行型βシート構造と呼ばれ、多数の真っ直ぐに伸びたペプチドが、互いに水素結合によって会合したシート状の分子構造をしている。
さらにアミロイド線維は、このシート状になった構造が何枚も折り重なり、平行型βシート同士が互いに面と面で会合することで強靭な線維となっている。このシートの面と面の間は、まるでジッパーのように端と端がぴったりと合わさって重なった構造となっており、シートの側鎖が密に充てんされたコア構造を形成することから「立体ジッパー」と呼ばれている。
これまで、天然のアミロイドタンパク質中のペプチド配列を用いた結晶構造解析によって、立体ジッパー構造の検証がなされてきた。しかし、その構造を人工的に構築するための設計指針がほとんど存在していなかったとする。その主な理由は、βシート構造になるペプチド配列が非常に強い凝集性を示すためシート状に並ばず、無秩序に会合するという問題を抱えていたからである。
立体ジッパー構造を人工的に構築する方法を開発することができれば、側鎖の種類に応じたジッパー相互作用の違いを理解することができ、さらに、アミロイド線維を模倣した強靭なペプチド性材料の創製にも応用できると考えられている。
そこで研究チームは今回、ペプチド同士の無秩序な凝集を避けるため、ペプチドに金属イオンと結合する設計を施すことにしたとする。この金属イオンによる自己組織化をうまく用いることで、精密な平行型βシート構造の構築と立体ジッパー構造の模倣を試みることにしたという。
具体的には、βシートの片面には金属イオンと結合する面を、もう一方には立体ジッパーを形成する面ができるようにペプチド配列が設計された。11種類のペプチド配列が合成され、亜鉛または銀イオンと水・アルコール溶液中で混合させると、9つの配列から単結晶を生成することができたとする。これら9つの配列のX線回折や電子線回折による構造解析から、平行型βシート構造、さらには立体ジッパー構造が形成されていることが高分解能の観察によって確認されたとした。
観測された立体ジッパー構造は、ジッパーを構成する側の鎖が全て小さい場合には噛み合い型を、側鎖が全て大きい場合には接触型を、側鎖が大きいものと小さいもののペアの場合には凹凸様式を取ることが判明。さらに、ジッパーを形成する際、2枚の平行βシートは逆平行に向かい合う様式で張り合わさることがこれまでの研究では報告されていたが、ジッパーを構成する側鎖の種類によっては2枚の平行βシートが平行に向かい合う様式で張り合わさっていることが今回初めて観測されたとした。
今回構築に成功した立体ジッパー構造は、アミロイド線維に分子レベルで働く相互作用を理解するための良いモデルとなりえるとする。
今回の研究成果を基に、立体ジッパーがもたらすアミロイド線維の構造安定性に関する考察を深め、アミロイド線維の形成を阻害するためのアイデアを得ていくことが期待されるとした。また、アミロイド線維のような強靭なペプチド性材料の創製にも応用できると考えているという。
さらに、今回構築された平行型βシートは平らなものだったが、自然界のタンパク質の構造中に見られる平行型βシートには、湾曲したものや長周期のねじれを持つものも少なくないため、βシートの形状を自在に設計できる手法の開発を進めたいとしている。