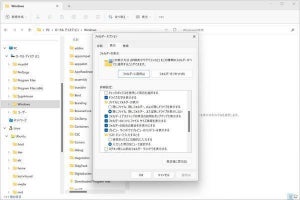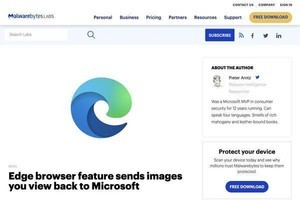日本マイクロソフトは6月27日~28日、開発者向けイベント「Microsoft Build Japan」を品川本社ビルとオンラインのハイブリッドにて開催している。
同イベントでは、米マイクロソフトが2023年5月23日~25日(現地時間)に開催した「Microsoft Build 2023」で発表された同社ソリューションのアップデートやAIを活用した新機能、開発者向けの最新情報などが紹介されている。
イベント初日の基調講演では、「Microsoft Cloudで加速するAI時代の開発」と題して、 Microsoft Buildでの50を超える発表内容の中から、組織でのAI活用を支援する「Copilot Stack」や「Azure OpenAIリファレンスアーキテクチャ」、新しいデータ分析スイート「Microsoft Fabric」など注目のトピックが取り上げられた。
「Microsoft AI Co-Innovation Lab」を開設
基調講演の冒頭では、日本マイクロソフト 代表取締役社長の津坂美樹氏が登壇し、「AIはパソコン、インターネット、携帯電話に続く4つ目のテクノロジーレボリューションだと感じている。そうした中で、開発者の役割が益々重要になる時代がやってきたと思う。私たちのテクノロジーが創造力と活動、そして経済成長に繋がれば幸いだ。開発者とともに新しい時代を作っていきたい」と述べた。
併せて津坂氏は、日本におけるAIやIoTを活用したビジネス推進を支援する場として、「Microsoft AI Co-Innovation Lab」を国内に開設すると発表した。すでにグローバルでは4拠点が開設済みで、日本は5番目の拠点となる。開設時期は2023年秋の予定だ。
同拠点では、企業が自社のシステムやサービスにAIを組み合わせるうえでの技術検証や、新たなソリューションのビジネス化などに取り組むことができる。ソリューションの構築・開発・プロトタイプ作成・テストを、マイクロソフトのエンジニアや開発者チームと共同で行える点が特徴だという。
マイクロソフトは数十年前からAIの研究・開発を続けてきており、独自開発のAI機能を製品に実装してきた。生成AI(ジェネレーティブAI)がもたらす影響力に注目し、2019年にはOpenAIとパートナーシップを締結。現在は、「責任あるAI」の原則という開発フレームワークに基づいたガイドラインに沿って、生成AIを利用した機能の設計・開発・製品提供を進めている。
生成AIを利用した機能群は、パイロットである人をサポートするというコンセプトの「Copilot(副操縦士)」として提供している。最大の特徴は、自然言語で指示を出すことでテキストや画像、グラフ、コードなどを生成できる点で、最初に発表されたCopilotが開発者向けの「GitHub Copilot」となる。
「私はMicrosoft 365とWindowsで提供されるCopilotを日々利用している。Copilotを利用することで自分の仕事が効率よくなるのを感じられ、世の中の大きな変化がすぐそこまで来ているのだと実感している」と津坂氏は語った。
「Copilot Stack」でオリジナルのAI機能を開発
GitHub Copilotのほか、マイクロソフトではDynamics 365 Copilot、Microsoft 365 Copilot、Windows Copilotなど、自然言語でAIによるサポートを受けられる機能の提供を発表している。Microsoft Buildでは、そうしたCopilotに機能を追加できる「Plugins(プラグイン)」が発表された。
日本マイクロソフト 執行役員 常務 クラウド&ソリューション事業本部長の岡嵜禎氏は、「Microsoft 365 Copilotにより、Wordで作成した契約書の内容をチェックすることが可能だが、プラグインによって専門性が要求される場面で機能拡張ができるようになる」と説明した。
例えば、契約書が米カリフォルニア州の法律に即した内容になっているかチェックし、誤っている文言の修正を行いたい際に、プラグインを有効にすることでCopilotが同州の法律に即した契約書レビューを行えるようになる、といったコンセプトをマイクロソフトでは構想している。
今後は企業や組織において、独自のアプリケーションやデータを活用したオリジナルのCopilotの開発が加速していくとマイクロソフトでは考えている。そうしたニーズに応えるための開発フレームワークとして、Microsoft Buildでは「Copilot Stack」が発表された。
同フレームワークでは前述のプラグインのほか、企業が自社で開発したアプリケーションに組み込むための「AI基盤モデル」と「AIオーケストレーション」を提供する。
「例えば、GPT-4の言語モデルを自分たちで拡張し、独自のモデルを作りたい場合に用いるのがAI基盤モデルだ。一方、AIオーケストレーションでは、GPT-3.5やGPT-4など既存の言語モデルをベースに、自分たちのデータをアプリケーションレイヤーに組み込める」(岡嵜氏)
開発者向けツールの「Azure AI Studio」にもCopilot Stackに対応した機能が追加された。今回、AIオーケストレーションによる開発を支援するGUIベースのツールとして「プロンプトフロー」が追加された。また、AI基盤モデルを利用して開発を行う際は、OpenAIの言語モデルだけでなく、Hugging Faceなどのオープンソースの言語モデルも利用できるようになった。
データ管理のスイート「Microsoft Fabric」
AI活用をデータ面で支援する製品としては「Microsoft Fabric」が紹介された。同製品は、マイクロソフトがこれまで提供してきたデータ分析の関連製品をスイートとして統合したもので、SaaS(Software as a Service)で提供される。
物理的に1カ所にデータを統合しなくても、組織内のデータを横断的に活用できるようにする「OneLake」というコンセプトを採用している点が同製品の特徴だという。また、Copilot機能も備わっており、同機能でデータを検索する際のクエリを自動生成することができるという。
岡嵜氏は、「他社のクラウドサービスやオンプレミスにあるデータも、仮想的にOneLakeで見えるようにしてMicrosoft Fabricで利用できる」と説明した。
このほか、基調講演ではMicrosoft Build後に発表された開発者向けのアップデートが紹介された。Azure OpenAI Serviceでは、任意のデータセットや社内データを読み込ませることができる「on your data機能」のパブリックプレビュー版の提供が開始した。
また、量子コンピューティングのクラウドサービスである「Azure Quantum」でもCopilot機能が追加された。Azure OpenAI Serviceに化学および材料科学データセットを読み込ませることで、研究者は自然言語でコードを生成したり、量子計算を行ったりできるという。
Azure OpenAI活用のためのリファレンスアーキテクチャ
近い将来、一般企業や組織でも独自のCopilotを作れるようになる中では、AIの開発、提供などに責任を持って取り組むことが求められる。例えば、著作権侵害をしていないか、人類に悪影響を与えないAIであるか、個人情報は守られているか、事実と異なる内容を出力していないかなどが、企業が独自にカスタマイズしたAIにも問われてくる。
基調講演では、企業の責任あるAI活用を支援するサービスとして「Azure AI Content Safety」が紹介された。同サービスでは不適切なコンテンツの検出や重大度の定義を設定する機能のほか、AIが生成したコンテンツかどうか判断する仕組みを実装する予定だという。
他方で、国内におけるAI活用を支援するために、マイクロソフトが推奨するAzure OpenAI Serviceの活用シナリオ例とアーキテクチャを提供する「Azure OpenAI Serviceリファレンスアーキテクチャ」が2023年7月4日よりMicrosoft Baseコンテンツポータルにて公開される。
今後は同リファレンスアーキテクチャのパートナープログラムも開始する。2023年8月以降には、同プログラムに参加する企業による独自のリファレンスアーキテクチャや事例なども公開される予定だ。同プログラムには、すでに45社の国内企業が賛同を表明しているという。
岡嵜氏は最後に、「パートナープログラムにより、開発の汎用的な部分に関するノウハウを共通化することによって、日本におけるAIのモメンタム、イノベーションを発展させていきたい。さまざまなユースケースによってAIの効果が見えてきている中で、どこで活用するか、どうやって作るかが問われる。それらをスピーディに実現するためには開発者の存在がキーとなる」と強調した。