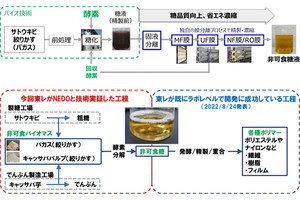京都大学(京大)は6月22日、ワイン作りに欠かせない酵母がブドウの果皮に適応する現象を実験室内で再現することに成功したと発表した。
同成果は、京大大学院 農学研究科の渡辺大輔准教授(現・奈良先端科学技術大学院大学 准教授)と同・橋本渉教授の研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。
ワインは新石器時代から醸造が始まったとされるが、人類がどのようにその醸造技術を獲得したのかは、未解明の部分が多い。通説では、ワインの原料であるブドウ果皮に、アルコール発酵を行えるワイン酵母「Saccharomyces cerevisiae」(S. cerevisiae)およびその近縁種が存在するとされ、ブドウを搾汁する過程でワイン酵母が果汁中に移行し、自発的にアルコール発酵が開始されると信じられてきた。
しかし近年になって、傷のない健全なブドウ果皮にはワイン酵母がほとんど生育しておらず、アルコール発酵能がない、または低い常在性の微生物からなる生態系が形成されていることがわかってきた。つまり、ワインの自発的な発酵プロセスにおいて、ワイン酵母が果皮に適応するためのメカニズムの解明が課題となっていたのである。
そこで今回はまず、ブドウ果実を乾燥させて作るレーズンに水を加えて数日間保温して生じさせた「レーズン酵母」に着目し、その中の微生物叢をメタゲノム解析で調べたとのこと。すると、高確率でS. cerevisiaeなどの高いアルコール発酵能を有する酵母がレーズンに存在し、優占的な生育を示したという。酵母はレーズン中の糖分を使ってアルコール発酵を行えるため、レーズン酵母こそがワインの原型の1つである可能性が考えられたとする。このことから研究チームは、ワイン酵母がほぼ存在しないブドウからレーズンへと変化する過程で、果皮においてワイン酵母が生育すると考察したとする。
続いて、実験室内で無菌のオーブンを用いてブドウ果実を乾燥させてレーズンを製造し、果皮に存在する微生物叢を再びメタゲノム解析で調べたという。その結果、実験室内のレーズン製造ではS. cerevisiaeおよびその近縁種の酵母は生育せず、あらかじめブドウ果皮に少量のS. cerevisiaeを人為的に付着させた場合にのみ生育が認められたとする。このことから、周囲の環境や虫・鳥などの動物に由来する外来性のワイン酵母がブドウ果皮に付着することがきっかけとなって生育し、ワイン酵母を含むレーズンが形成されることが推察された。
研究チームは、ブドウ果皮におけるワイン酵母の常在が困難な理由を調査。今回の研究では、代表的なブドウ果皮常在菌の一種である真菌「Aureobasidium pullulans」(A. pullulans)を国産ブドウから単離し、多くのワイン酵母が属するS. cerevisiaeとの比較を行ったという。