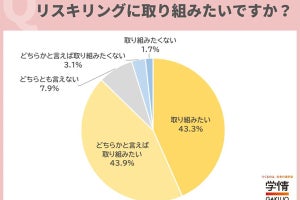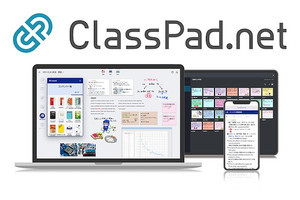米Duolingoは6月9日、語学学習アプリ「Duolingo」(以下、Duolingoアプリ)など同社が提供するサービスでのAI活用に関する記者説明会を開いた。
同社は過去10年以上にわたって、自社サービスにAIを活用し続けている。GPT-4を搭載した新サービス「Duolingo MAX」の日本公開を控える中、説明会では同サービスの詳細や同社が語学学習のどのような領域でAIを活用しているかが解説された。
2つの新機能を備えたGPT-4搭載の「Duolingo MAX」
米Duolingoは2023年3月14日(現地時間)にDuolingo MAXを発表した。同サービスは、「Duolingo Plus」に続く、Duolingoアプリの有料サービスとなる。月額課金のサブスクリプションモデルで提供され、現在は米国とカナダでリリース済みだ。今後は日本での提供も予定しているという。
同サービスでは、既存アプリで利用できる機能に加えて、「Roleplay」と「Explain My Answer」という新機能が利用できる。
Roleplayでは、「パリのカフェで飲み物を注文する」など、シチュエーション別の英会話トレー二ングが可能だ。ユーザーは対話型AIチャットボットを通じて、同アプリのキャラクターとテキストベースの会話を行う。Explain My Answerは、通常の語学学習レッスンで回答を間違った際に、「なぜ間違ったか」がリアルタイムに解説する機能だ。解説内容はAIによって生成され、チャット形式で配信される。
両機能には同社が開発した独自AIと、語学学習に合わせてAIモデルのトレーニングがなされたGPT-4が利用されている。GPT-4に対しては、チャットで送信するテキストの生成や文脈に合わせて展開すべき会話の示唆、解説の正確性向上などの指示がプロンプトを用いて行われる。
なお、アプリ内で作成されたプロンプトがOpenAIに保持され、GPT-4のトレーニングに活用されることはないという。
LLM(大規模言語モデル)を用いたAIは間違った内容を回答することが懸念されている。両機能でも文脈に沿わない返答や、誤った解説が生成される確率はゼロではないそうだ。
だが、Duolingo Head of AIのKlinton Bicknell氏は、「新機能のローンチにあたってはOpenAIとも協業している。間違った解説をする確率を下げるためにAIモデルのファインチューニングをしており、今後も継続する。また、GPT-4はGPT-3.5に比べて誤った内容を生成する確率が低く、サービスに実装するにあたり問題はないと確信している。新機能を活用することで、ユーザーは語学学習を深めるとともに、実践的な会話を身に付けることができる」と説明した。
Duolingoアプリには元々、英文作成や翻訳などで誤った内容が見つかった際にユーザーからフィードバックを受ける機能を実装している。GPT-4を活用した新機能においても同様に、フィードバックを機能改善に生かす方針だという。
他方で米Duolingoは2022年9月からOpenAIと協業関係を続けている。Bicknell氏は「GPT-4のローンチパートナーとして、当社のサービスとは関係ないデータをGPT-4のトレーニング用に一部提供していた」と明かした。現在はGPT-4のモデルが確立されたので、リクエストがあった際にデータを提供しているという。
「最適な教師」が持つ3つの特徴をAIで再現
2023年5月末時点で、DuolingoアプリのMAU(月間アクティブユーザー)は7000万人超となる。アプリでは1日あたり10億以上のユーザーデータを収集しており、米Duolingoではそれらのデータをユーザーのパーソナライズやプッシュ通知の最適化、キャラクターボイスの生成などに利用している。
米Duolingo 日本カントリーマネージャーの水谷翔氏は、「当社は創業当初からサービスの基本機能を無料で提供するフリーミアムモデルを採用し、アプリなどで満足度の高い体験を提供することでユーザーを増やしている。ユーザーが増えるにつれてデータも集まり、集まったデータによってプロダクトが改善される。日々集められる膨大なデータの処理にAIが必須なため、AIを活用することを前提にサービスが開発された」と述べた。
語学学習へのAI活用にあたって、同社は学習をサポートする「最良な教師」に備わっている3つの特徴を定義し、それらを再現できるようなAI機能を独自に開発・活用している。
1つ目の特徴が「教材を熟知している」で、AIアルゴリズムを搭載したツールで教材作成者を支援している。異なる言語同士では、ある表現を翻訳する際に正解となる表現が複数通り存在することがある。同社では、さまざまな文章サンプルを基に、「正解と見なしてよい表現の範囲」をAIに学習させることで、教材作成者が「どの表現を正解とするか」の判断をサポートしている。同AIの機能は、作業の効率化やヒューマンエラーの防止に役立っているそうだ。
2つ目の特徴が「生徒のやる気を維持することができる」で、ユーザーのモチベーション向上に繋がるようにAIを活用している。Duolingoアプリではゲーム要素を取り入れることを重視しており、さまざまな性格のキャラクターが登場するが、キャラクターの性格に合った音声合成にAIが活用される。
また、アプリ利用者に学習を促すメッセージを送る際のプッシュ通知にもAIを活用する。多くのアプリでは、プッシュ通知は同じ内容のメッセージが同じタイミングで送られるものだが、DuolingoアプリではAIが数百通りのメッセージからユーザーに合ったものを選んで配信しているという。
Bicknell氏は、「機械学習モデルで、アプリの利用状況やこれまでの通知を基にユーザーがどう行動したかなどを分析し、個々のユーザーが学習に取り組みたくなるようなタイミングでプッシュ通知を送っている」と解説した。
3つ目の特徴が「生徒が学習のどの段階で悩んでいるかわかる」だ。Duolingoアプリでは、ユーザーが効果的に反復学習が行えるよう、独自開発したAI「Birdbrain(バードブレイン)」を利用している。
具体的には、「HLR(半減期回帰)モデル」と呼ばれる統計モデルを活用して、ユーザーがどのタイミングで復習しなければいけないか同AIが判断し、一度学んだ内容の再演習を促しているという。
「再演習時に正解した場合、次の演習までのタイミングが長くなり、不正解だった場合は次の演習までのタイミングが短くなる。これにより、ユーザーの理解度や習熟度に合ったタイミングでの再演習が設計できる」(Bicknell氏)
-

右上の折れ線グラフが「HLR(半減期回帰)モデル」のイメージ。縦軸がユーザーの理解度で、横軸が初回学習時から経過時間。演習時に正解(緑の印)だったら、次回の学習までの時間が長くなり、失敗(赤い印)だったら次の学習タイミングが短くなる
加えて、簡単すぎず、難しすぎもしないユーザーそれぞれに合ったレベルである「発達の近接領域」を、ユーザーの学習内容を基にAIが分析して個々の演習内容を同AIが調整しているそうだ。
そうしたユーザーに合わせた学習内容の調整には、現在、同AIのバージョン2が利用されている。同AIはニューラルネットワークを活用することで、個々のユーザーの学習内容や理解度をより細かく把握できるようになったという。
「バージョン2ではユーザーの学習状況を継続的に更新できる仕組みにした。これによって、提供する教材もよりユーザーに沿ったものになったため、バージョン2移行後はユーザーはより難しい内容を扱えるようになり、レッスンに費やす時間も増えた」とBicknell氏は語った。