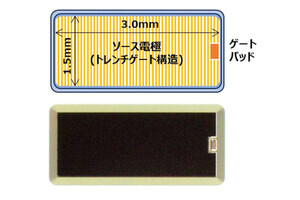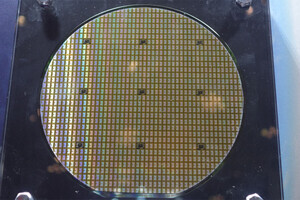電通デジタルは2022年2月、新オフィス「汐留PORT」の稼働を開始した。リニューアルによって空間を一新し、快適で機能的なオフィスを表彰する「日経ニューオフィス賞」において1社のみが選ばれる経済産業大臣賞を受賞した同オフィスは、どのような理念に基づきつくられたのだろうか。
3月14日に開催された「TECH+EXPO 2023 Spring for ハイブリッドワーク 『働く』を再構築する」に、同社 コーポレート部門 総務部長の飯野将志氏が登壇。「オフィスは経営戦略実現装置 ~リアルな世界が私たちを強くする~」と題し、オフィスリニューアルの経緯や計画の中で重視したことなどについて、実際に稼働するオフィスの様子を交えながら紹介した。
【あわせて読みたい】「TECH+EXPO 2023 Spring for ハイブリッドワーク 『働く』を再構築する」その他のレポートはこちら
オフィスは経営戦略を実現するための装置
講演冒頭で飯野氏は、「オフィスは経営戦略を実現するための装置だと考えるべき」だと持論を展開。経営者の視線で考えるとオフィスとはコストがかかるものだが、経営戦略実現のためには必要なものであり、オフィスづくりはその装置の開発への投資となる。それ故、オフィスの構築は投資に責任を持てる立場の人間と共に進めるべきであり、「投資責任者の最終的な判断を仰ぐことが必要」だと言う。
同氏はさらに、投資を最適化するには、オフィス設備のことだけを考えるのではなく、賃借料はもちろん、工事費や光熱費、利用するソフトウエア、そこに通う従業員の交通費など全てのコストを対象にし、働く環境全体に対してどのような投資が最適かを考えるべきだと説く。実際に同社では現在、こういったコストが社員1人当たりでどのように変遷しているかを捕捉追跡し、次の投資判断に活かすことにしているという。
オフィスのリニューアルに際し、飯野氏は最初に経営層への聞き取りを行い、4つの点について確認したそうだ。その4つとは、「経営戦略としてやるべきこと」「社として育てたいユニークさ」「オフィスというリアルな場に集まる意味」、そして「どんなかたちになればこのプロジェクトが成功したと言えるか」である。経営者は経営のプロではあるが、オフィスのプロではない。だから経営層にはオフィスのことではなく、会社をどのようにしたいかを確認すべきなのだ。
リアルなオフィスで行うと良い“振る舞い”を定義する
では、どのようなことを強化すれば経営戦略の実現が加速するのか。電通デジタルにおいては、専門力、統合力、機動力、信頼構築の4つの力をオフィスで強めることだったと飯野氏は語る。そしてそのためのオフィスとはどういうものかを考えた上で、基本計画の段階においては、まず集まる場所とその意味を整理するところから始めた。結果として「オフィスは、テキストでは伝わりにくいことを時間や場所を決めてやる場所である」と定義し、前述の強めたい4つの力それぞれについて、オフィスというリアルな場で行うと良いであろう社員の振る舞いも定めた。専門力であれば観察や発信、統合力は雑談や企画、機動力では商談や合宿、信頼構築なら対話やチームビルドといった具合だ。
これらの振る舞いについては、例えば「合宿」と言っても人によってイメージが異なる可能性がある。そのため、それぞれの振る舞いの写真をプロジェクトメンバーに見せ、「このプロジェクトにおいて合宿とはこういうもの」というイメージの統一も図った。さらに、それぞれの振る舞いに名前を付け、詳細化した。合宿ならば「ハックルーム」、観察ならば「チームホーム」と名付け、そこでどんなことが行われるべきか、そのためにどんなデザインが必要か、どんなIT環境であるべきかといったことを決めていったという。
この基本計画の段階では、「エクスペリエンスデザインの考え方を重視した」と飯野氏は言う。ここで重要なのは、オフィスを席数や室数といった“場所”で定義するのではなく、“振る舞い”で要素を整理すべきであること、そして初期段階で図面をつくらないことだ。
「先に図面があると、その図面の通りのオフィスをつくるためのプロジェクトになってしまいます。それを避けるためにも、図面は振る舞いを整理した後につくるべきなのです」(飯野氏)