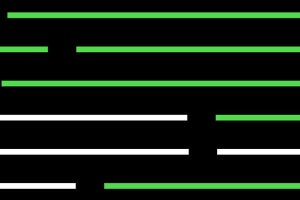米OpenAIが2022年11月に提供を開始したチャット型のAI「ChatGPT」の登場を皮切りに、MicrosoftやGoogle、Adobeなど、世界を代表するIT企業らが、次々にジェネレーティブAI(生成型AI)を誕生させている。ChatGPTに関するニュースを目にしない日がないくらい、世界中で盛り上がりをみせている。
一方、多くの国内企業では、情報管理や著作権などのリスクの観点からChatGPTの導入に踏み切っておらず、使用を禁止している企業もある。
そんな中、パナソニックホールディンクス(HD)傘下でシステム開発を手掛けるパナソニック コネクトは、ChatGPTの全社導入に舵を切った。業務生産性とAIスキルの向上を目指して、国内の全従業員1万2500人にAIアシスタントを展開している。社員は、AIに専門知識を聞いたり、プログラムコードの作成を頼んだりと、2月17日の開始日からわずか1週間で2万回利用しているという。
多くの企業がChatGPTの導入に踏みとどまる中、なぜパナソニック コネクトは、これまで早く導入を決定できたのか。そして、実際にChatGPTを使ってみて気づいたこととは。IT・デジタル推進本部 執行役員 CIOの河野昭彦氏、IT・デジタル戦略企画室長の向野孔己氏に話を聞いた。
当たり前を感じることが重要
パナソニック コネクトが展開するAIアシスタントの名称は「ConnectGPT」。MicrosoftがAzure上で提供する「GTP3.5」の法人向けサービスを活用して、AIアシスタントサービスを独自開発し導入した。また、3月13日からは同社が提供するChatGPTの法人向けサービスも導入しており、社員は社内イントラネット上から同サービスにアクセスして、いつでもAIに質問をすることができる。
「AIをビジネスに活用するかどうかではなく、いつ活用を始めるかの時代になってきていると思います。AIを使いこなすビジネスパーソンとそうでないビジネスパーソンの生産性には、大きな差が出てくる時代が必ず来るはずです」ーー向野氏はこう断言する。
同社はChatGPTに使用にあたって、「入力した情報は2次利用しない」、「入力した情報は一定期間を過ぎたら消去する」といったことを徹底することで、セキュリティ面に配慮している。
加えて、社員に対しては 、利用にあたって以下の5つの注意事項を周知している 。ChatGPTにできること、できないことをしっかりと把握させることで、正しく効率的に使用することを促している。
1. 回答が正しいとは限らない。最後は人が判断する
2. 情報が最新ではない(ChatGPTは2021年9月までの情報)
3. 英語のほうが正確な返答が返ってくる
4. 公開情報からしか回答しない。社内情報は非対応
5. 未来予測はできない
活用方法は大きく分けて「聞く」と「頼む」の2つあるという。「アドバイスや専門知識、アイデアを聞いたり、判断や文章・資料作成、プログラムコードの作成を頼んだりできます。AIに情報を与えれば与えるほど、正確に答えてくれます」(向野氏)
また、英語で質問したほうが、より精度の高い回答が得られることから自動翻訳機能も搭載。日本語で入力した質問を英語に変換してAIに質問したり、英語で得た回答を日本語に翻訳したりすることもできる。
実際に使用した社員からは、「仮説のアイデア出しに役立つ」、「人に聞くほどではないちょっとしたことを聞ける」、「プログラム開発のアドバイスが的確」といった好意的な声が上がっているという。
河野氏は、「聞くことに関しては、『そんなの当たり前のことじゃん』と感じてしまう回答も多々あると思います。ただ、この『当たり前を感じる』ことが重要だと思っていて。なぜかというと、自分の感覚と一般的な感覚にずれが生じていないことが確認できるから。自分の感覚が間違ってなかったことに気づくことで、自信にもつながりますよね。人に聞きにくい質問は、ひとまずAIに聞いてみることで、業務効率化にもつながると考えています」と説明する。
なぜこれまで早く導入できたのか
多くの企業がChatGPTの導入に踏みとどまる中、なぜパナソニック コネクトは、これまで早く導入を決定できたのか。
この質問に対して河野氏は、「『100%信用できるテクノロジーでないと使えない』という概念は捨てて、ChatGPTがどんなものなのか、とりあえず遊んでみようというスタンスで導入しました。最新テクノロジーを使ってみたい人にどんどん使ってもらって、AIの癖や完璧でない部分を感じてもらう。それを踏まえた上で、新たなアイデアに創出につなげてもらいたいと、われわれは考えています」と答えた。
「河野にChatGPTを導入しないかと相談したとき、1分以内に『やってみよう』という話になりました。社長の樋口や、常務でデザイン&マーケティング本部長の山口に相談したときも、誰一人としてダメとは言わず、『今すぐにどんどんやれ』としか言われなかったです」(向野氏)
テクノロジーを正しく理解し、迅速に意思決定できる風土が、パナソニック コネクトにはあるみたいだ。河野氏は、「『AIが人の代わりになる』と言われていますが、僕はそうはならないと思っています。ただ、AIはわれわれを助けてくれる存在であることは間違いありません。そういう意味では、これからAIを使う人とそうでない人の生産性は、大きな格差が生まれると思っています」と話す。
導入してみて気づいたこと
また、ChatGPTを実際に導入してみて、初めて気づいたこともあるという。
「キーワードだけを入力する従来の検索のやり方で、AIアシスタントを使う社員が多いことに気づきました。キーワードだけの指示では、回答の精度ももちろん悪くなるので、社員には『AIアシスタントは人間だと思って、懇切丁寧に伝えましょう』と発信しています」(向野氏)
同社は今後、AIアシスタント以外にも、データ分析やデジタルマーケティング、業務プロセスや、プログラムの開発支援などにもChatGPTを活用していく考え。例えば、社内アンケートの分析や、契約書のチェック、SNS投稿のドラフト作成、サンプルコードの作成などに活用する。
河野氏は、「すごく楽しい時代が来ました。今のところ可能性しか感じていないです。ただ使い方がすごく大事で、AIを使いこなすリテラシーがあらゆる人に求められるようになってくるはずです。また、今回の取り組みに関しても、ダメだなと感じれば即やめればいいだけのことで、1年後もっと使えるテクノロジーが出たら、うまく適用していきます。失敗したっていいんです」と語った。