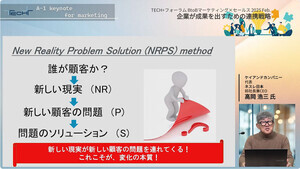昨年12月、有人地帯で補助者なしで目視外飛行が可能なドローンのレベル4飛行が解禁された。簡単に言えば、諸条件をクリアすれば、人が住む場所を無人のドローンが飛行することが可能になった。
有人地帯を飛行できるようになると、ドローンの活用の幅もグッと広がる。そのため、ドローンのレベル4飛行の実用化に向け、さまざまな企業が開発を進めている。
今回、ドローンの活用が大きく期待される物流業界において、物流eVTOL(Electric Vertical Take-Off and Landing:電動垂直離着陸機)の開発や実証実験に取り組むヤマト運輸のドローン輸送について、イノベーション推進部イノベーション推進グループ アシスタントマネージャーの伊藤佑氏、ビジネスソリューション設計部ビジネスソリューション設計グループ第1法人チーム スーパーバイザー齋藤寛氏に話を聞いた。
ドローンで社会課題の解決を
ビジネスサイドからドローン輸送に関わる齋藤氏は、同社のドローン輸送に関する姿勢について、次のように説明した。
「当社は、お客様の幅広いニーズに最適な物流サービスを提供するため、ドローン輸送を他のトラックなどの輸送手段に加え、新たな輸送モードとしてドローン輸送を組み合わせることを目指しています。現在は、ドローン輸送の技術を活用した新しい運び方で社会課題やお客様のお困りごとを解決するため、ビジネスモデルの実証実験や研究を進めています」
世の中にはさまざまな社会課題があるが、同社は医療における課題にフォーカスしている。2021年には、岡山県和気町で、持続的な医薬品輸送ネットワークの構築に向け、ドローン輸送の経済的実現性を検証する実証実験を開始した。
実証実験では、ティーエスアルフレッサの物流拠点からヤマト運輸が集荷した医療用医薬品などを、赤磐吉井営業所から医療機関へドローンで輸送し、さらにオンライン診療・服薬指導後の処方薬を調剤薬局から患者宅までドローンで輸送した。
齋藤氏は実証実験について、「ドローンは、持続可能な地域医療を実現する手段の一つと考えています。このプロジェクトはまだ入り口の段階で、持続的な運用に向けて、コストや運行などの課題を検討しています。医薬品という特性上、人の健康に大きな影響を与えるので、輸送環境などにも拝領しています」と語る。
「空飛ぶトラック」の開発にも挑戦
このように、ヤマト運輸はドローンを活用した輸送の経済的実現性を検証する実験を行う傍ら、物流に最適なドローンの開発にも乗り出している。
ドローンの研究開発を担当する伊藤氏は、「ビジネス実証実験など、ニーズや課題に対して現在できることから実績を積み上げています。一方で、未来にあってほしい世界、技術を描き、その実現に向けて取り組みも進めています。現在起点と未来起点、この二つの方向性を同時に遂行していくことで、実現性を高めながら、それでいてわくわくする物流をつくっていきたいです」と語る。
オンラインショッピングの利用増に加え、新型コロナウイルスの感染拡大が拍車をかけ、宅配便の利用は増加の一途をたどっている。一方、世界中で人材不足が進んでおり、日本の物流業界も例外ではない。配達を依頼される荷物は増えても、それを運ぶ人が足りない。
しかし、配達員が荷物の届け先まで出向く必要がない「空飛ぶトラック」が実現すれば、こうした物流業界が抱える課題を解決することができるかもしれない。
ヤマト運輸の「空飛ぶトラック」の開発は、2018年に端を発する。同年、米国テキストロン傘下のベルテキストロン(以下、ベル)と無人輸送機を共同開発すると発表した。
両社は、eVTOL機の開発に取り組み、2019年には、ベルが開発したAPT 70(自律運航型ポッド輸送機)とヤマトホールディングスが開発した貨物ユニットPUPA701(荷物空輸ポッドユニット)の機能実証実験に成功した。