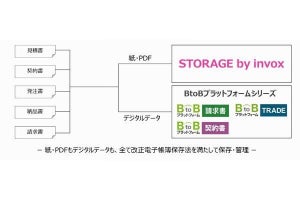企業間の取引などを管理する「インボイス制度」が2023年10月よりスタートする。同制度が始まると、仕入税額控除の対象として認められるのは「インボイス(適格請求書など)」のみとなり、そのインボイスを交付するためには、税務署長に登録申請書を提出し登録を受ける必要がある。
インボイス制度開始日から登録を受けるためには、原則、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があったが、2022年12月に政府が公表した「令和5年度税制改正大綱」によって、2023年9月30日まで延期された。しかし、登録通知が届くまでに一定の期間がかかるため(書面申請:約2カ月、e-Taxでの電子申請:約3週間)、早めの提出が肝心であることに変わりはない。
また、登録申請ができるのは課税事業者のみだ。免税事業者がインボイスを交付するためには、課税事業者への転換をしなければならない。賛成・反対はさておき、同制度に対する注目度は高まっている一方で、「正直よくわからない……」と嘆いている人(特に免税事業者)は少なくないだろう。
そんな中、会計ソフト大手のfreeeは1月某日、インボイス制度の対応に悩んでいるクリエイターを対象にしたセミナーを開催した。ハイブリット形式で開催し、約200名のクリエイターが参加した。同セミナーでは、アカウンティングフォース税理士法人 代表税理士の加瀬洋氏が登壇し、 参加したクリエイターからのインボイス制度に関する質問に答えていた。本稿では、印象的だった質疑応答を取り上げる。
企業案件が多いのでインボイス登録を予定していますが、たまに個人からの依頼もあります。相手側がインボイス登録をしていない場合、インボイス登録をしているこちらの税負担が増えるということでしょうか? (インフルエンサー)
加瀬氏:この場合、税負担は増えません。ここがインボイス制度の分かりにくい部分ですよね。受取側の対応と買取側の対応をごちゃ混ぜにして認識している方が多いです。
恐らくこのケースでは、企業案件も個人案件も受取側が焦点になります。受取側は、相手方がインボイス登録業者でもそうでなくても、消費税の支払額が多くなるといったことはありません。間違いやすいので、誤解のないように気をつけてください。
企業案件でもAmazonギフトカードで支払われるケースがあり、現在すべて確定申告しています。現金以外の報酬の場合もインボイス取引に該当しますか? (インフルエンサー)
加瀬氏:報酬の形は全く関係ありません。現金であってもAmazonギフトカードのような商品券であっても、インボイス取引に該当してしまいます。もっと言えば、モノをもらった場合も消費税が発生します。「Amazonギフトカードは現金じゃないからOK」ということにはなりませんので、お気を付けください。
食べ歩きインフルエンサーのブランディングとして、経費で食べ歩きをすることが多いです。領収書をもとに計上していますが、飲食店がインボイス未登録の場合は、税負担が増えるということでしょうか? (インフルエンサー)
加瀬氏:その通りです。実際に支払った金額で、消費税が含まれているモノを購入したとします。相手先がインボイス登録をしていなければ、自分が支払った消費税が仕入税額控除に使えません。支払った消費税が認められなくなるということです。ブランディングとしてご飯を食べるときにも、店舗側が登録していない場合、増税になってしまうリスクがありますよ、という制度になっています。
インフルエンサーでも商品提供・PRのみの無償案件は事業者登録・課税事業者登録をしなくても問題ありませんでしょうか。ミステリーショッパーという副業もインボイスが必要ということでしょうか? (インフルエンサー)
加瀬氏:無償案件はインボイス取引に該当しません。取引先は報酬を払っていないわけですから、仕入税額控除をする必要がないということになります。
年間数万円の企業案件しか取引していない場合でも、インボイスに対応したほうがいいでしょうか? (インフルエンサー)
加瀬氏:これは判断が難しいですね。取引先との関係性を総合的に勘案する必要があります。免税事業者のままでいる場合は、本来自分が収めるべき消費税を取引先に転嫁していると考えることもできます。仕入税額の一部を控除可能となる経過措置も2029年10月まで設けられていますので、企業との取引量、取引先の企業は免税事業者とどれくらい取引をしているかなど、総合的に考えて決断する必要があります。
外国法人であるGoogle社からの収入に関する質問です。YouTubeでの広告収入は課税対象外売上となるのでしょうか? (YouTuber)
加瀬氏:その通りですね。不課税取引になるケースであり、もらっている報酬にはそもそも消費税が含まれていません。動画プラットフォームからの広告収入のみであれば、インボイスに対応せずとも影響なしと考えられます。
フードデリバリーの配達員をしています。インボイス登録は必要でしょうか? (フードデリバリー配達員)
加瀬氏:契約主体がフードデリバリー事業を営む法人なのか、フードデリバリーの注文者なのかで法律関係、税関係は変わってきます。
事業者から手数料や配達料をもらっている場合は問題ありませんが、注文者からダイレクトにもらっている場合はインボイスに対応したほうがいいかもしれません。例えば、サラリーマンが経費で弁当をデリバリー注文した場合、あなたがインボイス登録をしていなければ、注文者が属する企業の税負担が増えてしまいます。そういったケースであれば、自分も登録しておいた方が、仕事の依頼は受けやすくなると思います。
外注先が副業サラリーマンで規模がとても小さいです。開業届も出されておらず、インボイスの登録もしないと思われます。その場合、発注元である私の税負担が増えるということでしょうか。私は法人の下請けなのでインボイス登録は予定しています(デザイナー)
加瀬氏:残念ながらおっしゃる通りですね。そういう状況に備えて、今から発注先の個人事業主の方々と交渉を進めることをお勧めします。一般的に「仕事を発注する側」の立場のほうが強いと言われています。しかし、立場を利用して、取引を一方的に中断したり、金額の引き下げを要請したりすることは、下請法や独禁法に転換するリスクがあります。
対等な立場からの目線で「インボイスに登録してくれませんか」というふうに交渉を始めることが重要です。