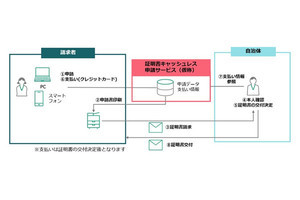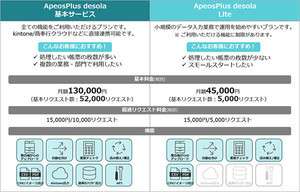富士フイルムは12月12日、DX(デジタルトランスフォーメーション)に関する取り組みを紹介する記者会見を東京都内で開催した。
同社のDXは、2014年のICT戦略推進プロジェクトの発足に端を発する。その後、ICT戦略推進室を設置し、2017年にはCDO(Chief Digital Officer:最高デジタル責任者)、DO(部門ごとのデジタルオフィサー)を設置した。
2021年にはトップダウン型のAll-Fujifilm DX推進プログラムを始動したほか、DX戦略会議を設置。現在は、グループ全体で最適化されたDX推進を目指しているという。
富士フイルムが掲げるDXのビジョンは「イノベーティブなお客様体験の創出と社会課題の解決」「収益性の高い新たなビジネスモデルの創出と飛躍的な生産性向上」の2点だ。これらのビジョンを支える基盤として「製品・サービス」「業務」「人材」「ITインフラ」の4領域を定めている。
富士フイルムの執行役員でCDOを務める杉本征剛氏は、同社のDXの到達段階について、「DX推進体制の整備、DX戦略の策定、DX推進状況の把握を昨年度までに完了し、今後はさらにアップデートする段階。現在は産業変革の加速、デジタルプラットフォームの形成、DX人材の確保に注力している」と、紹介した。
以下に、富士フイルムグループの具体的なDXの事例を紹介する。
富士フイルムDX事例1:ITインフラ
同社はDXの成熟度を4段階に分け、ステージ1を「旧来型で個別最適な段階」、ステージ4を「グローバルトレンドをリードする段階」として分類している。これに当てはめると、2021年度の同社はステージ2に相当し、部門横断的な基盤や全社共通のシステムは一部にとどまっていたという。
現在は2023年度末に向けて、ステージ3を目指している。ステージ3とは、クラウド中心で場所やデバイスにかかわらず柔軟な働き方を実現する段階だ。クラウド移行に伴ってゼロトラストセキュリティ基盤の整備も進める。これまでにMicrosoft 365の全社導入を完了しており、今後は生体認証などと組み合わせた多要素認証を可能とするエンドポイントデバイスを順次導入予定だそうだ。
富士フイルムDX事例2:人材DX
富士フイルムグループのDX人材育成はマインドセットから開始する点が特徴的だ。「なぜ富士フイルムがDXを進めるのか」を社員が理解するところから、育成を始めている。DXに関する基礎教育やデータ活用の啓発を通じてマインドセットを改め、その後に実際の業務課題に有用なツール活用などに取り組むのだという。
スキル習得の段階では、ハンズオンの研修を通じて手を動かしながらツールの習得を目指す。実務上の課題に対しては、適切なツールの選定や課題解決方法の検討に挑戦する。
さらに、その後の研修では成果の創出を狙って「製品・サービスDX」と「業務DX」の2つのコースに分かれ、数カ月間のブートキャンプを実施する。製品・サービスDXでは新たなビジネスモデルの構築を、業務DXでは仕事のスピードと質の向上を図る。
富士フイルムDX事例3:業務DX
富士フイルムでは知財活動を重要視しており、さまざまな場面で研究者や知財部員による特許調査を行っている。しかし、データベースを用いた特許調査候補の抽出では、見る必要がない特許(ノイズ)も多く抽出されてしまうことが課題となっていた。
そこで、同社は業務DXとして、機械学習を用いて特許調査の効率化に取り組んだ。具体的には、人による調査結果を教師データとしてAI(Artificial Intelligence:人工知能)に学習させ、ノイズの除去を試みたという。その結果、特に関心が高く人が確認するべき特許を機械学習によって抽出できるようになり、ノイズを最大83%程度減らすことに成功している。
なお、この機械学習モデルには、既存の自然言語処理基盤を応用したそうだ。同社では従業員向けに自然言語処理をノーコードで実装できるアプリを公開しており、専門的なプログラミングの知識を持たない現場社員が主導して分析モデルを構築できる強みを持つ。
富士フイルムDX事例4:製品・サービスDX
富士フイルムでは、持続的に製品およびサービスを創出するための仕組みとして、人材育成の一環でDXブートキャンプに取り組んでいる。ブートキャンプ内で扱うテーマはCEOや人事部長らが参加するDX戦略会議によって承認されるという。
DXブートキャンプから新サービスを創出した事例の一つが、メディカルシステム事業部が手掛けた医師主導のAI開発を支援するプラットフォーム「SYNAPSE Creative Space」である。これは、プログラミングなどの専門的な工学的知識を持たない医師であっても、画像診断を支援するAIを開発できるようになる目的で構築したプラットフォームだ。
SYNAPSE Creative Spaceはプロジェクト管理から、アノテーション、AI学習、実行までの一連の開発作業を支援する機能を備える。希少疾患などの専門性が高い領域のAI技術開発を医療機関へアウトソースすることで、AIの社会実装の加速を図るとのことだ。
また、医療機関としては研究から社会実装までの道筋が明確化されるとともに、収益化も見込めるため、富士フイルムは産学がwin-winとなるエコシステムが実現できると期待しているそうだ。