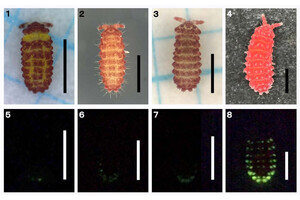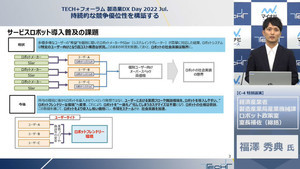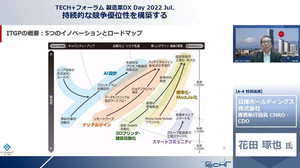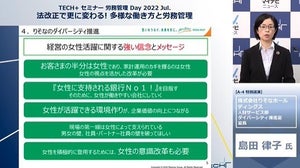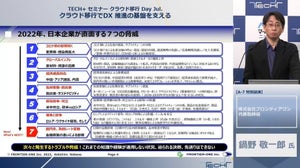パーパスを掲げる企業が増えている。SDGsへの関心が高まり、ビジネス環境が大きく変化する今、企業はパーパス経営を実践することで何が得られるのか。
8月25日、26日に開催された「ビジネス・フォーラム事務局×TECH+ EXPO 2022 for LEADERS DX Frontline 不確実性の時代に求められる視座」に京都先端科学大学 教授であり、一橋大学ビジネススクール 客員教授も務める名和高司氏が登壇。「新SDGsを実践するパーパス経営」と題し、パーパス経営の重要性について解説した。
パーパスを主軸とした新SDGsとは
名和氏は冒頭、自らが提唱する“新SDGs”について説明した。SDGsは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、2030年までに達成すべき17の項目を示した国際目標だ。一方で新SDGsには、パーパスを中心とした、2050年を見据えた方針が盛り込まれている。それを構成するのが、SDGsの18番目の項目を目指す独自の“Sustainability”、ツールとして使われるデジタルからトランスフォーメーションへと移行する“Digital”、ボーダフルな世界の再結合を目指す“Globals”の3要素だ。
名和氏は、新SDGsで大切なのが、3つの要素をつなぐパーパスだと言う。
サステナビリティだけでなく、パーパスが求められる理由
ここで名和氏は、サステナビリティの考えについて3つの段階に分けて紹介した。1つ目は「ESG(Environment・Social・Governance)」である。これは「やって当たり前だという段階」(名和氏)にあり、企業にとってリスク回避のために必要不可欠なものだ。2つ目はSDGsである。これはしっかりと解決できれば新しい事業機会となるものの、闇雲に取り組んでも「決して儲からない」と、同氏は述べる。3つ目は「CSV(Creating Shared Value、共有価値の創造)」である。これは社会価値と経済価値の双方を高めることで実現できるものだと言い、この段階で初めてボトムライン(利益)が成り立つ。そのため、企業経営においてはCSVを重視する必要があると、名和氏は論じる。
また、市場変化も看過することはできない。現在、企業が向き合うべき市場は「顧客市場」「人財市場」「金融市場」の3つがある。顧客市場はライフシフトに伴い、大きく価値観が変化している。人財市場もワークシフトに伴い、今後は1つの会社で働くスタイルから、プロジェクトごとに企業に参画するようなスタイルが一般化することが考えられる。金融市場では、ESGに消極的な企業への投資が減るといったマネーシフトが起こっている。これらのパラダイムシフトに対応するためにも、サステナビリティは必要不可欠な存在だ。
「しかし、サステナビリティを実践しても、必ずしも顧客や人財の心を掴んだことにはなりません。そのためにもパーパスが改めて求められているという時代背景があります」(名和氏)
名和氏はここで、2020年に幸せを量産する“ワクドキ”という18枚目のカードを出したトヨタ、2018年から「クリエイティビティとテクノロジの力で、世界を感動で満たす」というパーパス経営を掲げているソニー、デジタル化により徹底的に無駄を省いた新しい産業構造「有明プロジェクト」を打ち出したファーストリテイリングの事例を挙げ、改めてパーパス経営の重要性を説いた。