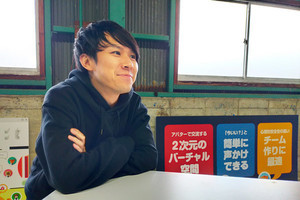仮想空間にオフィスを構築するシステムを手掛けるoViceは10月25日、同社主催のイベント「oVice Summit 2022」を開催した。2回目となる同イベントは、初めてオフラインで開催され、これからの働き方などをテーマに、10以上のセッションが行われた。
「出社」か「テレワーク」、加速する2極化
クロージングセッションにはoVice CEOのジョン・セーヒョン氏が登壇し、ハイブリッドワークを高度化する同社の新たな取り組みについて説明を行った。同氏は冒頭、「ハイブリッドワークに挑戦する企業には、テレワーク組と出社組との間に情報格差や評価の不公平感があるといった課題が散見され、出社かテレワークかの2極化が進んでいる」と、昨今の企業の働き方に関する現状を俯瞰した。
ハイブリッドワークは、出社時の対面によるコミュニケーションを通じたコラボレーションや、組織への帰属感の向上を実現できる一方で、テレワーク時の疎外感を生みがちだ。 例えば、ビデオ会議システムを用いた会議であれば、テレワークをしていても問題なく参加できるが、会議が始まる前やシステムを切った後の雑談にはテレワークをしている人は参加できず、疎外感を感じてしまうといったこともあるだろう。また、テレワークだと勤務時間中の姿が見えないため、なんとなく出社組よりも評価が低くなってしまうこともあるかもしれない。
こうした状況が、企業の「出社」か「テレワーク」かの2極化を進めている要因になっているかもしれないとジョン氏は指摘。例えば、ホンダは新型コロナウイルス禍で認めていたテレワークなどの在宅勤務を廃止し、2022年5月より原則出社に切り替えている。一方で、NTTグループや東芝などは、原則出社のルールを撤廃し、テレワークでの働き方を基本としている。
ジョン氏は、「oViceが目指すは、誰もがどこで働こうが、情報の質や量、パフォーマンスや評価が変わらないハイブリッドワークだ。それをサポートするソリューションを順次拡大していく」と今後の方針を示した。
急拡大するバーチャルオフィスツール「oVice」
同社が提供するバーチャルオフィスツール「oVice」は2020年8月にリリースされた。同ツールでは、アバターを使ってオンライン画面上を自由に動いて自由に話しかけることができる。自分のアバターに近い声は大きく、遠くの声は小さく聞こえる仕組みで、現実世界のオフィスに近い仕様になっている。
リコーや富士フイルムなど大手を中心に導入が進んでおり、導入企業数は2022年10月時点で約2200社と、2021年8月から約1000社増えた。また、約3万のスペースを発行しており、毎日oViceに出社する人口は約7万人いるという。
ジョン氏は、「7万人が毎日oViceで仕事をしており、oViceがないと多くの企業に迷惑をかけるようなインフラに成長してきた。一部の人だけが使うツールではなくなってきた。これからは、デバイスや通信環境に依存しない安定的なサービス提供に注力していく」と語った。
ハイブリッドワークを高度化するシステム
ジョン氏は同イベントで、ハイブリッドワークの高度化に向けた3つの新ソリューションを紹介した。
1つ目はモバイルアプリだ。同社はoViceのモバイルアプリを新たに開発し、PCからでなくても、バーチャル空間にアクセスできるようにした。モバイルアプリでは、PCと同様、バーチャルオフィス上のユーザーとの会話、会議室への入室が可能で、PCユーザーによって共有された画面を見ることができる。
また、リアルオフィスに設置した近距離にだけ届く電波を常に発信するビーコンと連携することで、リアルオフィスにいる人の位置情報をoVice上で常に反映することができるようになった。
次に紹介したのは「窓」と名付けられたサービス。同サービスは、リアルとバーチャルとのコミュニケーションをもっと気軽にそして円滑にするために開発されたという。
実際に窓になるのはサイネージ型のディスプレイ。リアルオフィスにディスプレイ(窓)を置き、位置を連携させた窓をバーチャル上にも置く。そしてバーチャル上の窓にアバターが近づくと、リアルオフィスの窓にそのアバターのアイコンが表示される。アイコンが表示されたバーチャル上のユーザーにはリアルオフィスからの声が届くようになり、カメラ映像を表示して会話することもできる。
逆に言えば、バーチャル上のユーザーも窓の近くにいる出社組の人が一目でわかるので「リアルとバーチャルに関係なく、気軽に話しかけられる」(ジョン氏)としている。
また、同じディスプレイを活用したホワイトボードを共有できるシステムも開発した。同システムは、リアルオフィスとバーチャルオフィスのホワイトボードを連携。リアルから書いた文字や図がバーチャル上に表示されるだけでなく、バーチャル上で書いた文字や図もリアルのホワイトボードに反映される。同システムにより、ビデオ会議システムを用いた会議による情報格差が減る。
これら3つのシステムのプロトタイプは現在運用中といい、11月以降、順次、商用化仕様の検討や開発を進める考えだ。
メリットは「場所時間問わず働ける」だけじゃない
ハイブリッドワークには「場所や時間を問わず働ける」といった従業員視点でのメリットがある。また経営者視点から見ても「オフィスの床面積を抑えることで固定費を削減できる」といったメリットがある。
さらに、「多様な働き方を認めることで人材流出を防ぎ、流入を増やせる環境が作れる。また固定費の削減で浮いた資金は、人材育成や新規事業の創出などに活用できる。ハイブリッドワークは従業員にとっても、経営者にとってもメリットを感じられる働き方だ」とジョン氏は補足した。
同社は今後、シームレスにオンラインとオフラインがつながっている環境の構築にとどまらず、oVice上のあらゆるデータを利活用していく。発話回数や接触回数、発話時間や滞在時間などのあらゆるデータをグラフや表で可視化して分析し、施策の検討や実行に生かしていく。
そしてジョン氏は、「oViceは『出会い』を重要なテーマにしている。今後はオフィスという枠組みにとどまらず、出会いが存在するさまざまな事業に挑戦していきたい」と今後の目標を口にして、イベントを締めくくった。