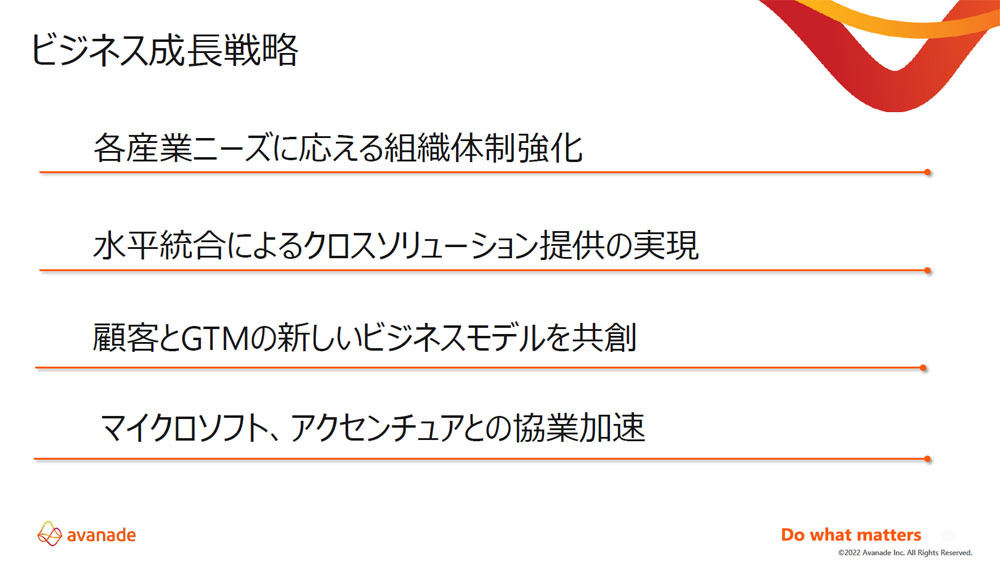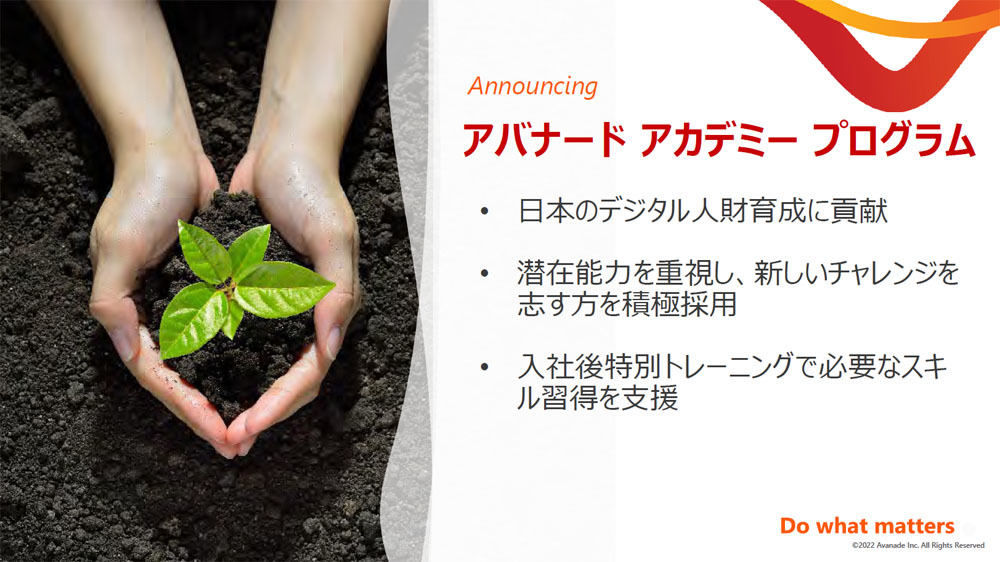アクセンチュアとマイクロソフトのジョイントベンチャーでITコンサルティングを手がけるアバナードは9月28日、オンラインで新年度の事業戦略説明会を開催した。説明会には9月に同社の代表取締役に就任した鈴木淳一氏と、新人事に伴い同 会長に就任した安間裕氏が出席した。
9月に新代表取締役として鈴木氏が就任
冒頭、安間氏はこれまでの取り組みを振り返り「私が代表取締役に就任してから約8年半となるが、アバナードの日本法人の設立から17年が経過し、アバナードの歴史の半分をマネジメントしてきており、当初は200人だった従業員が現在では800人となっている。就任時からグローバルを加速するために、国内外における人材採用の強化したほか、DX(デジタルトランスフォーメーション)が進まない日本において、欧米のオファリングやソリューションをローカライズして提供することでDXをサポートしてきた。主に土台を作ってきた8年半であり、次の世代にバトンタッチするための準備期間だったと認識している」と述べた。
新しく代表取締役に就任した鈴木氏は2008年にアバナードに入社し、日本においてアプリケーション&インフラストラクチャ、モダンワークプレース、ビジネスアプリケーション、データ&AIの4つのソリューションエリアを統括し、ビジネス戦略とデリバリを主導。また、通信・ハイテク業界、パブリックセクターを中心に複数の業界においてITプランニングやエンタープライズアーキテクチャデザイン、プロジェクトマネジメントを手がけてきた。
鈴木氏は2月に刷新したコーポレートビジョン“Advance the World through the power of people and Microsoft”(人とマイクロソフトの力で世界を前進させる)に触れ「より良い未来への鍵は人であり、人にテクノロジーと閃きを与え、責任あるビジネスにパワーを与え、より良い変化を可能にする。力を合わせれば誰にとってもより良い世界を作ることができ、その思いがビジョンに詰まっている」と話す。
同社ではビジネスが堅調に推移しており、昨年度の成長率は40%、従業員数はこの5年間で2倍に増加しているという。一方で、DXの成果や実感ができていない日本企業が多く、実施状況も限定的であることに加え、人材・スキル不足が課題となっており、システムの複雑化がレガシーシステム刷新の阻害要因になっていると同氏は指摘した。
アバナードが注力する4つの領域
そこで、同社は新年度における事業戦略として「パートナー、顧客との共創体制強化」「多様な働き方の支援強化」「デジタル人材の育成と採用の加速」「日本で愛され、貢献する企業に」の4点に注力していく。
鈴木氏は「ビジネスの成長戦略としては各産業ニーズに応える組織体制の強化や、水平統合によるクロスソリューションの提供を実現するとともに、お客さまとGTM(Go to Market)の新しいビジネスモデルを共創し、マイクロソフト、アクセンチュアとの協業を加速させていく」と強調した。
注力産業分野としては金融サービス、通信・メディア・ハイテク。製造・流通、素材・エネルギー、公共サービス・医療健康となり、“アジャイルデリバリー”により、顧客との共創で最適なDXを実現するとしている。
また、同社のグローバルにおけるワークプレース調査によると、日本の回答者の98%が自社は「人」が最優先であり、従業員体験(EX)の変革に取り組んでいると回答しているものの、64%は従業員に働く時間、場所、方法について自由な選択肢を与えるフレキシブルな働き方を可能にできていないと回答。さらに、62%の企業はクラウドベースのプラットフォーム、AIまたは自動化を通じてナレッジの管理と共有を簡素化できていないという。
ただ、ワークプレースとEXはビジネスにもインパクトを与えることから、同社ではワークスタイル選択の柔軟性強化を継続しつつ、日本全国47都道府県をワークプレースとし、グローバルタレントとしてのマインド情勢と育成を支援していく考えだ。
そして、人材育成に関しては9月28日にデジタル人材の育成促進を目的とした新しい採用の取り組みとして「アバナードアカデミープログラム」を開始。これは、潜在能力を重視し、新しいチャンレンジを志す人材を積極的に採用すると同時に、入社後の特別トレーニングで必要なスキル取得を支援する。
そのほか、日本で愛され、貢献する企業となるため「Do What matters」をキャッチフレーズにブランドキャンペーンを開始していることに加え、企業市民活動、サステナビリティへの取り組みを紹介した。
企業市民活動ではアバナードSTEM奨学金や、女性の地位向上プログラムとしてお茶の水女子大学寄付講座プログラム、グローバルキャリア支援、マイクロソフトの技術を活用したプログラミング教育、高専プログラミングコンテストの協賛、ビジネスアイデア&ハッカソンコンテスト「IDEACTIVE JAPAN PROJECT」への協賛など次世代教育支援を実施。また、サステナビリティは地方創生、SDGsアプリ、サステナビリティサービス日本版の支援などを進めている。
最後に、鈴木氏は「変化の多い現代において、お客さまの期待に応え、超えていくために当社が変化と進化を繰り返して成長することが重要だ。日本のDXをけん引するリーディングカンパニーを目指す」と締めくくった。