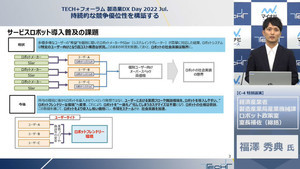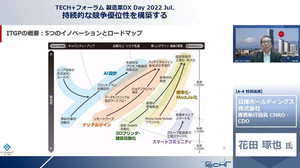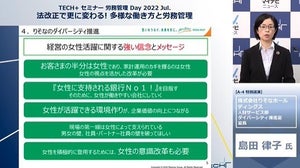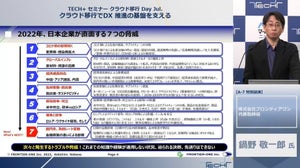DXとデータの組み合わせに異論を唱える人は少ないだろう。ビジネスへのデジタル活用が進む昨今、データの重要性が声高に叫ばれているが、DXの文脈ではデータをどう捉えて、どう活用すべきなのか。
ヤフーでデータソリューション事業本部 事業戦略部 部長を務める野口真史氏が、「ビジネス・フォーラム事務局 × TECH+ EXPO 2022 for Leaders DX Frontline 不確実性の時代に求められる視座」(8月25日、26日オンライン開催)に登壇。DXにおけるデータ活用について同社の事例を交えて解説した。
【ビジネス・フォーラム事務局 × TECH+ EXPO 2022 for Leaders DX Frontline】その他の講演レポートはこちら
DXにおけるデータの役割は目的や手段ではなく「資源」
講演冒頭、野口氏はDXとデータの関係について次のように説明した。
「DXはデジタイゼーション、デジタライゼーション、そしてデジタルトランスフォーメーションとステップを経ますが、各ステップでのデータの役割(立ち位置)は、”データの準備””データの活用””データを前提”となります。一足飛びに向かうのではなく、データを足元からしっかり固めていくことが大切です」(野口氏)
DXはさらに、事業側の「攻めのDX」、組織側の「守りのDX」の2つに分けることができる。特に攻めのDXでは、「顧客体験、提供価値の向上」が目的、「デジタル化」が手段となり、データはそれを円滑に行うための「素材や資源」と位置付けられると言う。
例えば、顧客体験の向上のために、サブスクリプションやSaaS、DtoC(Direct to Consumer)などのビジネスモデルを変革すると、ロイヤリティが高まり、収集できるデータが増える。データからどのような背景で商品を購入したのかなどが分かることで、集客や誰に向けてどのように訴求するのかといった広告アプローチも改善できる。さらにデータが増えれば、それを開発に活かすことができ、さらなる顧客体験の改善につながるという好循環が生まれるのだ。
「データを中心に、改善のプロセスが回ります。ここがDXにおいてデータが重宝される理由ではないでしょうか。データを中心に置いて考え、循環をどう作っていくのかがポイントです」(野口氏)
内製化すべきDX人材は「つなぐ人」
野口氏は攻めのDXに必要なデータ人材にも触れた。
顧客体験や提供価値の向上を目的に、デジタル化を手段とし、そのためにデータを素材や資源として活用する。そのための人材としては、「創る人、活かす人、つなぐ人の3種類が必要」と野口氏は話す。
「創る人」とはエンジニアや開発者など、「活かす人」とはデータを活用して作ったビジネスプロセスを回す、つまり運営する人を指す。野口氏は、大切なのは創る人と活かす人を「つなぐ人」だと言う。ビジネスの現場についての知識を持ちつつ、創る人であるエンジニアにどのようなシステムを作るべきか、自社の商品・サービスはどのような場面で使われているのかなどを伝えるという役割だが、ここは「社内で育成すべき」というのが野口氏のアドバイスだ。
「外部のコンサルなどにお願いしたくなるかもしれませんが、なるべく内製化することにより、自社のドメインを詳細に知っている人が長くビジネスプロセスの改善やDXに関わることができます」(野口氏)